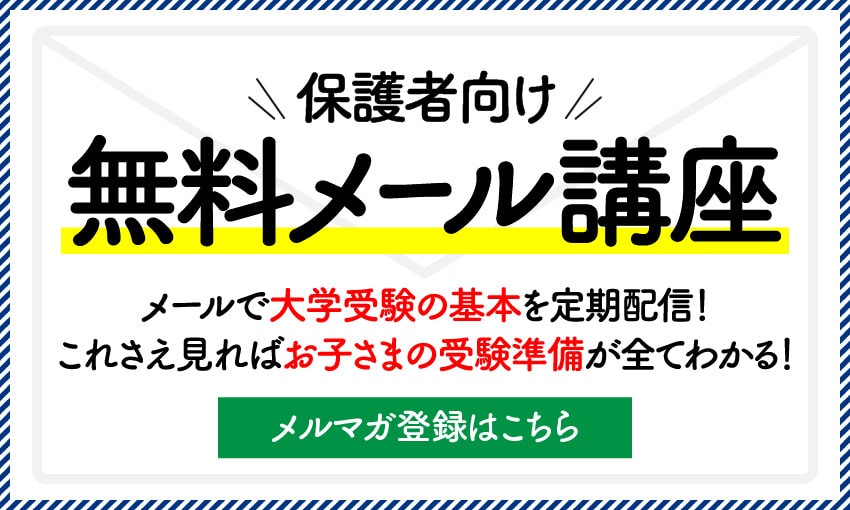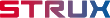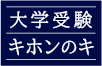志望校の選び方のコツは
「妥協しない」こと!
成績を気にせず、行きたい
大学を目指すべき理由とは?
受験期が近づくにつれて、徐々に志望校や受験勉強について考え始める受験生は多いです。もちろんできることなら、現役で第一志望校に合格したいですよね。
とはいえ、いきなり「一番いきたい大学を選ぼう!」と言われてもなかなかピンと来ない方も多いはず。
むしろ高校生の段階で「明確にやりたいことが決まっていて、行きたい大学もある!」という人の方が珍しいかと思います。
そこでこの記事では、そうした悩みを持つ受験生が知っておくべき「志望校の選び方」に関するコツをご紹介!スタートからしっかり受験に向き合うことで、無事に合格を勝ち取りましょう!
これだけは押さえたい!志望校の選び方に関する考え方とは?
それではここからは、志望校選びで覚えておくべき「受験勉強における基本の考え方」を見ていきましょう!
「HPの流し読み」「資料請求」から始める!
「志望校を決める」と聞くとかなりかっちりした感じがしますよね。確かにこれで受験の目標が決まるわけなので、なんとなく肩肘を張ってしまいそうです。
しかし最初に関しては「なんとなく良さげな大学のHPを流し読みする」という程度のことでもOK!
他にもTwitterなどで大学名について検索するして、在校生の声を拾ってみたりしてもいいでしょう。適当に資料請求するのもアリです。
もちろん「将来これがやりたい!そのためにこの大学に行く!」という受験生はそこを志望校にすれば大丈夫です。
しかし先述の通り、それは少数派。最初からいきなり自分のやりたいことや興味がわかっている受験生はほぼいません。
なのでまずは自分の興味を見つけるために、資料請求やHPの流し読みなどを繰り返し行いましょう!そこから徐々に大学を絞っていけば良いのです。
SNSやHPを見るのは隙間時間で気軽に出来ますからね。電車に乗っている時間など、ちょっと暇になったら見てみるのがオススメです。
もちろんいきなりオープンキャンパスに行ったり蛍雪時代を見る必要もありません。後になれば必要ですが、まずはざっくり調べる程度で大丈夫です。
「志望校に向けた勉強」をするためには学校だけでは不十分!
受験では「志望校合格に向けた勉強」というものが大切です。これは学校の勉強だけでは補ません。それはなぜでしょうか?
学校の勉強は集団授業が基本。そのため、先生が生徒一人一人の目標に合わせた細かい指導をすることが物理的にできません。どうしても教科書に沿った平均的な内容しか指導できないのです。
しかし志望校というのは一人一人違うもの。しかも現在の学力にも差があります。そのため、それらを踏まえ自学自習や塾で自分に合った勉強に取り組める環境を整えることが大切です。
レベルを気にせず『行きたい大学』を受験させよう!
ほとんどの受験生が、なるべくなら第一志望校に受かりたいと考えているでしょう。それは当然ですよね。
しかしその一方で「できれば現役で入りたいから、浪人してまで第一志望校を目指すのはちょっと・・」という気持ちもあるのではないでしょうか?
確かに志望校の偏差値が今の高校よりもかなり高い場合、浪人の心配が出てきます。また金銭的にも、できれば無理せず現役で合格したいというのが本音ですよね。
しかし、志望校に関しては「純粋に行きたい大学」を目指すべきです!それはなぜでしょうか?
理由はシンプルで「モチベーションが上がらないから」。受験勉強は長く孤独な戦いです。友人と一緒に勉強しても、最終的には1人で受験しなくてはいけません。そのためにはモチベーションの有無がかなり重要になってきます。
それに「第一志望校でないと勉強できない」という内容があると、そこを目指せないことによるモチベーションの低下もあるでしょう。
モチベーションがないと自学自習にも取り組みづらいので、まずは純粋に行きたい大学を目指すべきです。
志望校の合格最低点の勉強ができればOK!
とはいえ、いくら行きたい大学を目指せるとはいえ「いきなり偏差値の高い大学に挑戦するのはやはりリスキーでは?」とも感じるでしょう。確かに難関大学であれば試験問題のレベルも上がるので、点数獲得が難しいと思いますよね。
しかし受験においては、無理に高得点を取る必要はありません。あくまでも「志望校定める各教科の合格ライン」を越えればOK!
なので難関大学を受験したとしても、丁寧に出題傾向を分析して計画を立て、数字ベースで自分の実力を把握しながら勉強していけば合格可能性はグッと上がります。
もちろんガムシャラな勉強では意味がありません。計画を立てなければ本来受かっていたであろうレベルの大学に落ちてしまいます。
ハイレベルな大学を目指すとなっても結局必要なのは最低点なのでそこまで身構える必要はありません!
3,000時間の勉強で「絶対に受からない大学」というのはなくなる!
それでもなお、現時点の偏差値よりも高いところを目指すとなると不安になる方も多いでしょう。
しかし、受験では3,000時間の勉強で合格率をグッと上げることができるのです。
もちろんしっかりと計画を立てて勉強したらの話ではありますが、志望校に必要な勉強を把握しそれに集中して取り組めたらどんな大学でも合格可能性はあります。
こうしたこともあるので、モチベーションを高める意味でも純粋に行きたい大学を志望校にしましょう!
保護者はどのように志望校選びと向き合うべきか?
ここまでは受験生に向けた「志望校の選び方」のアドバイスでしたが、こうした考え方を踏まえ上で、保護者としてはどのように志望校選びに関するアドバイスをすればいいのでしょうか?
子供にアドバイスをするなら、まずは現在の受験知識を身につけよう!
まず前提として、保護者の方が子供に受験のアドバイスをする場合は「現在の受験知識を身につけている」ということが大切です。
なぜなら、現在の入試制度は多様化してる上に大学の種類も様々あるので、親世代の知識が通用しないため。
もちろん教科ごとの細かい内容まで覚える必要はありません。ただしアドバイスをするのであれば、最低限受験に関する知識や考え方は身につけておく必要があるでしょう。
親だからこそわかる「子供の興味」に関するアドバイス
親は小さい頃から子供を見てきた存在です。だからこそ「本人では気づけない良いところ」や「興味を示していたもの」などがわかる場合もあります。
そうした「子供が無意識に心を動かされていたこと」などについて話すと良いかもしれません。
子供の興味を引き出して志望校を選ぶためのお手伝いをするようなイメージですね。
「絶対に現役で!」というプレッシャーはダメ!
お金の問題もあるので「子供にはできれば現役で入って欲しい・・・」という気持ちはわかります。しかし決してその件でプレッシャーを与えてはダメです。
子供は受験する当人なので、現役合格を目指すべきだということは痛いほど理解してます。そうしたプレッシャーをすでに受けている子供に対して保護者からもハッパをかけてもほぼプラスにはなりません。
もちろん家庭の事情もあり浪人できない、という場合もあるはずですから、志望校の制約を早めに伝えておくことも必要です。
これを伝えるときも「こういう理由で現役でしっかり行ってほしい、行けるような大学を」というふうに伝えてあげるようにして、強い語調にならないように気をつけましょう。
わざわざ「浪人でも良い」と伝える必要もありませんが、子供の志望校をきちんと理解した上で、話し合いをしっかり重ねていくこと、そして志望校が決まったら静かに見守ることを意識しましょう!
併願校は傾向が似た大学を中心に選ぶ!
先ほどの「現役のプレッシャーを与えない!」に絡みます。おそらく浪人を回避するために併願校を受験する方も多いでしょう。なかなか「第一志望校一本!」という人はいないかもしれません。
併願校自体はもちろんリスクヘッジとして受験しても大丈夫です。しかしその「受け方」には気をつけなくてはいけません。
併願校があるということは、その大学に合わせた勉強をしないといけないということ。なのでもし、第一志望校と傾向が全く違う大学を受験するとなると、それだけで勉強量が増えてしまうのです!
極力第一志望校をメインとした勉強をした方が合格確率は上がります。なのでもし併願校を選ぶとしても、なるべく出題傾向が似ている大学を選ぶといいでしょう。
志望校選びからサポートしてくれるような塾や予備校を一緒に探す
志望校に合格するためには、ただ塾に行かせてあげれば良いというわけではありません!授業を受けるだけでなく、「志望校選びから合格までのしっかりしたサポートがある塾」を一緒に選ぶということが大切です。
塾というのは安い買い物でありませんからね。そうした料金面の問題もあるので一緒に選んだ方がいいでしょう。
どういうサポートがあるのかをしっかり確認できれば、保護者としても納得して払いやすくなりますよね!
保護者の助けも借りつつ最後は受験生自身の勝負!
ここまで様々なことをご説明してきましたが、最終的に受験をするのは受験生自身。
こうしたことを覚えておき、しっかり自分に合った志望校を見つけるのが大切です。保護者の方のアドバイスに耳を傾けるのももちろん大切ですが、最後は自分の力を信じて挑みましょう。
また親としては困っている時に手を差し伸べたくなるものですが、過剰に口出しをするのも良くありません。色々なことを言いたくなりますがそこはグッと我慢!
子供の取り組んでいる勉強を信じて適度にアドバイスをしつつ、塾選びの手伝いなどを行うことでサポートしていきましょう!