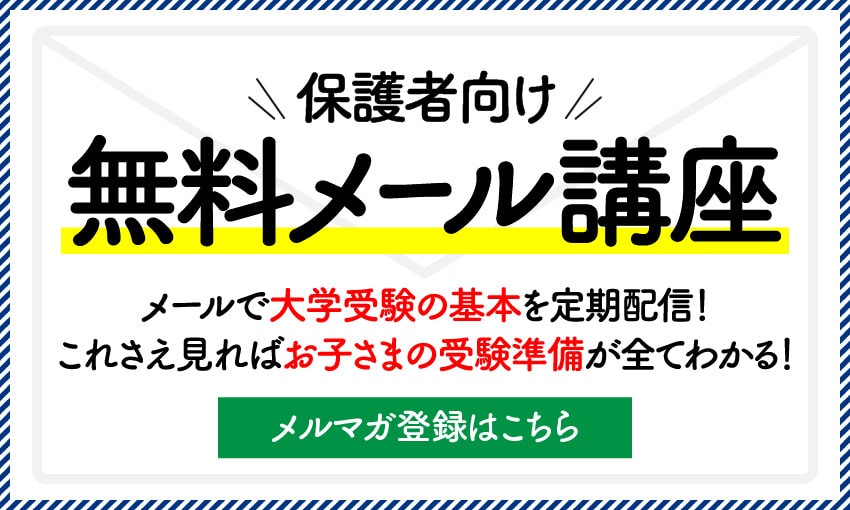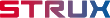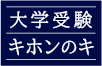大学入学共通テストとは?
センター試験との違いも比較!
※こちらの記事は「2021年度〜2024年度入試」で実施されている大学入学共通テストについてのもので、古い情報となっています。新課程での2025年度以降に実施される入試についてはこちらの記事を参考にしてください。
2021年度からの入試改革に伴い、センター試験は名称が「大学入学共通テスト」に変わります。
新しく導入される選抜方式で、記述式問題の延期など最初に発表された内容からも変更点がありました。
とはいえ「そもそもセンター試験・共通テストってなんなの?みんな受けるの?」「何に使うテストなの?」といった疑問を持っている人も多いはずです。まずはそもそも「共通テストとはなにか?」というところから見ていきましょう。
大学入学共通テストとは?
大学入学共通テスト
| 試験日 | 1月13日以降の土日 (2025年度は2025年1月18日(土)および19日(日)) |
| 受験科目 | 6教科30科目から選択 |
| 出題傾向 | マーク式 思考力・判断力・表現力が重視される問題も |
「大学入学共通テスト」は、センター試験に変わって2021年度から実施される共通入学試験で、様々な大学で共通して利用できるテストのことです。1月中旬に実施され、ほとんどの国公立大学ではこの「共通テスト」の点数と大学ごとの「個別試験」の点数で合否を判定しますし、私立大学でも一部利用するところがあるなど、多くの受験生が受験するテストになっています。
出題される受験科目は7教科21科目の中から選択で、共通テストの時間割としてはまだ出されていませんが、センター試験同様、1日目が社会・国語・英語、2日目が数学・理科と考えられます。
これらの科目の中から、志望大学で求められる科目を出願時に選択し、それをすべて受けることになります。
問題形式はマークシート式で、下記に記載されているような思考力・判断力・表現力が重視される出題が今後増えるようになります。
このように多くの高校生・受験生が受ける試験のため、高校3年生についてはほとんどの高校でまとめて共通テストの願書を出してくれます。
ただ、浪人生は自分で出す必要があるため注意が必要です。
基本的には9月頃に願書の提出・受験料の振り込みがあるため、忘れないようにしましょう。
共通テストって受験しないといけないの?
多くの高校生・受験生が受けるとはいえ、「必ず受験しないといけない」というわけでは有りません。私立大学で共通テストを全く使わない入試形式だけを利用する人がその一例です。たとえば「絶対慶應義塾大学に行きたいから、慶應しか受けない」という人は、共通テストを必ずしも受ける必要はありません。
ただ、私立大学でも後述のように「共通テスト利用入試」があったり、入試改革で共通テストの点数が必須になったりしているところもあります。チャンスが多いほうがいい、と考える人は受けておいたほうがよいでしょう。
また、国公立大学ではほぼ共通テストの点数が必須ですので、国公立大学を目指す人は必ず受験することになります。
共通テストを使う場面
このように、多くの受験生が受ける「共通テスト」ですが、大学受験ではどのような場面で使うのでしょうか?
国公立大学・私立大学の合否判定
「大学入学共通テスト」+「大学別の独自試験」
の合計点で合否判定されます。
国公立大学の9割が共通テストを合否判定で利用するため、原則受けなければなりません。
また、大学によって必要な科目が違います。
例えば東大ではセンター試験と同様に、文系は5教科8科目または 6教科8科目、理系は5 教科7 科目を課されます。
また、共通テストになってからは英語のリスニングも合否判定に利用されるようになります。
いっぽう早稲田大学国際教養学部では、必要な科目が国語+選択科目で、東大とは違い英語は合否判定に利用されません。
私大では共通テストが使わないことが多いのですが、最近の入試改革で早稲田、立教など一部の私立大学で取り入れられるようになりました。
上記のように、各大学によって共通テスト利用の有無や必要な科目が違うため、志望校の入試情報ページは必ず確認しましょう。
国公立大学の2段階選抜
2段階選抜とは、いわゆる「足切り」です。
共通テストの点数が各大学で課せられる基準点に満たない受験生を二次試験の受験対象外として一律不合格にふるいにかける選抜方式です。
ほとんどの国公立大学では2段階選抜を実施しており、東大など上位国公立では定員の◯倍、という決め方で実施し、個別試験を受験できる人数を絞っています。
たとえば、定員400人で1段階選抜を4倍としているところは、出願者の共通テストの点数で上から1600人だけが2次試験を受けられます。そうすると倍率が4倍になります。
だから、2段階選抜を実施している大学を受ける場合は、「1段階選抜ライン」(足切りライン)を超えているかを見極めないといけないのです。
しかし、「1段階選抜ライン」(足切りライン)は発表されません。発表される前に出願する必要があり、出願のやり直しはできません。
そのために、予備校などが共通テストの自己採点の点数を集めて志望校別の予想ボーダーを例年公開しています。
しかし、このボーダーはあくまで「予備校に自己採点を提出した人」のデータのため前後しやすく、過信できません。とはいえその中でも、予想ボーダーを参考にして最終的に出願するか決める必要があります。
足切りラインギリギリなら、「それでもチャレンジしたい」と特攻してもよいですが、その分2次試験を受けられず不戦敗になるリスクもあります。
そのリスクを避けて受験校のレベルを下げてもよいですが、それだと第一志望はチャレンジできません。
なので、受けたい大学を受けるためにも、特に国公立受験者は共通テストできちんと点を取らないといけないのです。
大学入学共通テスト利用入試
従来のセンター試験利用入試と同じく、私立大学で「大学入学共通テスト利用入試」を利用すれば、共通テストの点数次第では大学別の独自試験を受けずに合格することも可能です。
「大学入学共通テスト」の結果を活用する場合は主に2通りの方法があります。
・大学入学共通テストの結果のみで合否判定
・大学入学共通テストと独自試験の両方で合否判定
共通テストの利用のみの合否判定の場合、合格水準と倍率が高いので、主に志望校よりも難易度が下の大学で滑り止めで利用されることが多いです。
たとえば、第1第2志望で国公立大学を受験し、滑り止めとしてワンランク下の私立大学を共通テスト利用で複数校併願して受けるなどです。
「大学入学共通テスト利用入試」で受験すると各大学の受験会場に行かなくても出願出来るため、併願校が遠方の場合や現地に行かなくても受験出来るので、効率良く受験を進められます。
ただし、「大学入学共通テスト利用入試」は定員が少なく、各予備校で出している合格ボーダーも前後しやすいため、確実に合格出来るわけではないので注意してください。
従来のセンター試験と何が違うのか?
この「大学入学共通テスト」は、もともと「大学入試センター試験」として実施されていたものが2021年度入試から変更になるものです。
その際、
・国語・数学での記述問題の導入
・英検など外部試験の活用
などが予定されていましたが、既に延期が決定している内容もあるため、変更は各科目の細かなところにとどまり、大幅な変更はまだ先になりそうです。
2024年度からは新指導要領の影響で、情報という新設の科目などなど受験科目に影響が出たり、外部試験の活用が本格的に導入されるなどより大幅に本格的に入試改革が進むでしょう。
試行調査の内容は以下から確認できるので、対策するために必ず確認しましょう。
国語・数学での記述問題の導入延期などから、「大学入学共通テストはセンター試験と特に変わらないのでは?」と捉えている受験生もいるでしょう。
しかし、実際は出題傾向の変更などがあるため、変更点を理解した上で受験勉強を進める必要があります。
英語のリーディングとリスニングの配点比率が同等に
| リーディング (旧筆記) | リスニング | |
| 旧センター試験 | 150点 | 50点 |
| 大学入学共通テスト | 100点 | 100点 |
「大学入学共通テスト」で最も大きく変わる科目は英語です。
共通テストの新設にあたって、英語の筆記はリーディングという名称に変わりました。
旧センター試験では、リスニングの配点は全体の4分の1でしたが、「大学入学共通テスト」から上記のような配点比率になりました。
リスニングは一朝一夕で身につくものではないので、しっかり勉強しましょう。
思考力・判断力・表現力を重視
「大学入学共通テスト」では、単なる知識を問われる問題だけでなく、思考力・判断力・表現力が求められる問題が重視されます。
国語、数学I・Aでの記述問題の導入は延期されたため、2021年度入試の時点では大きく問題の方向性は変わらないと思われます。
どこまで思考力を問う問題が出るかわかりませんが、変更点が出てくる可能性もあるため、最新の情報は常にチェックしましょう。
実用的な文章を題材に
「大学入学共通テスト」では、実用的な文章や、日常的な出来事など身近にあるものを題材とした問題が出題される傾向があります。
日常的な出来事を題材にした問題は、日常生活や新聞記事など題材とします。
大学受験で活用するには
各大学の一般選抜では、旧センター試験と同じように「大学入学共通テスト」の点数を活用できます。
・「大学入学共通テスト」+「独自試験」の点数から合否判定
・「大学入学共通テスト」のみの点数から合否判定
主に上記の2パターンで合否判定されるケースされるので、「大学入学共通テスト」で高得点を取ることは志望校合格により近づけます。
一部の国公立大学では「2段階選抜」でも活用されます。
また、今までは学校の成績と課外活動が評価されれば学力テストを受けずに合格できた「学校推薦型選抜」「総合型選抜」でも、入試改革の影響で共通テストの提出が必要になることが多くなります。
どの選抜方式でも「大学入学共通テスト」で高得点を取れば、志望校合格率が高くなるのできちんと把握した上で勉強に取り組みましょう。
まとめ
ここまでの内容をまとめておくと…
「大学入学共通テスト」は、センター試験に変わって2021年度から実施される共通入学試験。
主に、国公立大学を志望する人と私立大学の「大学入学共通テスト利用入試」を活用する人が受験します。
従来のセンター試験とは違い、思考力・判断力・表現力が求められる問題が重視され、英語のリーディングとリスニングの配点比率が同等になるなどの変更点があります。
現状、共通テストの影響を最も受けるのは英語くらいです。
まずは大学受験で出題される範囲を終わらせ、11月以降に共通テストや志望校の過去問に取り組めるように勉強を進めましょう。