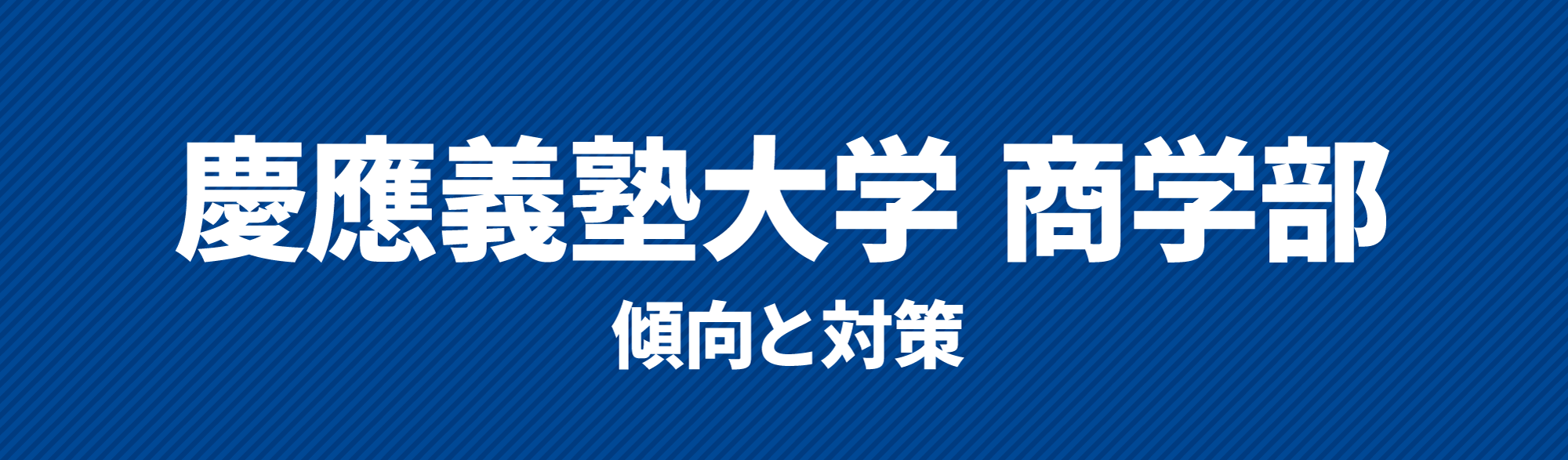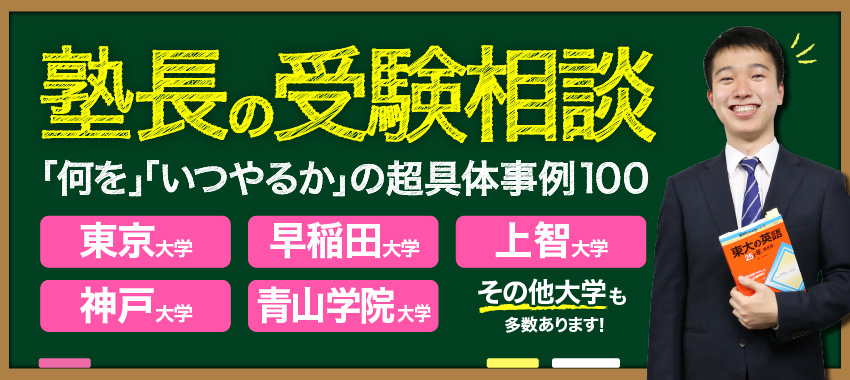難関私立大学として知られる慶應義塾大学。著名な卒業生や経済人を数多く輩出している大学です。幅広く専門的な授業に魅力を感じて入学する人が多いようです。商学部では商業・経営・経済・会計の主力4分野に加えて、数学系の授業も自由に履修することができます。将来の夢や興味のある学問が定まっていない方には、オススメの学部です。
2025年度入学入試から、学習指導要領の変更により、一部大学で配点・科目の変更などが予定されています。順次記事を更新しておりますが、この記事は変更前のものとなりますので、配点等は必ず大学公式HPを参照してください。
Part.1 慶應義塾大学商学部の試験・出願情報
慶大は学部ごとに試験問題が異なります。この章では、商学部の入試形態について確認していきます。試験方式が2つあるので、科目選びには注意しましょう。また「論文テスト」という小論文が課されるので、独自の対策が必要になることに気をつけてください。
商学部の試験日・入試形態・出願について
| 一般入試 | |
|---|---|
| 期日 | 2月14日 |
| 共通テスト | 不要 |
| 1次選考 | なし |
| 出願時期 | 12月~1月 |
| 科目 | A方式:外国語(英語)・地理歴史(世界史B・日本史B・地理Bから選択)・数学 B方式:外国語(英語)・地理歴史(世界史B・日本史B・地理Bから選択)・論文テスト |
2021年度入試より一般選抜において主体性評価などの自己評価を出願時に提出することになっています。商学部は、他の学部と違う点がいくつかあります。1つめは地理を選択できる点ですが、私大で地理を必要とするところは多くないので、地理を選択するのはあまりオススメしません。A/B方式ともに地理歴史が必要になるので、自身の得意・不得意に合わせて選択しましょう。
商学部の特徴的なところのもう1つは、国語は不要な反面、A方式の「数学」またはB方式の「論文テスト」が求められるという点。数学受験のA方式が定員480人、論文テスト受験のB方式が定員120人となっており、B方式のほうが倍率が2倍くらい高いです。論文テストは論文や資料を参考にして、与えられた問いに答えていくという形式です。年度によって「読解力を中心に論理的思考力を問う」場合と「数学的思考を求めて、その中で論理力を測る」という場合があります。基本的には大問2つ構成で、上記の2パターンが1つずつ出されているのが特徴です。広い考察力や基本的な計算力、長い問題文を正確に読み解く読解力を普段から鍛えておきつつ、過去問を使って演習を重ねておくことが大切です。
Part.2 商学部の配点と目標点【理系】
次に、配点と目標点数をパターン別に紹介していきます。得点調整が社会2科目間で「年度によって」行われており、2020、19年度は実施されています。合格最低点と受験者平均点が公開されているので、それらのデータから目標点数を換算していきます。
目標点数
A/B方式共通の科目の配点は英語200点、地理歴史100点です。A方式の数学は100点、B方式の論文テストも同様に100点で、総合400点です。経済学部などで行われているような一次選考はありません。
例年の合格最低点は、数学がないB方式の方が得点率が高くなっており、A方式が60~65%、B方式が72~77%を推移しています。
| 合格最低ライン目安 |
|---|
| 350点(科類により異なる) |
| パターン1:A方式 | |
|---|---|
| 英語 | 150/200点 |
| 地歴 | 80/100点 |
| 数学 | 50/100点 |
| 合計 | 280点 |
| パターン2:B方式 | |
|---|---|
| 英語 | 160/200点 |
| 地歴 | 80/100点 |
| 論文テスト | 70/100点 |
| 合計 | 310点 |
科目別に受験者平均得点率を見ると、英語と地理歴史が60%で安定している一方で、数学と論文テストは出題内容によって大幅にアップダウンしています。
数学の受験者平均得点率は、2019年度の50%から2020年度の30%まで激減しています。数学の平均点が30%~50%と低いとはいえ、数学で半分以上はとっておかないと点数が安定しません。
2019の論文テストは、「暗号化」のシステムという捉えづらいテーマの出題だったため平均得点率が58%なのに対し、数学的要素が少なく単純な確率の計算だった2020年は70%近い得点率を叩き出しています。70%近い点数の時に、この論文テストで差をつけるのは難しいですから、英語・地歴で確実に点をとっておくことが重要になってきます。
全体の最低得点率が8割近い年もあることを考えると、英語・社会は8割を目指しておきましょう。
| 模試一覧 | |
|---|---|
| 5月 | 駿台atama+共通テスト模試 |
| 7月 | 駿台atama+共通テスト模試 |
| 8月 | 河合全統共通テスト模試 |
| 9月 | 駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試 |
| 10月 | 河合全統共通テスト模試 代ゼミ慶大入試プレ 駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試 |
| 11月 | 河合早慶オープン 河合全統プレ共通テスト |
| 12月 | 駿台atama+プレ共通テスト |
*点数推移:準備中
河合の「早慶オープン」では選択問題と全体問題があり、選択問題は志望大学・学部の問題を選べますが、全体問題では早慶の問題が混じって出題されます。志望大学・学部以外の問題も出題される難しさもあり、例年の「早慶オープン」ではD判定の人がほとんどのようです。C判定以上を目指して挑戦しましょう。結果が悪くても、気にせずに復習をおろそかにしないことが大切です。代ゼミと駿台が共催している「慶大入試プレ」では、学部別に問題が出題され、より本番に近い形式で出題されるようです。慶應大学に特化した模試は多くありませんので、「早慶オープン」と「慶大入試プレ」は受けておきましょう。
併願校・志望変更
| 慶應内併願 |
|---|
| 経済学部、文学部など |
| 私立大併願 |
|---|
| 明治大などMARCH、日東駒専 |
| 国公立大併願 |
|---|
| 東京大、一橋大、京都大 |
商学部は試験方式に関わらず「英語・地歴」が必須科目なので、慶應の他学部や他の私大を受験しやすい傾向にあります。
慶應内で併願する場合は、経済学部がオススメです。特にA方式の人は絶対に経済学部と併願しましょう。商学部の人は経済学部の併願が多く、経済学部のA方式は「英語・数学・小論文」、B方式は「英語・地歴(世界史Bまたは日本史B)・小論文」であるため、小論文の過去問対策や現代文の勉強をきちんとしておけば、A/B方式のうち得意な方を選ぶことができます。経済学部はA/Bともに倍率はあまり変わらないため、難易度は大きく変わりません。B方式の人が併願する場合は経済学部もB方式(英語・地歴・小論文)での受験がよいでしょう。商学部B方式は倍率が高く併願をしっかり組んでおきたいので、文学部などの他学部を狙っておく戦略もありです。
慶應より下のレベルの併願校にする場合は、「古文」の勉強が必要になります。早めに古文の対策をして、MARCHレベルに対応できるようになっておかなければなりません。オススメの私立大学は商学部がある明治大学などです。
ちなみに早稲田大学の商学部は英語が長文メインで、比較的特殊な対策は不要なため、併願することも可能です。しかし、早稲田商の国語では漢文が数問出題されるので、漢文の勉強は最低限必要になります。しかも、慶應と早稲田では傾向が大きく異なるため、あまり併願には向いていません。
最上位国公立を受験する場合には、数学を使うことができる慶應の商学部を併願するのは良い選択肢だと思います。慶應商をA方式で受験すれば、倍率的にも比較的ラクに受けられそうです。
慶應義塾大学の受験相談事例集
Part.3 科目別の勉強法と攻略法
ここからは過去問の傾向や具体的な攻略法を分析していきます。各科目のポイントだけでなく、オススメの参考書と対策時期を紹介します。受験に必要な情報を有効に活用していってください。
英語
大問が8つと多く、そのうち7つが長文を中心とした出題です。長文の読解や空所補充などボリューミーなので、時間内でどのくらい正確に解けるかがポイントになります。残りの大問も空所補充が中心に出題されるので、文法や単語の理解が重要になってきます。夏までには基礎を完璧にし、夏以降は「ポラリス3」や「やっておきたい1000」レベルの長文問題集を短い時間で解けるように訓練してください。
本番で8割程度を目指しましょう。

慶應義塾大学商学部 英語の対策
地理歴史
地理は基本的なレベルをまず把握することが重要なので、高3の夏前までに「スタディサプリ」などで一通り系統地理・地誌を入れていきましょう。慶應の場合、歴史的背景と絡めた問題や特定地域の問題が多く出題される傾向が強いため、夏以降は各国地誌を資料集などで深堀りしながら、過去問演習を中心に対策していく必要があります。
日本史と世界史は、高2の冬〜高3の春頃には学校のペースより少し早めに「スタディサプリ」などで通史の理解を進めて、高3の夏前には一通り全範囲を終えたいところです。難しい単語も出題されますが、基本単語が押さえられれば8割は取れる問題ですので、まずは基本問題で絶対に点を落とさないことを目指しましょう。通史の流れを優先して押さえ、秋ごろから一問一答でマイナーな単語も含めて完璧にしましょう。

慶應義塾大学商学部 世界史の対策

慶應義塾大学商学部 日本史の対策

慶應義塾大学商学部 地理の対策
数学
A方式の数学は、大問4つ構成で、1A2Bから出題されます。すべて空所補充形式なので、部分点がもらえないことに注意しましょう。夏休みには共通テスト形式の問題集やセンター(共通テスト)の過去問で、誘導に乗りながら解くコツを身につけておきましょう。秋以降からは更に難易度を上げて問題に取り組むべきです。「確率+三角比」「ベクトル+関数」といった分野横断的な問題ばかりなので、「良問プラチカ」や慶應の他学部の数学の過去問などをたくさん解いて、解き方の思考を身につけておかなければなりません。50%以上の得点率が目安なので、大問4中2つ完答を目指して、着実に取れる分野を作っておきましょう。

慶應義塾大学商学部 数学の対策
論文テスト
B方式の「論文テスト」は、年度によって内容が大きく異なり、それによって平均点も大きく上下します。商学部的な内容(経済や経営の話)とは直接関係しないようなものもあります。計算・数学的思考が入る場合でも、確率論や経済学・経営学の視点が必要なものが多い印象です。設問形式のほとんどは、選択肢から適切なものを選ぶ「穴埋め」形式です。「下線部の意味と最も近いものを選ばせる問題」が出題された年度もあり、原則として国語力が求められていると言えます。過去問などで、出てきた単語の定義などをきちんと確認していくことが重要になってきます。もし計算問題が出題されても、正確に文章内の説明を読み取って、基本的な計算が出来れば問題なく解けるでしょう。
オススメの勉強法は、「システム現代文」シリーズなど基本的な現代文の学習をして、時間があれば「ちくま評論選」などで難しめで幅広いテーマに触れておくことです。また、「キーワード読解」を使ったり、文章中に出てきた単語を辞書で調べたりするなどして、言葉を広く正確に知っておくのが大切です。
さらに、数学の「確率」「数と式」あたりの領域は、きちんと理解をしておくべきです。学校のテストレベルを軽く復習しておき、計算問題には慣れておきましょう。
一番大事なのは、いかにしっかり過去問をやり込めるかです。過去問をやりこみ、過去の問題傾向や出題された内容を把握し、穴埋め形式のものをどう解くか自分なりに分析してみましょう。
【準備中】慶應義塾大学商学部 論文テストの対策