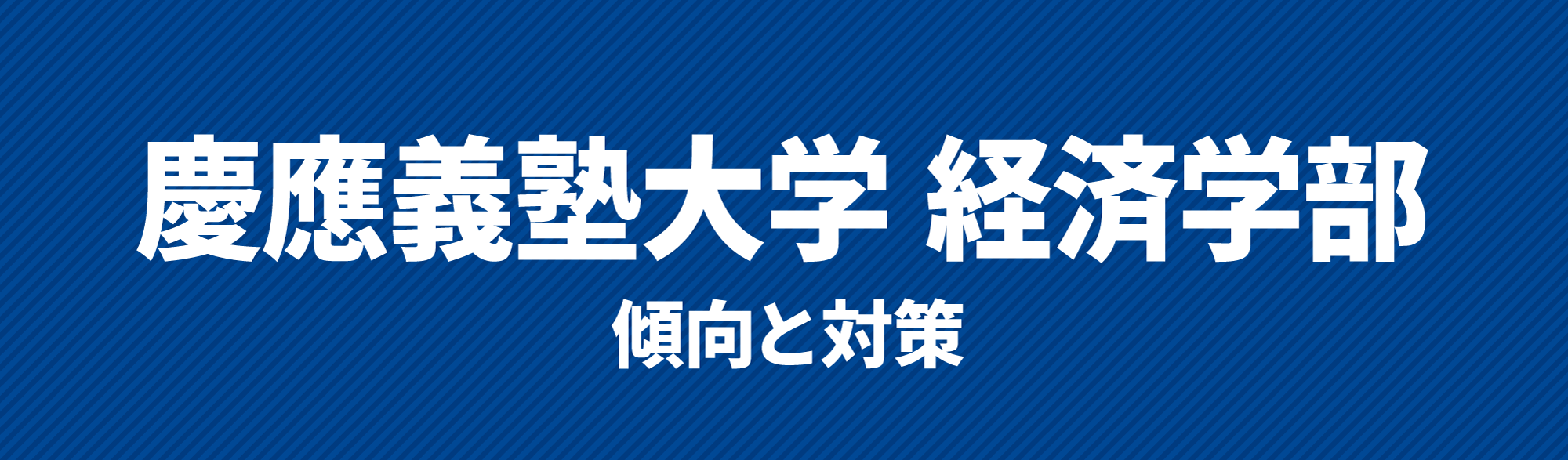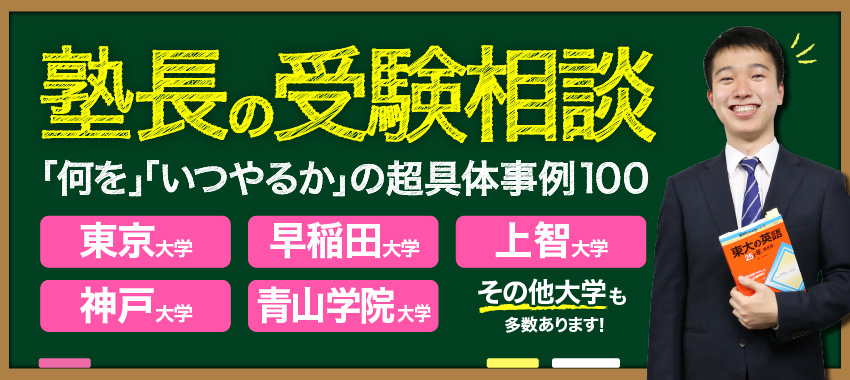難関私立大学として知られる慶應義塾大学。著名な卒業生や経済人を数多く輩出しています。幅広く専門的な授業に魅力を感じて入学する人が多いようです。経済学部は就職に強く、認知度も高いので、人気学部の一つです。
2025年度入学入試から、学習指導要領の変更により、一部大学で配点・科目の変更などが予定されています。順次記事を更新しておりますが、この記事は変更前のものとなりますので、配点等は必ず大学公式HPを参照してください。
Part.1 慶應義塾大学経済学部の試験・出願情報
慶大は学部ごとに試験問題が異なります。この章では、経済学部の入試形態について確認していきます。経済学部は試験方式が2つあるので、科目は戦略的に選びましょう。
経済学部の試験日・入試形態・出願について
| 一般入試 | |
|---|---|
| 期日 | 2月13日 |
| 共通テスト | 不要 |
| 1次選考 | あり |
| 出願時期 | 12月~1月 |
| 科目 | A方式:外国語・数学・小論文 B方式:外国語・地理歴史(世界史B・日本史Bから選択)・小論文 |
2021年度入試より一般選抜において主体性評価などの自己評価を出願時に提出することになっています。
定員はA方式が400人以上、B方式が200人程度となっており、数学受験の方が門戸が広いことが分かります。A/B方式で倍率はほとんど変わりませんが、私大は数学の難易度が高いことが多いので注意しましょう。
2段階の選考が行われ、「1次選考」「最終選考」という形で区切られています。B方式では、英語の200点の中でも基本的な90点分の問題が「1次選考問題」となっており、A方式の場合は英語の90点分に加え、数学150点のうち70点が対象です。この1次選考問題で一定以上の点数が取れていないと、そこで不合格となってしまいます。どの問題が1次選考の対象となるかはわからないので、基礎問題は確実に取れるようにしておきましょう。
Part.2 経済学部の配点と目標点【理系】
配点と目標点数をパターン別に紹介していきます。経済学部は成績標準化による得点調整は社会2科目間で「年度によって」行われています。2020、19年度はいずれも実施されていません。合格最低点と受験者平均点が公表されているため、それらのデータから目標点を換算していきます。A方式とB方式それぞれのパターンを参考にしてみてください。
目標点数
A/B方式共通科目の配点は英語が200点、小論文が70点です。また、A方式の数学は150点、B方式の歴史(世界史Bまたは日本史B)も同様に150点です。歴史の出題範囲は世界史が1500年以降、日本史は1600年以降が中心となっています。各科目の平均点などが公表されていないのでどちらが有利かは分かりませんが、普段の勉強の定着度やモチベーションなどを考慮して、得意な方を選択してよいと言っていいでしょう。
配点が高い英語と数学でいかに点数を確保できるかが、得点するうえで重要になってきます。先述のように2段階選抜が課されるので、基本的な問題はきちんと点を取れるように準備しておきましょう。1次選考の最低点はいずれも60%〜70%程度ですが、どの問題が1次選考対象かわからない点を考慮すると、80%以上を確保して安心しておきたいところです。また、問題全体での合格最低得点率はA/B方式ともに55%~65%を推移しており、受験者平均得点も近い値を取っています。難易度によって大きな差がありますが、目標得点率を66%と設定してパターン別に目標点数を考えていきます。
| 合格最低ライン目安 |
|---|
| 280点 |
| パターン1:A方式 | |
|---|---|
| 英語 | 145/200点 |
| 小論文 | 35/70点 |
| 数学 | 100/150点 |
| 合計 | 280点 |
| パターン2:B方式 | |
|---|---|
| 英語 | 130/200点 |
| 小論文 | 30/70点 |
| 社会 | 120/150点 |
| 合計 | 280点 |
1次選考がある英語・数学は、配点も高いため、7割近く確保しておきたいです。1次選考の対象問題を8割程度取ることができれば、それだけで英語約70点、数学約50点程度は確保できます。合格点に達するために、追加で各科目で倍の点数を上積みしていきましょう。数学は3分の2の得点率を達成するため、全6問中完答4つを目指し、そうでなくても完答3つ・部分点2つという形を狙います。数学は高得点が狙いにくいですが、地道に計算していけば解ける問題も含まれているので、数学が苦手な人はそこで点を逃がさないようにしましょう。また、B方式の歴史はA方式の数学に比べて点を稼ぐことができるので、8割を狙っておくべきです。
| 模試一覧 | |
|---|---|
| 5月 | 駿台atama+共通テスト模試 |
| 7月 | 駿台atama+共通テスト模試 |
| 8月 | 河合全統共通テスト模試 |
| 9月 | 駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試 |
| 10月 | 河合全統共通テスト模試 代ゼミ慶大入試プレ 駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試 |
| 11月 | 河合早慶オープン 河合全統プレ共通テスト |
| 12月 | 駿台atama+プレ共通テスト |
*点数推移:準備中
河合の「早慶オープン」では選択問題と全体問題があり、選択問題は志望大学・学部の問題を選べますが、全体問題では早慶の問題が混じって出題されます。志望大学・学部以外の問題も出題される難しさもあり、例年の「早慶オープン」ではD判定の人がほとんどのようです。C判定以上を目指して挑戦しましょう。結果が悪くても、気にせずに復習をおろそかにしないことが大切です。代ゼミと駿台が共催している「慶大入試プレ」では、学部別に問題が出題され、より本番に近い形式で出題されるようです。慶應大学に特化した模試は多くありませんので、「早慶オープン」と「慶大入試プレ」は受けておきましょう。
併願校・志望変更
| 慶應内併願 |
|---|
| 商学部、文学部、法学部 |
| 私立大併願 |
|---|
| 明治大、法政大、立教大、青山学院大など |
| 国公立大併願 |
|---|
| 東大、一橋大 |
慶應内の併願で最も多いのが商学部と経済学部で、2000人以上が併願しています。商学部はA方式が「英語・地歴・数学」、B方式が「英語・地歴・論文テスト」なので、経済学部と商学部で同一の方式を受けるのが望ましいです。ただ、商学部B方式では、論文やデータを読み取って問いに答えるという形式の「論文テスト」が出題されます。文章を読み込んで主張をまとめる小論文とは形式が少し異なるので、対策は別途必要になります。
小論文の負担を小さくするには、小論文の傾向が近い「文学部」、「法学部」を受験するのが得策です。特に文学部は入試の難易度が大きく変わらないのでオススメです。一方、法学部は倍率が高いので、難易度が高くなっています。どちらを併願するにしても、進学後の学習内容は大きく異なるため、熟慮しましょう。
他の私立大学との併願は、共通テスト併用のない明治大学・法政大学が楽です。ただ、共通テストの勉強に時間をかけることができるなら、立教大学や青山学院大学もいいでしょう。なお、MARCHや日東駒専などレベルを下げた併願校では、「古文」の勉強がさらに必要になってきますので、おろそかにしないでおきましょう。
ちなみに、慶應と同じ難易度の早稲田は、傾向が大きく違うため併願には向いていません。慶應経済では英作文が多く出題されますが、早稲田の政治経済学部とは傾向が異なります。早稲田政経は自由英作文のみの出題に対し、慶應は自由英作文よりも和文英訳が多く出題されます。仮に早稲田での併願をするなら商学部でしょう。早稲田商学部の英語は長文メインで英作文がほぼ不要なので、余分な対策をする必要がありません。漢文の対策は多少必要となりますが、配点は低いため併願の選択肢としては入れてもよいでしょう。
国公立の記述問題と慶應の小論文は比較的相性がよく、数学が得意であれば枠の広い数学受験でアドバンテージが取れるため、併願を考えても良いでしょう。
慶應義塾大学の受験相談事例集
Part.3 科目別の勉強法と攻略法
ここからは過去問の傾向や具体的な攻略法を分析していきます。各科目のポイントだけでなく、オススメの参考書と対策時期を紹介します。受験に必要な情報を有効に活用していってください。
外国語(英語)
大問5つ構成で、長文問題が3題と英作文が2題(和文英訳・自由英作文)出題されます。長文は設問も英語で書かれていたり発音問題があったりと幅広い問題が出題されるため、難易度が高いです。長文の文章量も多いため、時間配分をマネジメントしておかないと解ききれなくなってしまいます。速読力が必須なのはもちろん、過去問をやりこみ、出題傾向を把握したうえで、解く順番まで想定しておくことが必要です。第4問・第5問の英作文は、そこまで難易度が高くないため、20〜30点程度は確実に得点しておきたいところです。
小論文の対策時期を考えると、高2のうちに英語の基礎は固めておかなければならないので、早めに対策していきましょう。
本番で8割程度を目指しましょう。

慶應義塾大学経済学部 外国語(英語)の対策
小論文
基本的な形式は、内容理解を問うものが1問(200字程度)、意見を聞かれるものが1問(400字程度)となっています。経済学を主軸に、社会学や政治学、行動経済学など幅広いジャンルと絡めて出題される傾向にあります。
専門性の高い文章を要約する練習は不可欠なので、経済学部の過去問に限らず文学部・法学部の過去問を熟読しましょう。
「筆者の主張を正確に読み取って要約する」問題では現代文の対策が役に立ちます。「自分の意見を述べる」設問では、年度によって「本文の意見を踏まえるべき」なのか「本文の意見にとらわれずに」なのか指定があるので、注意しましょう。意見の一貫性を保って文章を書く能力が重要になってくるので、過去問などを解く際には必ず添削してもらいましょう。
小論文の難易度を考慮すると、高3の夏前(7月頃)からは練習をしておくべきです。文章を書くことが苦手な人は5〜6月には始めておきましょう。

【準備中】慶應義塾大学経済学部 小論文の対策
数学
数学が必要になるのはA方式です。経済学部の数学は6問構成、そのうち3問はセンター試験のような空所補充形式です。前半の空所補充問題は一次選考の対象になりやすいため、確実に点を取り、7割以上を取れるようにしておかなければならないと推測できます。後半3問は記述問題ですが、手が出ないような問題は1問程度、それ以外は途中までは必ず解けるような基本的な問題が例年出題されています。大問数が多く時間との戦いになるので、時間がないときは捨てるべき1問をきちんと見極めて、取れる問題にいかに時間をかけられるかが重要です。
空所補充問題で「2完(2問完答)+部分得点」または「3完」、記述問題で「1完+部分得点」を目標にすると良いでしょう。高1・高2から長期休みごとに復習をしていき、高3の夏休みには青チャートのレベル4程度は解けるように高2のうちに1A2Bの青チャートのレベル3を完璧しておくべきでしょう。

慶應義塾大学経済学部 数学の対策
世界史・日本史
B方式の世界史・日本史は、高2の冬〜高3の春頃には学校のペースより少し早めに「スタディサプリ」などで通史の理解を進めて、高3の夏前には一通り全範囲を終えておきましょう。難しい単語も出題されますが、基本単語が押さえられれば8割は取れる見込みです。高3の夏までは通史の流れを優先して押さえ、秋ごろから一問一答で細かい単語も含め完璧にしましょう。

慶應義塾大学経済学部 世界史の対策

慶應義塾大学経済学部 日本史の対策