- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、共通テストの問題変更が予定されています。2024年度共通テスト終了後記事も順次更新しますが、しばらくは古い情報も含まれますのでご注意ください。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。
共通テスト地理の勉強はできてますか?
- 共通テスト本番まで1ヶ月しかないけど、地理の対策何もしてない…
- 共通テスト模試で50点以下だった…
という人もいるのではないでしょうか?
しかし、安心してください!地理は世界史や日本史と比べると、短期間で成績を伸ばしやすい科目のため、今から勉強しても十分間に合います。
この記事では、共通テスト地理を1ヶ月で8割超えする方法を解説します。
*この記事は、過去の共通テスト・第1、2回試行調査・市販の予想問題集の内容を元に作成されています。
共通テスト地理の概要を知ろう!
短時間で共通テスト地理の点数を上げるには、共通テスト地理について理解し特化した対策をするのが重要です。
まずは共通テスト地理の概要を知りましょう。
共通テスト地理の試験時間と時間配分
共通テスト地理の試験時間は「60」分で、問題量のわりには多めの時間設定です。
共通テスト地理では地図やグラフなどの資料が大量に出題されますが、時間はたっぷりあるので、あせらずに資料と選択肢を見てから解答を選びましょう。
共通テスト地理の設問構成と出題範囲
共通テスト地理の設問構成と出題範囲は、基本的には毎年以下の内容で固定されています。
地理A
| 設問 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 1 | 地図の読み取りと活用 | 20 |
| 2 | 世界の生活・文化 | 20 |
| 3 | 東アジアの地誌 | 20 |
| 4 | 地球全体の課題 | 20 |
| 5 | 苫小牧市および周辺の地域調査 | 20 |
地理B
| 設問 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 1 | 世界の自然環境および自然災害 | 20 |
| 2 | 資源と産業 | 20 |
| 3 | 村落・都市と人口 | 20 |
| 4 | ラテンアメリカの地誌 | 20 |
| 5 | 苫小牧市および周辺の地域調査 | 20 |
共通テスト地理は、A・Bともに「大問ごと20点×5問」という構成です。配点は1問3~4点。
共通テスト地理の詳しい設問分析と出題範囲はこちらをチェック!

短期間で共通テスト地理を8割にする勉強法
共通テスト地理の勉強の流れは以下の通りです。
- 系統地理を勉強する
- 地誌を勉強する
- 時間の許す限り問題練習を行う
系統地理は「産業」「気候」など、特定のテーマに沿って学習する地理のこと。
地誌は「アフリカ」「日本」など、特定の地域について勉強する地理のことです。
系統地理から勉強を始める理由
共通テスト地理の勉強は、系統地理から始めます。
なぜなら「系統地理」で覚えた知識があれば、「地誌」の問題はそれほど暗記しなくても解けるからです。
例えば、地誌で「アイスランドの発電の種類の内訳」という問題が出された場合を考えましょう。
そもそも系統地理では、「アイスランド周辺はホットスポットで火山が多い」ということを学習します。
そのため、アイスランドでは「地熱発電量がほかの国より圧倒的に多いはず」と推測できますよね。
細かい数値までは聞かれないため、地熱発電の割合が高いことさえわかれば問題が解けるのです。
このように、系統地理で得た知識を地域別に当てはめるだけで、地誌の問題は解けます。
そのため、まずは系統地理から勉強しましょう。
系統地理の勉強では「事象の因果関係をしっかりと理解すること」を意識することが重要です。
例えば、農業テーマで勉強すると「東アジアは稲作が盛んだ」という事柄が出てきます。
出てきた際に「なぜ東アジアは稲作が盛んなのか?」まで考えましょう。
考えると「東アジアはモンスーン気候なので、高い気温と豊富な雨が必要な稲作の栽培に適している」ということが分かります。
このように事象の原因まで理解することで、ただの丸暗記よりも楽に覚えられます。
系統地理について詳しく知りたい方はこの記事をチェック!
系統地理の次は地誌を勉強する
系統地理の勉強がひと通り終わったら、地誌の勉強をしましょう。
農作物の生産量や工業データを丸暗記するのは大変なので、必ず系統地理で得た知識を使ってデータを「推測」することが重要です。
地誌について詳しく知りたい方はこの記事をチェク!
系統地理と地誌の勉強には『共通テスト地理B集中講義』がオススメです。
センター過去問の出題傾向の分析にもとづき、テーマと学習項目をランク付けしています。
厳選された系統地理と地誌の内容がコンパクトにまとまっているため、しっかり取り組めば短期間で高得点を狙える1冊です。
参考書は「記述を読む+付属の問題を解く」という流れで使いましょう。
参考書を読んでいて「詳しいデータ」「実際の写真や地図」を見たくなったら、教科書・資料集・地図帳を使って確認します。以下の『データブック オブ・ザ・ワールド2023』『新詳高等地図』などがオススメです。

その他の共通テスト地理のおすすめ問題集はこちらをチェック!
時間の許す限り問題演習をしよう
共通テストでは「データから答えを推測する力」が必要ですが、参考書を読むだけでは十分にこの力を身につけられません。
参考書を1周したら共通テスト形式の問題を解いて、「データから答えを推測する作業」に慣れていきましょう。
センターと共通テストで地理の問題はほとんど変わらないため、使う参考書はセンター過去問・共通テスト予想問題集のどちらでも構いません。
共通テスト地理とセンター地理の違いについて詳しく知りたい人はこの記事をチェック!
予想問題集は『共通テスト実戦模試(13)地理B』、共通テスト・センター過去問は『赤本』がオススメです!
5年分ほど解いてそれぞれ満点を取れる状態までしっかり復習すれば、8割程度の問題は解けるようになります。
「8割が取れなかった」「安定して8割を取れるようになりたい」という場合は、時間の許す限り問題演習を続けましょう。
問題演習をする際は「答えの出し方を学ぶこと」が重要です。
解説には答えの導き方が詳しく書かれているので、「答えを間違えた問題」「解答に自信がなかった問題」は必ず解説を読み、解けなかった原因が以下どちらのパターンなのかを分析しましょう。
- 単なる知識不足
- 知識はあったが答えに結びつけられなかった
「単なる知識不足」なら、参考書や教科書を使って、間違えた問題で出題されていた範囲を読み直し、足りない知識を確認しましょう。
「知識はあったが答えに結びつけられなかった」なら、解説に書かれている考え方を理解して、類似問題に対処できるようにしましょう。

まとめ
共通テスト地理は暗記する量が少ないので、日本史・世界史といった科目と比べて、短期間勉強しただけでも高得点を狙いやすい科目です。
今まで地理の勉強を全然してなかったという人でも、直前に対策するだけで良い点が取れるようになるので、この記事を参考に「系統地理→地誌→問題演習」の順番で勉強しましょう!
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば地理の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
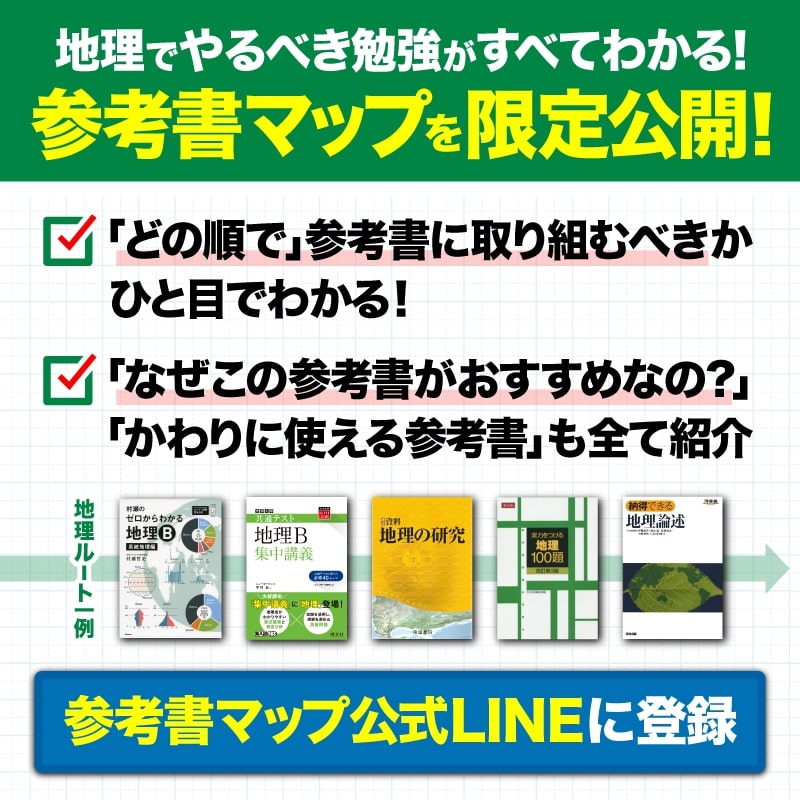
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト地理の解き方のコツはこの記事をチェック!
















