『青チャート』は、MARCH理系~国公立大学が志望校の人にオススメの参考書です。多くの受験生が使用する有名な参考書で、基礎から応用まで網羅されています。
『青チャート』を2冊(理系なら3冊)やり切れば、数学に必要な定石を理解できるでしょう。
今回の記事では『青チャート』の具体的な使い方やオススメな人、使う際の注意点などについて解説します!
『青チャート』はどんな参考書?
それではまず『青チャート』がどんな参考書なのかを簡単に確認しましょう。
- 料金
- ¥2,255
- ページ数
- 671ページ
- レベル
- 関関同立理系、MARCH理系、国公立理系2次試験
- 料金
- ¥2,431
- ページ数
- 664ページ
- レベル
- 関関同立理系、MARCH理系、国公立理系2次試験
- 料金
- ¥2,541
- ページ数
- 736ページ
- レベル
- 関関同立理系、MARCH理系、国公立理系2次試験
『青チャート』は、網羅的に数学の定石を理解できる参考書です。分からない問題を辞書的に調べることもできます。
「共通テストで9割以上とりたい」「国公立大学2次試験で数学が出題される」という人は『青チャート』を使いましょう。
『青チャート』のメリット・デメリット
メリット
- 全ての例題にレベル別に5段階のコンパスマークがついている
- 基礎から応用まで網羅的に掲載している
- 解説動画がついているため分かりやすい
- 本体の解説文が丁寧
デメリット
- 問題数が多く挫折しやすい
- 必要なレベルに応じて問題を選ぶ必要がある
『青チャート』は受験に必要な問題を網羅しているため、さまざまなレベルの人が取り組める参考書です。レベル別に5段階のコンパスマークがついており、志望校に必要な問題を正しく選べます。
基礎から応用まで学習できる『青チャート』を使えば、MARCH理系~国公立大学2次試験の基礎をしっかり固められるでしょう。
ただし、問題数が多く挫折しやすいため、粘り強く取り組む必要があります。途中で挫折せずに取り組み終えるには、自分に合ったレベルの問題を選択することが大切です。
『青チャート』がオススメな人
『青チャート』は以下のような人にオススメです。
- 共通テストで9割以上取りたい人
- MARCH以上の大学を狙っていて数学が出題される人
- 理系国公立大学が志望校の人
- 網羅的に数学の定石を知りたい人
『青チャート』は、基礎から応用まで網羅的に定石を理解したい人にオススメの参考書です。
チャートシリーズは易しい順に『白チャート』『黄チャート』『青チャート』『赤チャート』に分かれています。志望校のレベルに応じて選びましょう。
選び方を知りたい人は、こちらも参考にしてください。
『青チャート』の解説が全く理解できない場合は、まず教科書レベルの勉強をするのがおすすめです。こちらで勉強方法を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

『青チャート』の使い方
ここからは具体的な『青チャート』の使い方をチェックしていきましょう!どんなによい参考書でも正しい手順で使えなければ、効率的に勉強できません。
『青チャート』は基本的に以下のステップで活用しましょう。
- Step1.
- 時間を計りながら解く
- Step2.
- 解説をすみずみまで読む
- Step3.
- 理解できない解説は印をつけて飛ばす
- Step4.
- 間違えた問題は解説を読んだ直後に解きなおす
- Step5.
- 正解できるまで間違えた問題に取り組む
Step1.時間を計りながら解く
問題を解く際は時間を計りながら行い、3分程度手が止まったら解説を読みましょう。分からない問題に時間をかけすぎないのがポイントです。
Step2.解説をすみずみまで読む
解説には、問題を解くための方針が詳しく掲載されています。単純に公式や答えを覚えるのではなく、「なぜその解き方なのか」に着目して解法パターンを暗記しましょう。解説動画もあるので、読むだけで理解しにくい問題は動画も視聴するのがオススメです。
また、間違えた問題は、復習の際に分かりやすくするために印を付けましょう。
Step3.理解できない解説は印をつけて飛ばす
解説のなかで理解できない部分があった場合は、とりあえず「理解できなかった」と分かるように印だけ付けて先に進みましょう。分からなかった部分以降の解説を読めば理解できることもありますし、2周目以降で気づく可能性もあります。ひとまず、飛ばしてでも先に進むことが重要です。
ただし、質問できる相手がいるのであれば、すぐに疑問を解消するのがオススメです。
Step4.間違えた問題は解説を読んだ直後に解きなおす
解説を読んで解き方を理解できたら、その場で解説を閉じて解きなおしましょう。「分かったつもり」になっていないか確認できます。
もし解けないようであれば、解説を理解できていないということです。その場合は、もう一度読み直してから解きなおしましょう。
Step5.正解できるまで間違えた問題に取り組む
2周目以降は印を付けた場所「のみ」をもう1度解きなおしましょう。解説を読んで理解した部分は解けるはずです。
くり返し間違えた問題のみを解きなおして、最終的に必要なレベルの問題を自力で全て解けるようになったら『青チャート』は卒業です。
数学の定石を理解する勉強法はこちらの記事で詳しく解説しています!数学の勉強に悩んでいる人は、参考にしてください。
『青チャート』を使う際のペース配分
『青チャート』に取り組むペース配分は、どんな状況で使うかによって異なります。自分に合うものを選んで適切なペースで暗記していきましょう。
まだ受験まで時間がある高校1・2年生の場合は、毎日1時間を目安に取り組みましょう。もし問題が難しく感じるならば、コンパス1〜3つの例題に絞って、挫折しないよう取り組むのがオススメです。
部活動で忙しくて時間が取れないという人は、最低週に3時間以上を目安に取り組みましょう。ただし、忙しいからといって、間違えた問題の復習を怠ってはいけません。完璧になるまで、くり返し解くことが重要です。
受験まで時間がない高校3年生の場合は、志望校のレベルに合わせて問題を絞って取り組むとよいでしょう。
『青チャート』を使う際の注意点
『青チャート』を使う際は以下の点に注意しましょう。
- 1周目は自力で解ける問題が3割でもOK
- 解けない問題は必ず印をつけて復習する
- 自分のレベルに合った問題を解く
- 解説はすみずみまで読み込む
最初は問題数が多いことや問題が解けないことが原因で挫折しやすいです。そのため、自分のレベルに合わせてステップアップしていきましょう。
また、1周目は解けなくても心配する必要はありません。解説を読み込んで完璧になるまで「解きなおす」ことが重要です。解説動画も活用しつつ『青チャート』を完璧にしましょう。

まとめ
最後にもう1度『青チャート』がオススメな人を確認しましょう。
- 共通テストで9割以上取りたい人
- MARCH以上の大学を狙っていて数学が出題される人
- 理系国公立大学が志望校の人
- 網羅的に数学の定石を知りたい人
志望校が理系MARCH以上の人や理系国公立大学の人は『青チャート』に取り組みましょう。
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば数学の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
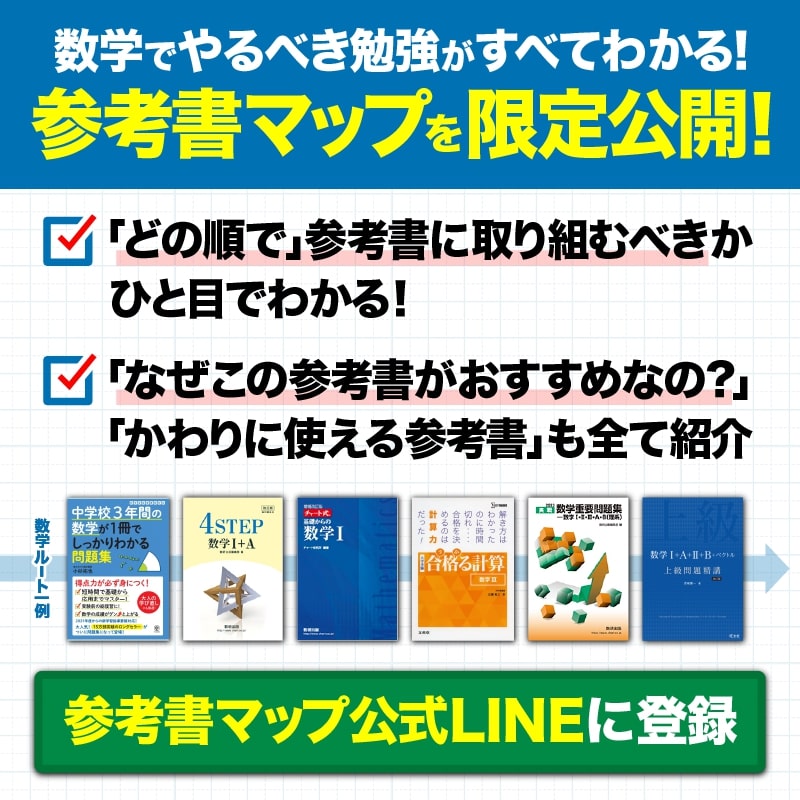
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る













