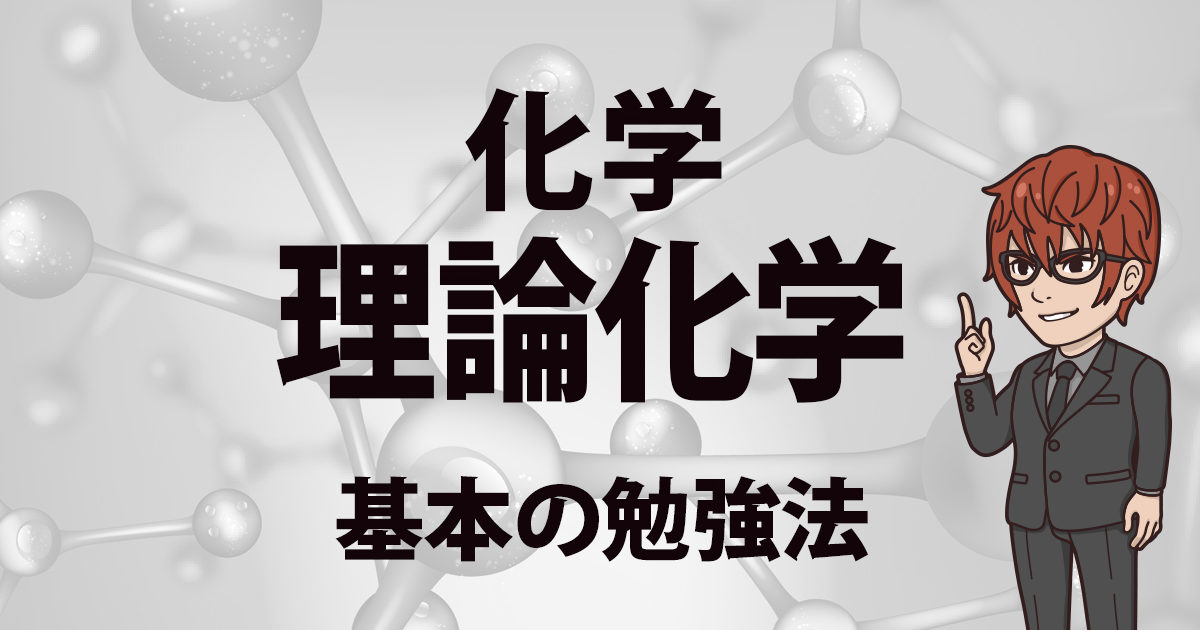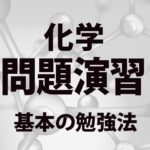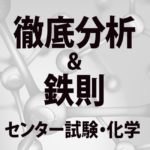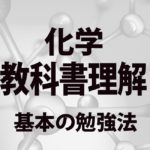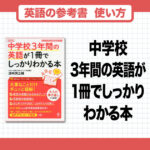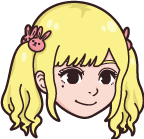

さきさきの言うように化学の理論分野は難しい単元です。「化学が苦手」と感じる人の多くは、この理論分野で挫折の経験があるのではないでしょうか。
しかし、この難しい理論分野を乗り越えられれば、残りの単元もスムーズに勉強できます!理論分野は他の単元の基礎となる部分も多いため、まずは理論分野をしっかり理解してから進めましょう。
今回の記事では、化学の理論分野が重要な理由や勉強する際の注意点などを解説していきます。
高校化学で理論分野が最重要な理由

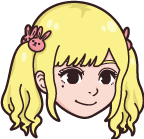

化学には「理論分野」「無機分野」「有機分野」の大きく分けて3つの分野がありますが、その中で理論分野が最も重要な理由は以下の2つです。
- 理論分野は無機や有機に関連する単元を含むから
- 入試では理論分野の配点が高いケースが多いから
理論分野は無機や有機に関連する単元を含むから
一言で理論分野といっても、たくさんの単元が含まれています。その中には、「無機や有機の問題に直接関係する基本的な単元」もあれば、「理論分野単体で完結する問題が多い発展的な単元」もあります。
特に「無機や有機の問題にも直接関係する基本的な単元」は重要です。この基本的な単元としては、具体的に以下が該当します。
- 濃度の計算
- 中和反応やその計算
- 酸化還元反応やその計算
理論分野で上記の単元を理解できていないと、無機や有機分野の勉強で躓く原因になるでしょう。
例えば、無機分野で出てくる「金属の精錬」は、酸化還元反応の知識を多く使います。「どれくらいの鉄鉱石からどれくらいの鉄が作れますか?」などの量的計算も必ず入ってきます。
また、有機分野なら「アルコールを酸化させたらアルデヒドを経由してカルボン酸になります」という反応を考える際に、酸化還元反応の知識が必要です。カルボン酸は典型的な酸なので、中和反応に出てくることもあります。その際は、濃度に注意して計算を進めなければなりません。
このように、濃度計算や中和・酸化還元反応の計算は、無機や有機分野の両方で出てくる内容です。それらの計算は、すべて理論分野の中で学習していきます。
入試では理論分野の配点が高いケースが多いから

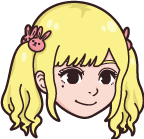
化学の入試では理論分野の配点が高いです。例えば2023年の共通テストは以下の配点となっていました。
- 第1問:理論(20点)
- 第2問:理論(20点)
- 第3問:無機(20点)
- 第4問:有機(20点)
- 第5問:理論&無機(20点)
こうして見ると、半分近くが理論分野からの出題であるとわかりますね。
なぜ理論分野からの出題範囲が多いのでしょうか?それは「理論分野は単元ごとで難易度に適度なバラつきがある」かつ「それぞれ独立した単元になっている」という分野なので、問題を作成しやすいからです。
例えば、以下のように難易度ごとで独立した大問を作れます。
- 易しい:原子や分子の電子配置など
- 中くらい:中和計算、酸化還元計算など
- 難しい:化学平衡など
一方で無機分野はどのテーマでも難易度はほとんど同じです。そのため、難しい問題を「無機の範囲だけで作成すること」は、なかなかできません。強いて言えば、無機分野は理論分野と絡ませて難易度を上げられますが、そうなると結局、理論分野の配点が高くなります。
また有機分野は簡単な問題を作成することが難しいです。暗記だけで解ける問題も作れますが、暗記だけで大問1つ分も出題すると全体のバランスが悪くなります。
上記のような理由があるため、結果として理論分野からの出題が多くなり、配点も高くなる傾向にあるのです。

高校化学の理論分野を得意にするための勉強法!
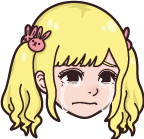

理論分野は、高校化学の基礎となる分野です。そのため、苦手な状態をいつまでも放置しておくわけにはいきません。理論分野が得意になれば模試や入試で高い得点を獲得できるため、成果に繋げられるようしっかり勉強しましょう。
具体的な勉強の流れは以下の通りです。
教科書レベルの理解→基本レベルの問題演習→発展レベルの問題演習→過去問演習
まずは教科書や学校の授業レベルの基本的な内容を理解しましょう。理解をせずに暗記だけで乗り切ろうとすると、問題集や模試などの解説を理解できなかったり、入試で出題形式が変わったりした際に対応できません。学校の授業を聞いても理解できない部分は『スタディサプリ』などの映像授業を使うのがオススメです。
教科書理解の具体的な勉強法については、以下の記事でも解説しています!
教科書の内容を理解できたら、次は『セミナー』や『リードα』など、学校で配られる問題集で基本的な問題演習に取り組みましょう。理論分野は計算も多いので、自分の手を動かして演習することが重要です。手を動かすことで、実際の入試で身に付く知識も増やせるでしょう。
基本的な問題演習まで完了すれば、MARCHや関関同立レベルの過去問なら半分以上は解けるようになるはずです。よりレベルの高い大学を目指すのであれば、『重要問題集』などの発展的な問題集にチャレンジしましょう。
問題演習の具体的な勉強法については、以下の記事でも解説しています!
問題演習まで終わったら、残りは過去問演習です。ただし、過去問演習は理論分野だけ取り組んでも意味がないので、無機と有機の勉強を進めてから取り組みましょう。
まとめ
化学の理論分野を難しく感じる人は多いです。しかし理論分野は、無機や有機でも使う単元が絡むため、基礎固めの意味で勉強しておくことが欠かせません。また、理論分野は入試の配点も高くなりやすいため、得点を上げる意味でも知識を身に付けておくことが必要です。
実際に勉強する際は、
教科書レベルの理解→基本レベルの問題演習→発展レベルの問題演習→過去問演習
という順番を守り効率よく化学の実力を身に付けていきましょう。
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば化学の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
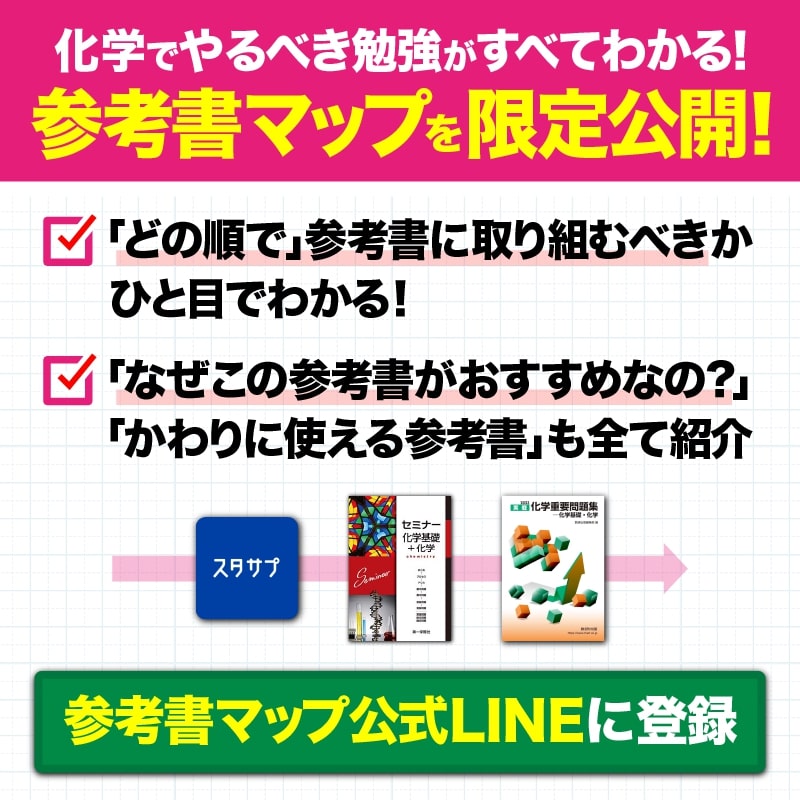
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る