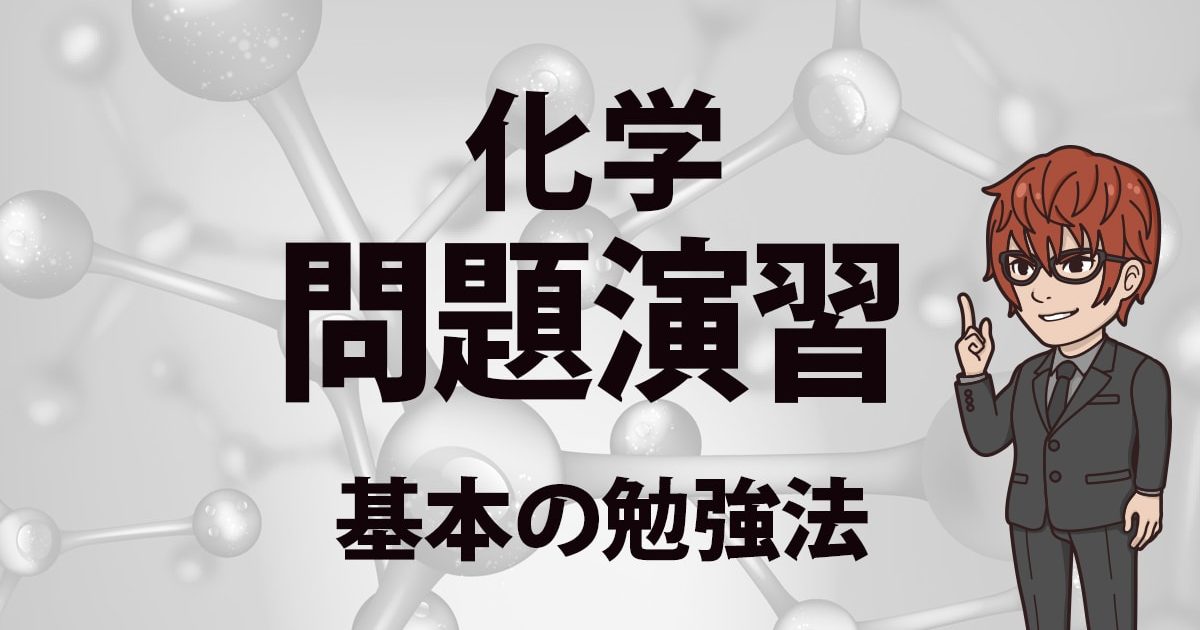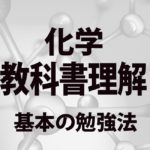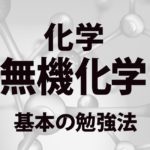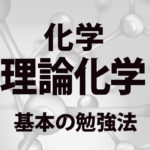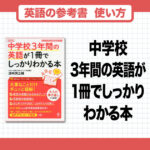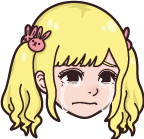

「授業を理解すれば化学の問題は解けるよね!」と考える人も多いはず。しかし実は、授業の内容を理解しただけで入試や模試、定期テストの問題が解けるわけではありません。
授業で習ったことを発揮してテストで得点するためには、問題演習によって知識を定着させることが重要です。
とはいえ、やみくもに問題演習をすれば良いわけではありません。演習のやり方を間違えると、せっかくの勉強時間が無駄になることもあります。
自分で解いた問題演習の量や時間に見合う成果を出すためにも、今回の記事で「正しい問題演習のやり方」を理解しましょう!
化学の勉強の全体像
問題演習のやり方を理解する前に、まずは大学受験で必要な化学の勉強の全体像を確認しておきましょう。
化学の勉強は以下の流れで進めることが基本です。
教科書レベルの理解→基本レベルの問題演習→発展レベルの問題演習→過去問演習
最初は必ず「教科書レベルの理解」から始めましょう。教科書に書かれている内容は、化学の勉強における基礎です。この基礎が固まっていない状態で問題演習に取り組んでも、効率よく勉強できません。
特に以下のような人は、先に基礎の「理解」をすることが重要です。
- 学校の授業がわかってない
- 定期テストで平均点以下しか取れない
教科書レベルを理解するための具体的な勉強法については以下の記事で解説しています!
今回の記事では、上記の基本理解が終わっていることを前提として「基本レベルの問題演習」「発展レベルの問題演習」のやり方にフォーカスして解説します。
「基本レベルの問題演習」とは、学校指定の易しいレベルの問題集を使った学習のことを指します。この基本レベルの問題演習まで完了できれば、MARCHや関関同立クラスの大学で合格最低点を狙える実力を身に付けられるでしょう。
「発展レベルの問題演習」とは、早慶理科大などの難関私立、旧帝大などの難関国公立大の合格に必要な勉強のことを指します。発展レベルの問題演習に取り組む場合は、入試レベルのみを掲載した問題集を活用しましょう。

化学の問題演習はどうして大切なの?
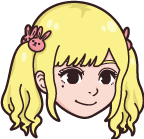

具体的に化学で問題演習が重要な理由は以下の3つです。
- 手を動かさないと入試で使える知識は身に付かないから
- 手を動かさないと計算ができるようにならないから
- 完璧に暗記できていなくても解ける問題が多いから
それぞれ確認していきましょう。
手を動かさないと入試で使える知識は身に付かないから
授業を聞いて、単純に「知識を理解する」という部分までなら達成できる人は多いでしょう。しかし「授業の内容を理解できること」と「理解した知識を使って問題を解くこと」はまったく別です。
「授業で中和も酸化還元について理解はしたけど、この反応はどっちの反応?」
「有機の基本的な性質は習ったけど、この物質の構造ってどうやって決めればいいの?」
問題演習をしていなければ、こんな風になってしまうことはよくあります。
また、用語を暗記するにしても、漠然と参考書を読むより実際に手を動かして問題を解いたほうが定着します。
なぜなら「暗記している時間」よりも「暗記した内容を思い出そうとする時間」を長く取ったほうが知識が頭に残るためです。実際に問題を解くことで「これはどういう意味だっけ?」と思い出す機会を増やせます。
手を動かさないと計算ができるようにならないから
暗記などの知識だけでなく、「計算」も実際に手を動かさなければ上達することはありません。問題文の意味(実験の内容)が理解できても、どう計算を進めるかで手が止まるようでは、答えにたどり着くことはできませんよね。

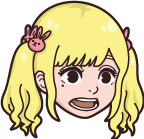
仮に計算できても「細かい計算に時間をかけすぎている」という状態では、入試の試験時間内に全ての問題に手を付けられない可能性が高くなります。
特に共通テスト化学はサクサク計算を進めないと間に合わない人も多い試験です。また「個別試験で理科が2科目必要」という大学の多くでは、計算を一瞬で終わらせるくらいのスピード感で進めないと、最後まで問題を解けないくらいの出題量になっています。
計算を早く正確にできるようになれば、入試や模試で難しい問題に直面したとき「どうやれば解けるのか?」を考える時間を確保できます。
難しい問題をじっくり解く時間を確保するためにも、普段から問題演習でしっかり手を動かし、自力で計算できるようにしましょう。
完璧に暗記できていなくても解ける問題が多いから
化学では用語などの暗記が重要です。実際の問題を解きながら、必要な用語を丁寧に暗記することで入試本番でも問題を解けるようになります。
だからといって「暗記を完璧に暗記しなきゃ!」と思う必要はありません。
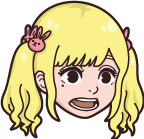
実は化学の問題には、完璧に用語などを暗記していなくても解ける問題が多くあります。例えば、消去法で答えを導けたり、次の小問から逆算して記憶を辿れたりすることも珍しくありません。
また問題演習を繰り返すことで、入試で「頻出」の内容を多く勉強できます。一問一答や教科書、プリントを見て暗記するだけでは、すべての内容が同じ頻度で出てくるので、入試頻出でない内容に多くの時間を割いてしまう可能性が高くなってしまうんです。
実際、化学の問題では出題されやすい物質や反応は限られています。なぜなら、難しすぎる内容を出題すると、ほとんどの人が解けず結局点数に差が出にくいためです。
完璧に暗記することを意識しすぎて、頻出ではない細かい部分まで時間を費やしてしまうと、「勉強時間の割に成績が上がらない」ということも起きてしまうのは想像できますよね。受験までの勉強時間は限られるため、そうした事態だけは避けなければなりません。
暗記単体に使う時間は最低限に抑えて、理解した単元から順番に問題演習に取り組みましょう。
入試で出題されやすい内容だけでもきっちり暗記できれば本番で80%は解けます。80%解ければ入試で十分合格ラインに到達できるでしょう。
化学の問題演習におすすめの問題集を紹介!
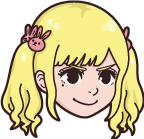

化学の基本的な問題演習:『セミナー』『リードα』『ニューグローバル』『エクセル』
基本レベルの問題演習では、『セミナー』『リードα』『ニューグローバル』など、学校で指定されている分厚い問題集を使いましょう。いずれの問題集も持っていなければ『エクセル』を使えばOKです。

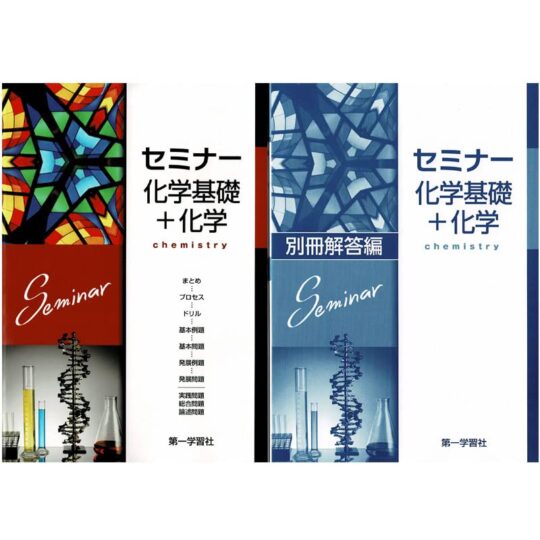
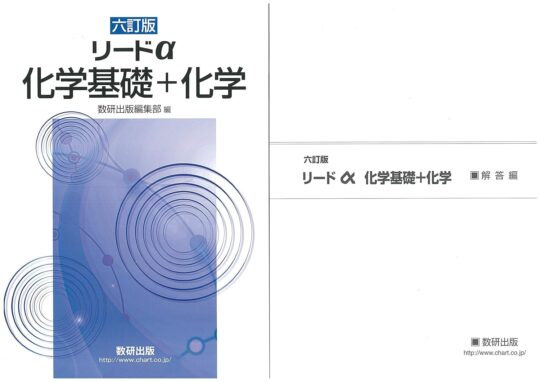

『セミナー』『リードα』『ニューグローバル』『エクセル』の具体的な使い方については、以下の記事でも解説しています!
『セミナー』の発展問題まで全て解けるようになれば、GMARCHや関関同立、共通テストレベルの問題は解けるようになります。
化学の発展的な問題演習:『重要問題集』『化学の新演習』
『重要問題集』も学校で配られることが多いですが、配布されなくても自分で購入できます。『重要問題集』まで解ければ、早慶理科大や旧帝大だけでなく、東大や京大など最難関大の問題も半分くらいは解けるようになるでしょう。
具体的な使い方などについては以下の記事で解説しています!
東大や京大、東工大などの最難関大を志望する人は『化学の新演習』まで取り組むことが理想です。
具体的な使い方などについては以下の記事で解説しています!
具体的な問題集の使い方

- ステップ1
- 時間を計りながら問題を解く
- ステップ2
- 解説を丁寧に読む
- ステップ3
- 間違えた問題は解説を閉じて解きなおす
- ステップ4
- 資料集の該当範囲に目を通す
- ステップ5
- 間違えた問題に印をつける
- ステップ6
- 2周目以降は間違えた問題だけ取り組む
問題演習の際は必ず時間を計りましょう。入試本番を意識するという意味もありますが、そもそも「時間をかけても解けない問題」はいくら粘っても解けません。
特に用語を答えるだけのような簡単な問題こそ、暗記できていなければどれだけ時間をかけても解答できませんよね。サッサと飛ばして先に進み、2周目以降にできるようになれば大丈夫です!
それぞれの問題集で、以下くらいの時間を意識して解きましょう。
- 『セミナー』の基本問題:数分/問
- 『セミナー』の発展問題:10分/問
- 『重要問題集』『化学の新演習』:15分/問
問題を解いたら解説を丁寧に読み込みましょう。とくに1周目は、間違えた問題を読み飛ばさず入念に読み込みます。また、欄外にコラムとしてまとめられている部分も読み飛ばしてはいけません。
間違えた問題は解説を閉じて解き直しましょう。特に計算はきちんと解き直さないと、自力で素早く正確に解けるようにはなりません。
また、記述問題が出題される大学の場合は、記述まで意識して必要な内容を答えられるように意識しましょう。「20字で答えなさい」といった問題は、模範解答をすぐに思い出して解答できるレベルまで練習しておきます。
解き直したら、該当範囲の資料集もチェックしましょう。1単元につき5~10分でOKです。とくに色や実験器具、日常とのつながりなど、問題集だけでは見えない部分を資料集でインプットしておくと、知識として身に付きます。
資料集のチェックまで終わったら、間違えた問題に印をつけて、間違えた問題だけ周回しましょう。勉強スピードを上げるために、正解した問題は解かなくてOKです。

化学の問題演習に取り組む際の注意点
実際に問題演習に取り組む際は、以下の点に注意しましょう。
- わからない問題は調べ、必要に応じて飛ばす
- 挫折せずに何周も取り組めるよう工夫する
- 過去問に取り掛かる時期を意識する
わからない問題は調べ、必要に応じて飛ばす
問題演習に取り組む中で、解説を読んでもわからない問題もあるはずです。そのような問題はあまり悩みすぎず、資料集や教科書で調べたりググったりしましょう。調べればすぐ解決する問題なのに、自分の頭だけで解決しようとして時間を使いすぎるのはもったいないことです。
いくら調べてもわからなければ、飛ばしてしまいましょう。もしかしたら、その日はたまたま調子が悪いだけかもしれませんし、2周目に「知識が増えて解けた」ということもあり得ます。気軽に飛ばして、とにかく次の問題に取り組みましょう。
ただし、問題を飛ばした場合は、付箋をはったり印をつけたりしておき、あとから振り返れるようにしておきます。
挫折せずに何周も取り組めるよう工夫する
『セミナー』など学校配布系の問題集には500題以上収録されているため、最初から全部取り組むと途中で挫折することがあります。
挫折を防ぐには、いきなり全部解くのではなく、
- 1周目:基本問題を解く
- 2周目:1周目で間違えた問題&発展問題を解く
- 3周目:2周目で間違えた問題&総合問題を解く
というように、周回ごとにレベルを上げてチャレンジしましょう。
他の問題集に取り組むときも同様です。こうした工夫をしながら解いて、途中で挫折しないようにしましょう。問題演習では最後までやり切ることが重要です。
過去問に取り掛かる時期を意識する
『重要問題集』『化学の新演習』などの難易度が高い問題集に取り組む際、過去問演習の時期と被ることもあります。過去問演習の時期と被ったら、問題演習ではなく「過去問演習」を優先しましょう。
高3の11月からは、共通テストの演習や併願大学の過去問演習が始まります。そのため、遅くても「高3の10月まで」には問題演習を終わらせましょう。
化学の問題演習が終わったら何をすべき?
受験に必要なレベルの問題演習を解き終えたら、過去問演習で総仕上げを行いましょう。
化学は学校の授業ペースが遅く「全範囲を終えるのが受験直前」ということも珍しくありません。学校の授業ペースに合わせすぎて過去問演習の時期が遅れる現役生も多いですが、そうならないよう早めに問題集を終えましょう。
まとめ
化学の問題演習が重要な理由は以下の3つです。
- 手を動かさないと入試で使える知識は身に付かないから
- 手を動かさないと計算ができるようにならないから
- 完璧に暗記できていなくても解ける問題が多いから
化学は、学校の授業内容だけを理解しても、実際に手を動かして問題演習を繰り返さなければ解けるようになりません。以下のように自分のレベルに合わせた問題集を活用しながら、何度も演習を繰り返しましょう。
- 基本レベルの問題演習:『セミナー』
- 発展レベルの問題演習:『重要問題集』
- 最難関レベル:『化学の新演習』
過去問演習の時期に被らないよう、遅くても「高3の10月まで」には問題演習を終わらせることが理想です。
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば化学の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
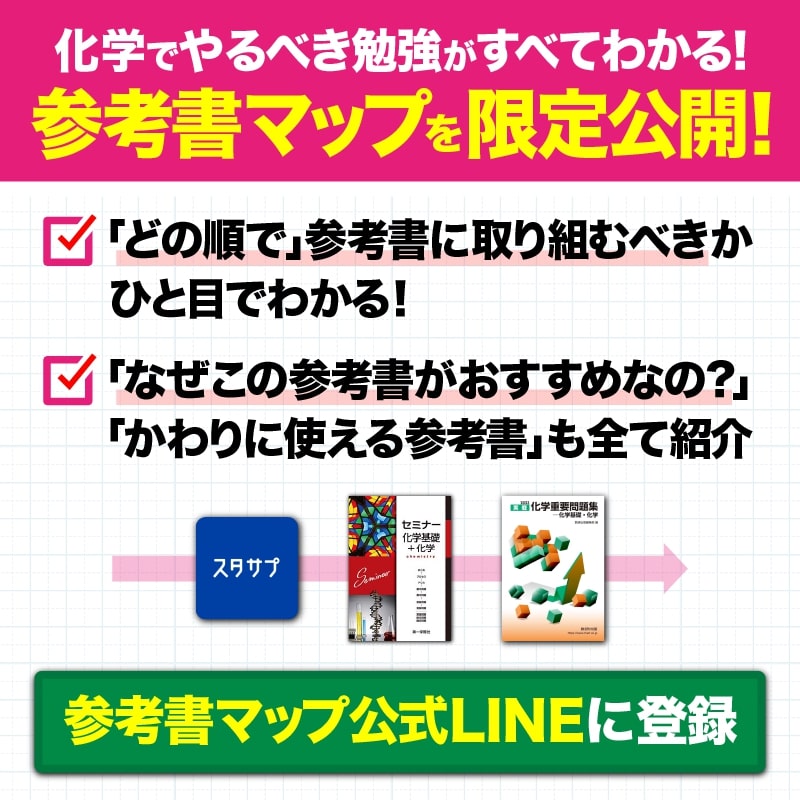
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る