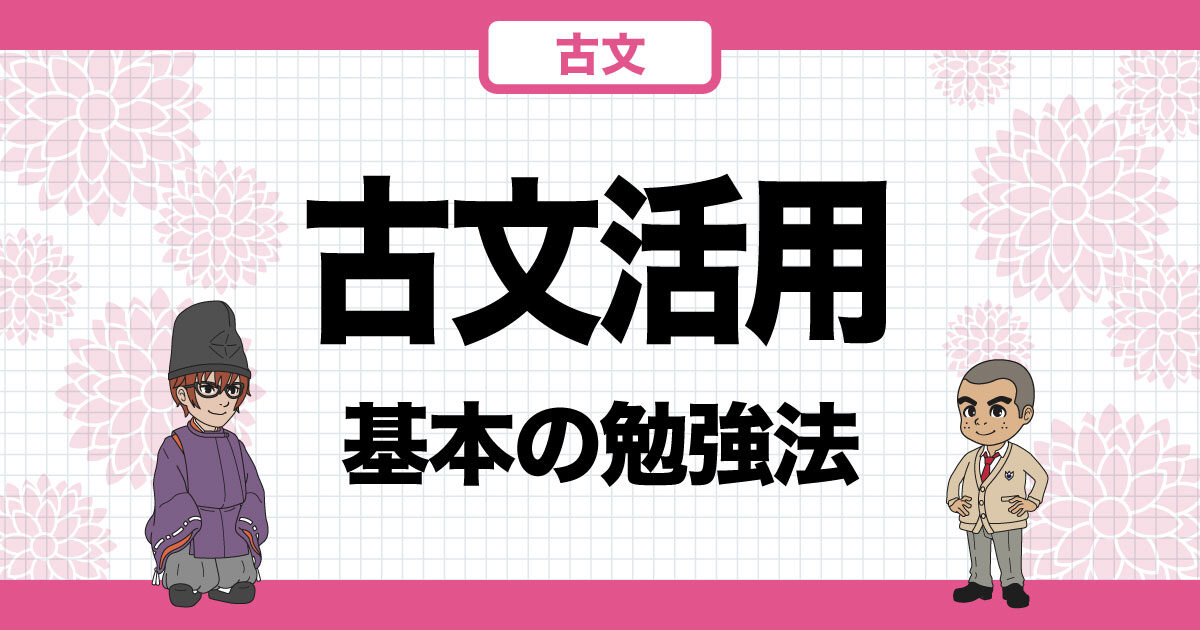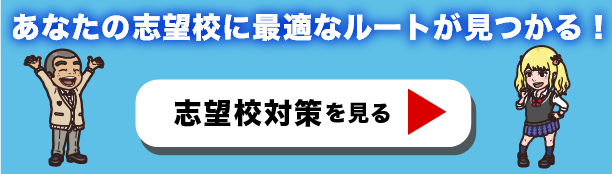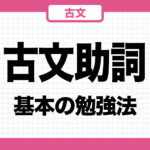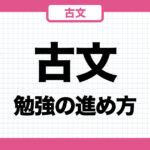古典の「活用」と聞いてピンと来ますか?「こんなの重要なの?」なんて思っている人も多いのではないでしょうか?意外と意識せずに忘れがちな人が多い分野でもあります。しかし侮ることなかれ。活用がわからないと古文を正確に読むことができないので、だんだん苦手になってしまいがちです。そこで今回は「活用を全く勉強していない人」でも「1週間で暗記できる」勉強法をご紹介します。

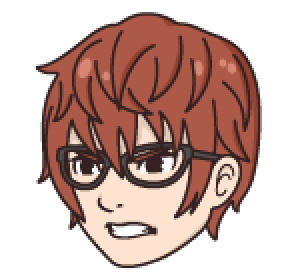


そもそも古文の「活用」って何?どうして覚えないといけないの?

勉強法を解説する前にマルオ君も感じていた疑問に答えていきましょう。
古文の「活用」って何?
そもそも「活用」とは何を指すものでしょうか?
日本語を使うときに、みなさんは単語の語尾などを変えて使いますよね。
例えば「歩く」ということばだと
- 歩くことは健康に良い
- 公園へと歩いた
- 暑いので歩きたくない
- けっこう歩かないといけない
というように、後ろに来る言葉によって形が変わりますよね。
日本語の中には、動詞や形容詞など、後ろに来る言葉によって形が変わる単語の種類がいくつかあります。
この「単語の一部が変わること」を「活用する」と呼ぶと覚えておきましょう。
この理屈は古文でも同じ。
古文も時代は違えど日本語ですから、現代語と同じように
- 歩くこと
- 歩きにけり
- やしろへと歩かん
といったふうに「活用」します。
「上一段活用」「サ行変格活用」など聞いたことがあるかもしれませんが、これは活用の種類ごとに名前をつけたもの。
この「形が変わる」ときのルールや法則を覚えていくのが「活用を覚える」ということです。
古文で「活用する」品詞は次の4つ。
- 動詞
- 形容詞
- 形容動詞
- 助動詞
この4種類の品詞は、すべて活用形を覚えなければいけません。

古文の活用は意味を正確に取る上で必須

と思う人もいるかもしれませんが、活用はすべての種類を覚えておかなければいけません。
私たちは幼い頃から現代の話し言葉で喋っているので、こうした活用のルールは勝手に身についています。そのため、活用なんてわざわざ学ばなくても自然とできてしまうものなのです。

現代語では自然とできてしまうので「活用なんかわざわざ覚えたくない」と思う人も多いかもしれませんが、古典になると覚えないわけにはいきません。
例えば、
「桜の木があった」
は古文で書くと
「桜の木ありき」
ですが、
「桜の木があった頃」
は
「桜の木ありし頃」
となります。
「き」と「し」はともに過去を意味し、「き」は文末の場合(終止形)、「し」は後ろに名詞が来る場合(連体形)に使います。
このように現代語とは違う形になってしまうので、現代語と同じ感覚で解くと当然間違えてしまうことになります。
この現代語とは違う形の活用が見極められないと、言葉の意味が正確に分からず正しい訳ができないですよね。
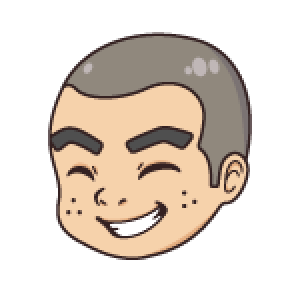
似ているようで違うものが古文では非常に多いので、活用は必ず改めて覚え直してください。
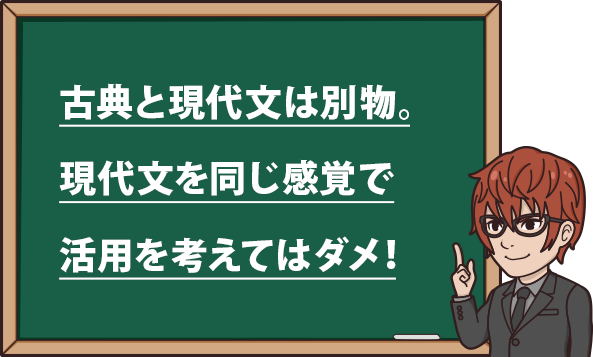

頭に残る活用の覚え方3選

古文の活用を覚える重要性がわかったところで、ここからは、古典活用を暗記する上でおすすめの覚え方を紹介します。活用を覚える上では、以下の3つのコツを駆使してみてください。
- 種類ごとに分別して覚える
- 替え歌で覚える
- 繰り返し音読する

種類ごとに分別して覚える
「種類ごとに分別して覚える」とはどういう意味でしょうか?
ここでは、活用を様々なパターンに分けて、整理して覚える覚え方のことを指します。
例えば動詞や形容詞、形容動詞の活用であれば、
- 属する語を覚えるべきもの
- 法則で理解して覚えるもの
に分別して覚えることになります。
1つ目の「属する語を覚える」ものについては、下の6個があてはまります。
- 上一段活用
- 下一段活用
- カ行変格活用
- サ行変格活用
- ナ行変格活用
- ラ行変格活用
これら6個の活用形に共通していることがあります。それは当てはまる語が少ないことです。
例えば、下一段活用は「蹴る」の一単語のみです。「蹴る」以外で下一段活用を使うことはないので、活用は「け・け・ける・ける・けれ・けよ」で覚えればOKです。
他にも、ナ行変格活用なら「死ぬ」「往ぬ」の2単語のみです。
- 上一段活用
- 干る・射る・鋳る・着る・煮る・似る・見る・試みる・居る・率る・用ゐる(ひいきにみいる)
- 下一段活用
- 蹴る
- カ行変格活用
- 来・まうで来
- サ行変格活用
- す・〜す
- ナ行変格活用
- 去ぬ(往ぬ)・死ぬ
- ラ行変格活用
- あり、をり、はべり、いますかり
これらの「活用形と、それぞれの活用に属する動詞を覚えておけばOK」というものは、必ず属する語とセットで覚えるようにしましょう。
2つ目の「法則で理解して覚えるもの」は、それ以外の活用形。
- 四段活用
- 上二段活用
- 下二段活用
- 形容詞の活用
- 形容動詞の活用
これら5個は当てはまる単語が多いため、活用形と見分けるための法則を覚えておきましょう。
例えば四段活用で解説していきます。
四段活用では活用語尾が「a・i・u・u・e・e」と「aiue」音で変化します。
「書く」だと「書か・書き・書く・書く・書け・書け」と変化するようになります。
つまりアルファベットで書かれた部分にその単語の活用語尾の音が入るということです。「書く」なら「カ行」、「思ふ」なら「ハ行」というふうに入ります。
(1)も(2)も両方混ぜて覚えようとすると頭の中が整理できず、実践できなくなってしまいます。
活用を覚えるときは「丸暗記してしまったほうが楽なのか」「活用の変化の仕方だけ覚えればいいのか」を区別して覚えるようにしましょう。
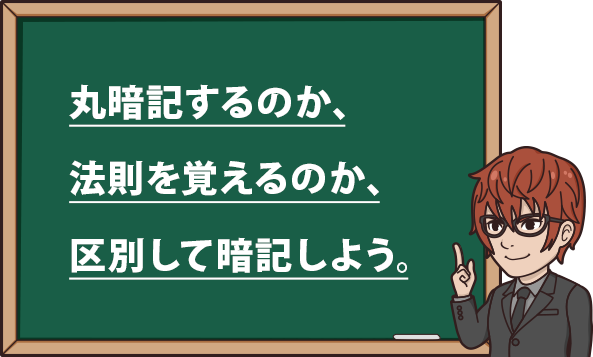
替え歌で覚える
2つ目は、動詞の活用や助動詞の種類などを、替え歌で覚えるやりかた。
助動詞の意味を覚えるために「歌」に乗せて覚える人も多いと思いますが、活用の暗記でも応用してやってみると効果的です。
試験本番だと、緊張や普段と違うなれない空気感のせいで、せっかく暗記した活用をど忘れしてしまうことがあります。
しかし歌に乗せてリズムで覚えていると、自然と頭の中に残るので思い出せることがあります。それだけ、リズムで覚えると忘れにくくなるということです。
YouTubeなどで調べるといろいろな替え歌があるため、参考にしてみるといいでしょう。
繰り返し音読する
最後に紹介するのが一番効果的な、音読を繰り返して覚えていく方法です。
活用は工夫して覚えることができますが、「活用表を何度も繰り返し音読して丸暗記してしまうこと」が一番強力です。
手順は以下の3つです。
- Step.1
- 活用表を見て5回音読する
- Step.2
- 活用表を見ないで5回音読
- Step.3
- 1週間同じ動作を繰り返す。
これを「動詞の活用」「形容詞の活用」「形容動詞の活用」「未然形接続の助動詞の活用」といったように、種類に分けて覚えていくのがおすすめ。「今週は動詞の活用」「今週は未然形接続の助動詞」といったふうに分けて覚えると、混乱せずに済みます。
各手順でのポイントとより詳細なやり方を解説しましょう。
Step.1 活用表を見て5回音読する
まず、活用表を見てなんどもブツブツ音読してください。
このときのポイントは
- 複数列がある活用も必ず「未然形→連用形→終止形→連体形→已然形→命令形」の順で唱える
- 途中の「◯」も唱える
の2つです。ただ唱えて順番を覚えても、どの活用が何形なのかが分からなければ意味がありません。「順番は覚えてるんだけど、『遊べ』って已然形だっけ?連体形だっけ?」みたいなことがないように、必ずこの2つを守りましょう。
まず、複数列がある活用、例えば形容詞の「ク活用」なら
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|
| く から |
く かり |
し | き かる |
けれ | かれ |
となっています。これを「く、く、し、き、から、かり、かる、けれ、かれ」と覚えてしまうと、どれが未然形でどれが終止形かわからなくなってしまいます。
そのため、必ず「く・から、く・かり、し、き・かる、けれ、かれ」というように、未然形は2つセットで唱えるようにしましょう。
「く・から」と「く・かり」の間に一呼吸置いて唱えるとより間違いが少なくなります。
もう1つの「◯」まで唱える、というのは、主に助動詞の暗唱で意識してほしい内容です。
例えば助動詞の「き」だと
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|
| せ | ◯ | き | し | しか | ◯ |
となっています。これを「せ、き、し、しか」と覚えてしまうと、またまたどれが未然形でどれが終止形かわからなくなってしまいます。
そのため、このときは「せ、まる、き、し、しか、まる」と、「◯」も含めて音読をしてください。

Step.2 活用表を見ないで5回音読する
見て5回正確に唱えたら、今度は表を見ないで暗唱しましょう。この時も同じく、一息で言い切りましょう。
この時5回連続で見ないで言えなかったら、それは頭の中に残っていない証拠。もう一度、活用表を見て覚えなおしましょう。
Step.3 1週間同じ動作を繰り返す
最後に【Step.1】【Step.2】を1週間欠かさずやり切りましょう。
Step.3でのポイントは、欠かさず継続することです。
活用は一つ一つ覚える量も少ない上に、活用がシンプルに並んでいるだけなので忘れやすいものです。そのため毎日かかさずやることで、自分の頭の中に残っているかどうか点検しましょう。
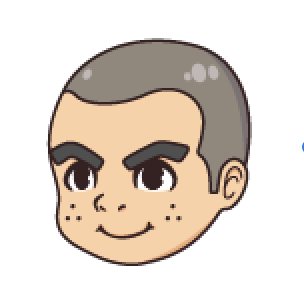
また、繰り返し音読するときには最初に「どのくらい音読するか」回数を決めておくことが大事です。5回ずつだと物足りない、なんとなく不安という人は回数を変えて自分にとって最適な音読量をこなしましょう。
古文の活用を身につけるおすすめ参考書
ここまで活用の覚え方をお伝えしてきましたが、「一覧で確認できる詳しい参考書がほしい」「問題を解いて確認したい」という人も多いかもしれません。たしかに、ただ唱えて覚えるだけよりも、その後に問題演習をしたほうが定着しやすいのでおすすめです。
古文の活用暗唱に役立つ参考書は次の2つ。
- 『古文ヤマのヤマ』
- 日栄社『古典文法サブノート』
『古文ヤマのヤマ』はどちらかというとインプット向け、『古典文法サブノート』は問題演習用の問題集です。
それぞれ簡単に特徴を説明していきましょう。
『古文ヤマのヤマ』
『古文ヤマのヤマ』は、ベストセラーになっている『漢文ヤマのヤマ』の古文編。それぞれの文法事項の解説が一通りまとまっているため、活用だけでなく助動詞の意味や覚え方、見極め方までチェックすることができます。
基本的にはどんどん読み進めながら、途中に挟まっている「演習ドリル」のページで問題を解いていくのがおすすめです。
文法事項は先程挙げたコツに従って出てくるたびに覚えていきましょう。
「学校の文法書だとわかりづらい」「授業の内容を忘れてしまったので一通り復習したい」という人におすすめの参考書です。
こちらのページでも詳しく触れています。
日栄社『古典文法サブノート』
『古典文法サブノート』は、日栄社から出されている30日完成の問題集。解説に品詞分解もついているため、復習まで取り組みやすい内容になっています。
文法事項や助動詞のかんたんな解説はもちろん、それを問題演習形式で確認することができるためおすすめです。
文法を問題演習で確認したい人にはおすすめですが、デザインの古さと解説の少なさだけ要注意です。

まとめ
今回は古文の「活用」について、なぜ活用を覚える必要があるのか、覚えるためのコツをそれぞれお伝えしました。
- 活用は正確な意味の理解に重要
- 活用がわからないと意味を見分けられないので、全て覚えよう
- 活用は「何度も唱える」ことが大前提
- 替え歌や覚えるべきことを整理するなど工夫して覚えよう
- 音読するときは活用ごとに
- 必ず「未然形→連用形→終止形→連体形→已然形→命令形」の順になるように、「◯」なども読もう
毎日何度も繰り返し唱えていれば、自然と覚えられます。
英語で言えば不規則動詞の過去形を覚えるようなもので、古文の一番基礎になる部分です。なるべく早く覚えて勉強を先に進められるようにしましょう。
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば古文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
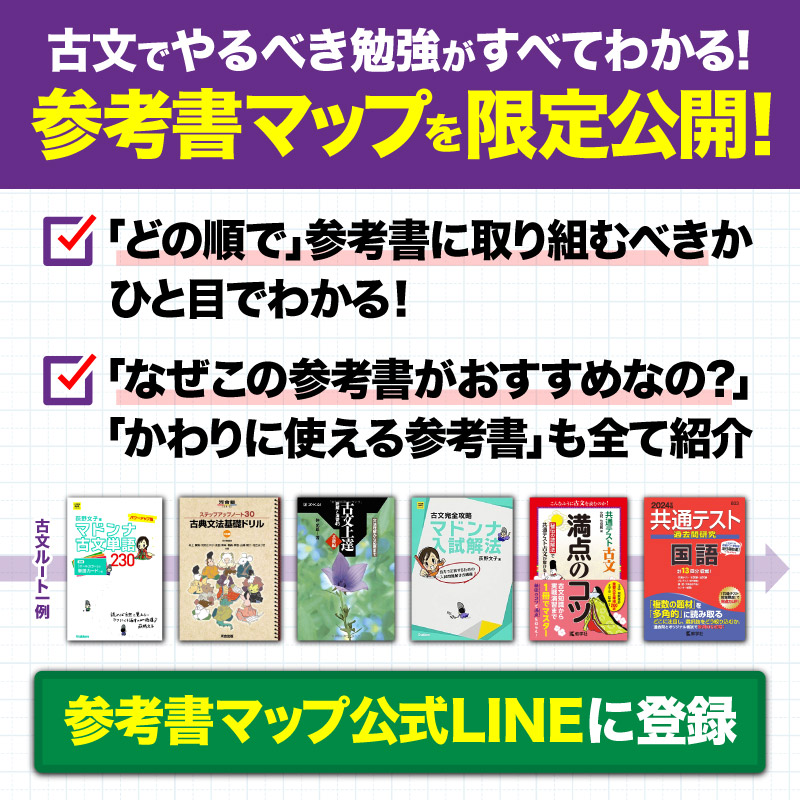
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る古文の文法全体の勉強法はこちらもチェックしてみてください。
また、活用の中でも特に助動詞は覚えるのが大変。活用以外の意味・接続も含めた重要性と覚え方はこちらからチェックしましょう。