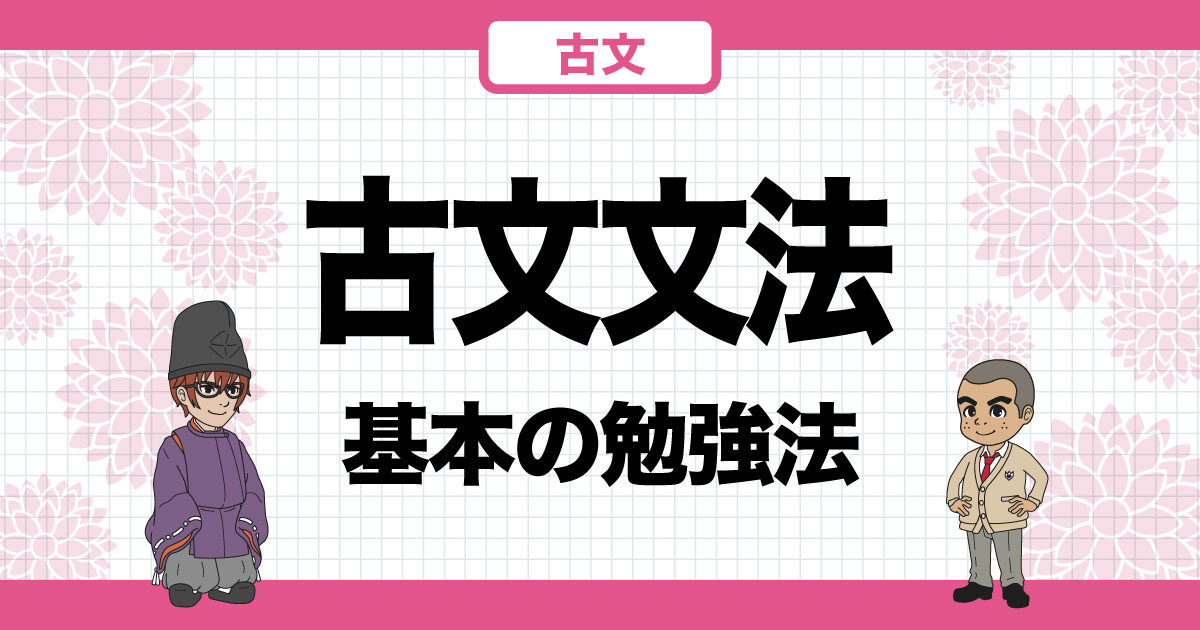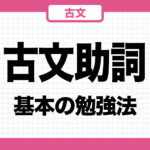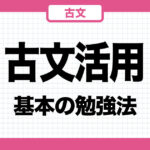古典文法といえば古典の勉強の核となる部分。古典文法ができないと、古文の入試問題はほぼ解くことができません。とはいえ、ゼロから始めるとなると、「どうやって勉強したらいいの?」と思う人も多いはず。
この記事では、そんな受験生に向け「たった1ヶ月」で古文文法を覚えられる勉強法を解説します!


なお、古文文法の勉強法については以下の動画でも解説しています!
古典文法で覚えるべきポイントは3つ!
まず「古典文法の勉強」をする上で絶対にやるべきことを知っていますか?
助動詞や敬語など難しそうな内容が多いですが、実は古文の文法事項において押さえるべきポイントはハッキリしています!
なぜなら、古典文法は英語と比べて勉強すべき内容がシンプルなためです。
それでは早速、古文文法を勉強するときに押さえるべき3つのポイントを紹介しましょう!
古典文法で覚えるべきことはこの3つ!
- 活用
- 意味
- 接続・識別
以下でひとつひとつ説明していきます。
古典文法で覚えるべきポイント①:活用

と、思う人もいるでしょう。
「活用」とは、同じ単語でも後ろに来る言葉で語尾の形が変わることを指します。
たとえば、「書く」という動詞は、後ろに続く言葉によって次のように形が変わります。
書かず / 書きて / 書く人 / 書けば / 書け
このように、まったく同じ単語でも後ろに来る言葉で語尾の形が変わるため、活用を覚えていないと文章が全く読めません。
活用は次の6種類に分かれるので、動詞や形容詞・形容動詞、助動詞など活用する単語はすべて、「未然形はどういう形」「連用形はどういう形」というものを覚えていないといけません。
- 未然形
- 連用形
- 終止形
- 連体形
- 已然形
- 命令形
そして、この活用形がなにかを知っていないと、後ろに来る言葉の意味がわからないということもあります。
どういうこと?と思う方も多いかもしれませんが、次の2つの文章を見てみてください。
花、咲きぬ。
花、咲かぬこと、
この2つは同じ「ぬ」という単語が使われていますが、意味は大きく違います。
違いに気づくには、1つめが「咲き」という活用(連用形)になっていること、2つ目が「咲か」という活用(未然形)になっていること、そしてこの2つの活用形によって「ぬ」の意味が変わってくることの3つを知っていないといけません。
詳しくは3つ目のポイント「接続・識別」のところでお伝えしますが、活用形を完璧に覚えていないと意味の識別が正確にできないので、古文を読み解くために、活用は一番最初に覚えましょう。
活用に関しては、以下の記事も参考にしてください。
古典文法で覚えるべきポイント②:意味
活用を覚えたら、次に覚えるのは「意味」。
動詞や形容詞の意味などは単語の部類に入りますが、助詞や助動詞などの「付属語」(それ単体では意味をなさない単語)の意味は覚えていなければいけません。
たとえば、先ほどの例で使った「書かず」の「ず」は”打ち消し”の意味を持っています。現代語に訳すと「〜ない」です。
古文単語や助動詞には「1つにつき2つ以上の意味を持つ」というものが多く、すべての意味を覚えないと試験で対応できないのです。

日本語は「〜しよう」「〜したい」「〜しない」のように語尾で意味が決まるので、助動詞や助詞など語尾に来る部分の意味を正確に覚えていないと、いくら単語の意味がわかっても正確に読めないのです。
助動詞の意味はすべて、助詞も重要なものはすべて表などで覚えておく必要があります。
古典文法で覚えるべきポイント③:接続・識別
活用と助詞・助動詞の意味がわかったら、最後に「助動詞の接続」を覚えて、単語の識別ができるようにしていきます。
ある特定の助動詞の上にくる、動詞や形容詞の活用形は決まっていて、これを「接続」とまとめて呼びます。
たとえば、打消の助動詞「ず」の上にくる動詞は、「起きず」「動かず」など必ず未然形になります。
この場合、助動詞「ず」は未然形接続の助動詞と呼ばれます。
「ず」以外の助動詞にも同じようなルールがあります。
よって、どの助動詞が使われているか見極めて、この後の「識別」を正確に行うために、この「接続」は重要なヒントになるのです。
これまで勉強してきた「活用」は、この助動詞の「接続」を見極めるために重要になるわけですね。
そして識別とは、文章中に書かれている単語の品詞・意味が何かを判別することです。
古典では、一見同じ文字を使っていても意味が違うことがあります。そのため、どの文法事項が使われているかを区別できないと、文章の意味を捉え違えてしまいます。
正しく文章を読み解くために、きちんと識別できる力を身につけましょう。

具体的な参考書として、『ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル』の内容をあげて解説します。
『ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル』では、26章から30章までの中に識別の解説が掲載されています。
その中でも注目すべきは、解説の中に書かれている『判断するポイント』です。
この部分では、識別の際に確認すべきポイントを簡潔に紹介しています。
例えば、
“「る・れ」の識別では「る・れ」のすぐ上の一字の音を見て判断する”
というように紹介されています。
この判断ポイントをしっかり覚えることは大切です。

識別をする際は、助動詞だけでなく動詞や助詞など複数の品詞から選ぶため、少なからずややこしさもあります。
しかし、「どこが識別するポイントなのか?」を理解できれば必ず識別できるようになるので安心してください!
識別の際に迷いがちな助詞と助動詞について詳しく知りたい人は、以下の記事をチェックしましょう。

古典文法の覚え方&勉強法
古典文法で何を勉強すればいいかわかったところで、具体的な勉強法を解説していきます。主な勉強法は、3つです。
古典文法は次の順番で勉強していきましょう。
- Step1
- 用言(動詞・形容詞・形容動詞)の活用を覚える
- Step2
- 助動詞の「活用・意味・接続」を覚える
- Step3
- 助詞やその他の文法事項を覚える
- Step4
- 識別の練習をする
これらの勉強法を実践して、古文文法を自分のものにしていきましょう。
古文文法の勉強ステップ1:用言(動詞・形容詞・形容動詞)の活用を覚える
まずは簡単なところ、かつ基本的なところから覚えていきましょう。
活用する自立語(単体で意味をなす単語)のことを「用言」といいますが、まずは用言である動詞・形容詞・形容動詞の活用から覚えていきます。
活用で覚えるべきなのは
- 活用の種類(四段活用など)
- 活用形
の2つだけ。活用の種類は次のとおりですね。
- 動詞の活用
- 四段活用
上一段活用
下一段活用
上二段活用
下二段活用
変格活用(カ行・サ行・ナ行・ラ行) - 形容詞の活用
- ク活用
シク活用 - 形容動詞の活用
- ナリ活用
タリ活用
「どの動詞はどの活用の種類か?」の見極めができれば、後はそれぞれの活用の種類がどう活用するのかを覚えるだけです。
活用形を覚える場合は、声に出して何度も音読することが大事です。
動詞の四段活用を例に、実際にどうやって音読すればいいか説明しましょう。
動詞の四段活用の活用パターンは、
未然形・連用形・終止形・連体形・已然形・命令形の順に、必ず「ア・イ・ウ・ウ・エ・エ」
となります。
たとえば「書く」という四段活用の動詞は、「書か・書き・書く・書く・書け・書け」となるわけです。
この活用パターンをひたすら音読してください。おもわず口ずさんでしまうくらい何度も何度も。
この例で言うと「ア・イ・ウ・ウ・エ・エ」を何度も何度も繰り返しましょう!

古文文法の勉強ステップ2:助動詞の「活用・意味・接続」を覚える
用言の活用を覚えることができたら、次は助動詞を覚えていきます。
古典文法の一番の難所がこの「助動詞」ですが、覚えることは次の3つです。
- 活用
- 意味
- 接続
この3つを、用言と同様に何度も声に出して唱えながら覚えていくのがポイントです。それぞれについてはすでに説明をしているとおりですが、参考書などについている助動詞の表には、必ず上から「接続」「活用」「意味」の順に載っているはずです。
助動詞の「活用・意味・接続」を覚えるということは、助動詞の表をすべて覚えるということです。

たしかに、ただこの表を眺めたり、やたら唱えたりするだけでは覚えるのに時間がかかってしまいます。
助動詞の表は接続→活用・意味の順に整理して覚えるのがコツです。
まずは助動詞の接続を覚えます。未然形接続はどの助動詞で、連用形接続はどの助動詞で、と覚えていくのがポイントです。
- 未然形接続
- る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほし
- 連用形接続
- つ・ぬ・たり・けり・たし・き・けむ
- 終止形接続
- らむ・べし・まじ・らし・なり・めり
- 連体形・体言接続
- なり・たり・ごとし
- 特殊系(「サ未四已」)
- り
古文の助動詞接続は、表を見るとこれらに分類されているはずです。
これをたとえば「未然形接続は『る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほし』、『る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほし』……」と何度も唱えて覚えていけばOKです。
唱えるだけで覚えにくい場合は、替え歌の語呂合わせで覚えるという手もあります。
歌だとより口ずさみやすく、かつフレーズで助動詞の接続が切り替わるので無意識のうちに覚えられます。
横軸で「接続」を覚えたら、次に「活用」「意味」を覚えていきます。
このときもいきなり全ての助動詞を覚えようとするのではなく、「まず今週は未然形接続の助動詞の活用を覚えよう」というふうに分けて覚えるのがおすすめです。
未然形接続の活用をすべて覚えたら意味を覚えて、覚えたら連用形接続に進んで、というふうに取り組むと、1ヶ月〜2ヶ月で助動詞をすべて覚えられるはずです。

表のヨコ→タテの順で唱えて覚える、という工夫で楽に覚えましょう!
古文文法の勉強ステップ3:助詞やその他の文法事項を覚える
助動詞をすべて覚えることができたら、助詞やその他の文法事項も覚えていきます。
助詞も助動詞のように表がありましが、すべて覚える必要はなく現代語と違う意味のものの意味だけ覚えられればOKです。どうしても必要なものは演習しながらでも覚えられるので、時間をかけすぎないようにしましょう。
助詞以外にも「係り結びの法則」など細かい文法事項があります。参考書によっては敬語も文法事項として扱っていることがあるので、これもこの際に覚えておきましょう。
古文文法の勉強ステップ4:識別の練習をする
ここまでで、古文の品詞ごとの重要なものについては一通り覚えました。これでようやく古文の識別について勉強する準備が整ったので、ここからは問題集を使って識別の練習をしていきなり文章を読み始めるのが不安な場合は、「品詞分解」の練習をしてから読解に取り組みましょう。
ここまでの勉強は表さえあれば覚えられるので、『スタディサプリ』などで知識のインプットさえできれば問題集はなくても進められましたが、識別は実際の文章を見ながら実践していくことではじめて身につきます。
古文の「文法問題集」と言われる参考書、例えば先程紹介した『ステップアップノート』やこの後紹介する『日栄社30日完成古文』などでは、最後のほうに必ず識別についてのページが複数あります。使いやすい参考書で構わないので、問題を解いて識別の練習をしていきましょう。
このとき、識別をしながら忘れていた活用形やルールは、参考書や文法書を見返してその都度覚え直す事を忘れないでください。
古典文法を覚えるためのおすすめ参考書
ここまで古典文法の覚え方を紹介してきましたが、それぞれの活用や意味・接続の暗記までは、学校の授業をある程度受けていれば表さえあれば覚えられるので、参考書を無理に新しく買う必要はありません。
ここでは、
- 古典文法の基本をゼロから勉強するための参考書
- 古文の識別を中心に、知識を定着させる問題集
の2つを紹介しておきます。表だけで知識を覚えてもいまひとつ不安、この記事で読んだ内容を完全に理解できていない、という場合は1冊目から取り組むのがおすすめです。
古典文法おすすめ参考書①:『富井の古典文法をはじめからていねいに』
『富井の古典文法をはじめからていねいに』では、文法のポイントや受験にとって大事なポイントが過不足なくまとめられています。
古文の品詞について、助動詞や助詞についてなどが講義調でまとまっているため、独学でも読み進めやすいはずです。古文が苦手な人にはおすすめです。
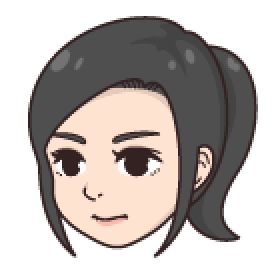
古典文法おすすめ参考書②:『日栄社発展30日完成古文高校中級用』
日栄社の『発展30日完成古文』は、初級・中級・上級とステップ別に古文の文法・読解の演習ができるすぐれもの。歴史のある問題集ですが、解答に品詞分解がついているためとことん識別の練習をすることができます。
詳しい使い方はこちらでもチェックができます。
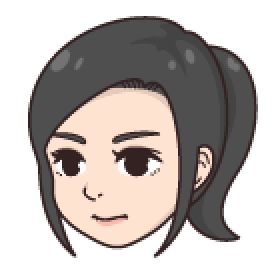
古文文法の参考書の使い方
これらの文法の参考書は次のように使っていきましょう。
- Step1
- 文法の重要ポイントを確認
- Step2
- 実際の問題を解く
- Step3
- 解説を読み、わからないところ、覚えられてないところを復習
- Step4
- 間違えた問題、不安な問題をもう一度解く
それぞれのステップについて簡単に見ていきましょう。
Step1. 文法の重要ポイントを確認
まずは文法の理解から。勉強しはじめてすぐの人や古文が苦手な人は、必ず問題を解く前に「重要ポイント」を見て、頭の中で整理してから問題を解きましょう。この部分を問題集ではなく『はじめからていねいに』『スタディサプリ』などで補うのもおすすめです。
Step2. 実際に問題を解く
理解ができたら実際に問題を解いていきます。ここでのポイントは、「なぜその答えになったのかを考えながら解く」ということです。
根拠がない解き方は絶対にダメ。受験で出題される問題には必ず正解になる根拠があります。正解の理由を説明できない場合は、次に似た問題が出たときに正解できない可能性があります。
Step3. 解説を読み、わからないところ、覚えられてないところを復習
問題を解いたら解説を読みます。このとき、Step2で考えた「なぜその答えになったのか」のプロセスが合っていたかを確認しましょう。合っていない場合は、足りていなかった暗記事項をその場でもう一度確認して覚え直してください。
Step4. 間違えた問題、不安な問題をもう一度解く
間違えた問題をもう一度解きましょう。「正解していたがたまたま合っていた」という問題も、この時必ず解き直してください。

まとめ

- 「活用」「意味」「接続」を覚える
- 用言の活用、助動詞の活用・意味・接続をまず最初に覚えることが、古文の文法学習の第一歩!
- 問題集を繰り返し解いて「識別」の練習
- 古文の識別は問題集で何度も解いて身につける。「なぜこの答えになるのか?」まで答えられなければ覚えなおそう。
一見すると覚えることが多そうでうが、英語や社会に比べれば圧倒的に覚えることは少ないはずです。長期休みにまとめて覚えるもよし、毎日コツコツ覚えるもよし。理想は高2の間までに覚えきって、高3からは読解の演習に入れるようにしたいですね。
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば古文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
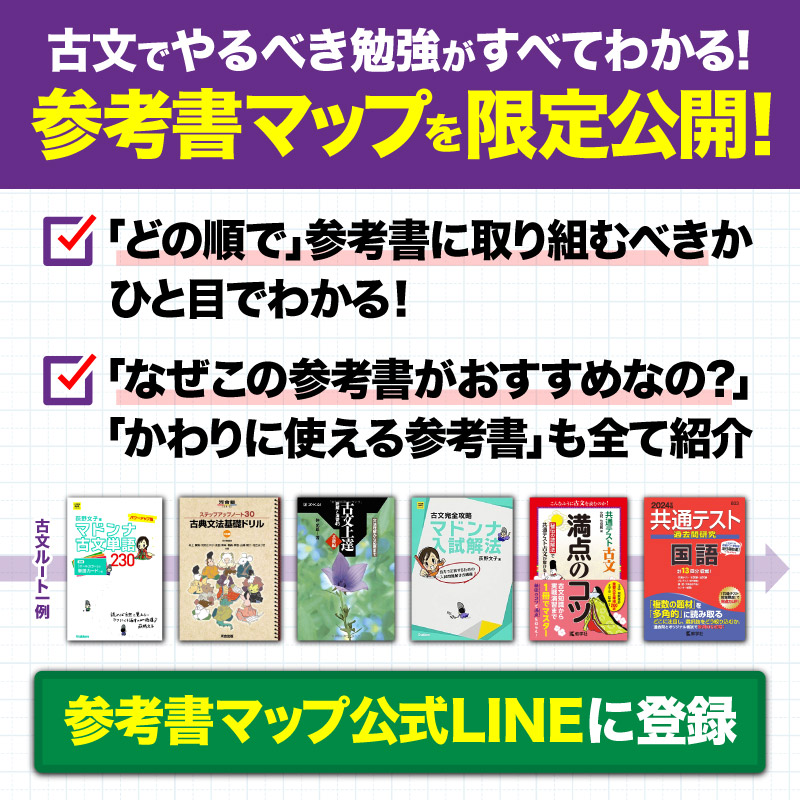
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る古文の勉強法は、こちらの記事でも詳しく説明しています。