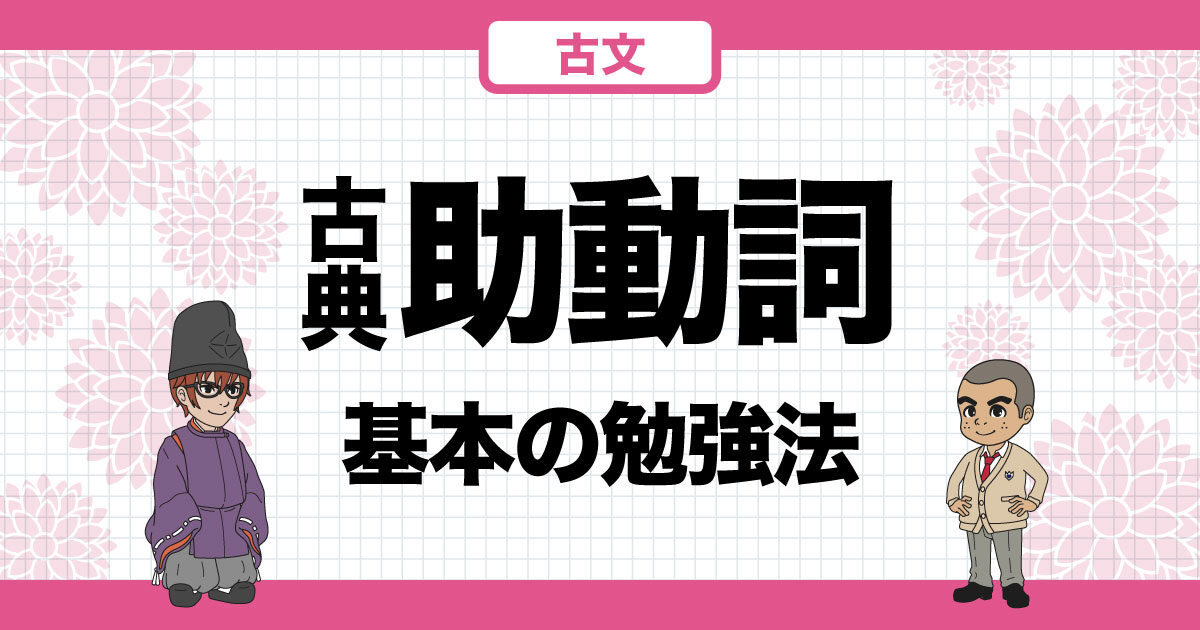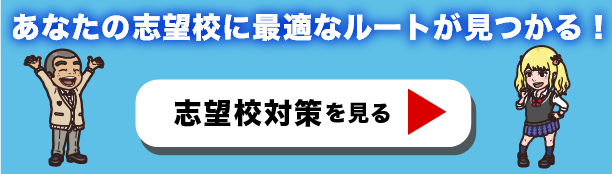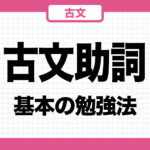古典の文法の中で、最も重要な項目が助動詞。助動詞がわからないと古文を正確に読めるようになりません。
しかし、助動詞は意味がいくつもあって複雑で、「正直、覚えるのが苦手…」と思っている人が多いのではないでしょうか。この記事では、そんな人の悩みを解消するべく、「助動詞が苦手な人」でも「2週間で助動詞を完璧に身につける勉強法」をご紹介します。
古文助動詞の勉強法については、以下の動画でも解説しています!
今回は次の流れで説明していきます。




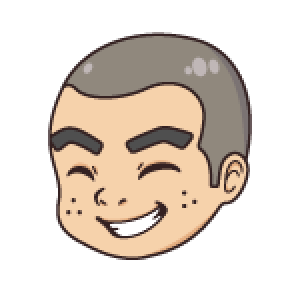
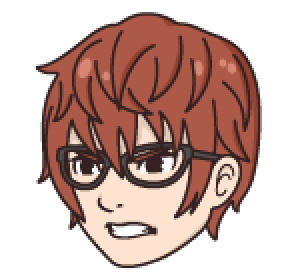


なぜ古文の助動詞を覚える必要があるのか?


マルオ君のように「助動詞って全部必要なの?」と思う人も多いと思います。確かに量は多いものの、文章の中に登場する頻度は助動詞によりまちまちです。あまり登場しない助動詞も多くあります。
しかし結論から言うと、助動詞は必ず全種類覚えるべきです。
なぜ助動詞はすべて正確に覚えていないといけないのか、かんたんに解説していきましょう。
古文の助動詞で「文の意味」が180度変わる!
なぜ助動詞を正確に覚えている必要があるかというと、古文の助動詞は「文の意味の大事な部分」をコントロールしているものだから。
助動詞は文の終わりの方に来ることが多く、今の言葉で言えば
「勉強した」
「勉強しよう」
「勉強しない」
「勉強したい」
の太字の部分があてはまります。
日本語は文の最後で意味を決めるので、これら4つの言葉は前半こそ同じでも意味が大きく異なりますよね。
この「〜た」「〜よう」などの意味が正確にわかっていないと、文の意味を正確につかめません。
古文の助動詞も役割は同じ。
助動詞で文の意味が決まるため、正確に助動詞を覚えられていないと、文の意味を捉え間違えてしまい、なんとなくで読んでしまうことにつながりかねません。
だから、古文の助動詞の勉強は最重要、と言われるんですね。
古文の助動詞は「全部」覚えるべき!
このように大事な助動詞なので、必ず表に載っているすべての助動詞について覚える必要があります。
あかなし「「「覚えるべき助動詞はこれらだな!」」」
- 未然形接続
- る、らる、す、さす、しむ、ず、じ、む、むず、まし、まほし
- 連用形接続
- つ、ぬ、たり、き、けり、たし、けむ
- 終止形接続
- らむ、べし、まじ、らし、なり、めり
- 体言・連体形接続
- なり・たり・ごとし
- 特殊(サ行の未然形・四段の已然形)
- り
どの助動詞も文章では使われますし、出てくる頻度が高くないものも、その分重要な意味を持っていて、問題で聞かれる事が多いので注意が必要です。
唯一「ごとし」だけは現代語にも近いぶん問題で問われにくいですが、それ以外はすべて出題される可能性があると思っておきましょう。
助動詞で覚えるべき3つのこと
このように、助動詞はすべての種類を覚えておく必要がありますが、助動詞の「何を」具体的に覚えるかは限られています。それは、次の3つです。
- 接続
- その助動詞の上にくる用言(動詞など)の活用形がなにか
- 活用
- その助動詞をどう活用するか
- 意味
- その助動詞がどんな意味を持っているか
助動詞の参考書を見てみると、この3つ以外にもたくさん書いてありますが、必要な知識はこの3つに集約されます。接続、活用、意味の3つを覚えれば文章を読めるようになるので、助動詞をなかなか覚えられない人はこの3つを集中的に覚えましょう。
まずは表に書いてある3つのことを覚えて、意味が複数あるものは一旦覚えたあとで、問題演習を通じて見分け方を覚えていくことになります。
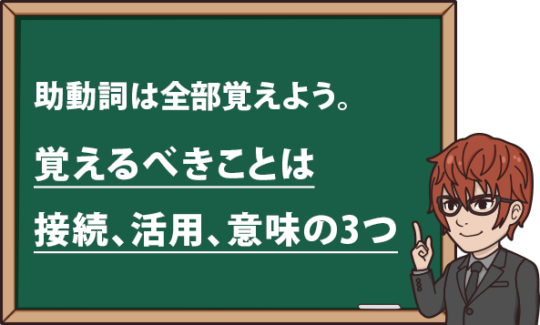
助動詞の効率的な覚え方を知ろう!
ここからは、助動詞の具体的な覚え方を見ていくことにしましょう。「覚える」というと、単語帳のようになんどもテストしたり、歴史のように問題を何度も解いたりということが思い浮かぶかもしれませんが、ただ表を見たり、問題を解いたりするだけでは覚えられないのが助動詞です。
短時間勝負!助動詞は2週間で一気に覚えてしまおう
助動詞をなかなか覚えられない、というひとは、時間をかけて少しずつ覚えようとしていませんか?
古文の助動詞は、英語の文法に比べて覚える量が少ないので、短期集中で一気に覚えきってしまい、その後は忘れないように定期的に確認する程度でいいのです。
古文の文法書などに載っている助動詞の表を見てみるとわかりますが、助動詞は全部で30個ほど。1週間で15個ずつ、と考えると大変そうですが、1日3つの助動詞に絞って覚えていけば、最後に復習をする日も含めて2週間で覚えることができます。
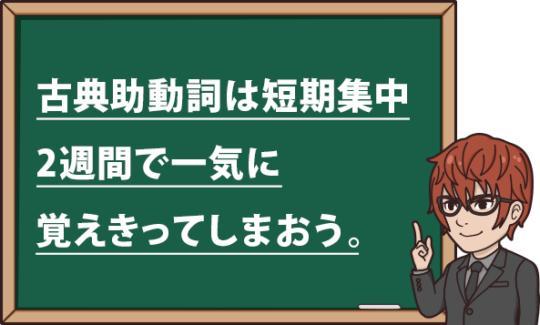
具体的な覚え方
助動詞を覚える上でのオススメの勉強法は2つ。
- 小分けにして何度も唱えて覚える
- 歌に合わせて覚える
どちらもそれぞれ良さがあるので、自分にあうやり方で覚えていきましょう。
小分けにして、何度も唱えて覚える
助動詞を覚える上で基本の覚え方は、この「小分けにして何度も唱えて覚える」やりかた。
簡単に言うと「同じ接続の助動詞をまずまとめて覚えてしまって、接続ごとに活用や意味も繰り返し覚える」ことです。小分けにしたほうが頭の中が整理されやすく、かつ実用的です。
覚え方のステップは次の通り。
- ステップ1
- 助動詞の「接続」を覚えるために、接続ごとにまとめて何度も唱える
- ステップ2
- 接続を覚えたら、まずは未然形接続の助動詞だけでいいので、意味と接続を覚えていく。同じような意味の助動詞はまとめて覚える。
- ステップ3
- ステップ2を他の接続についても繰り返す。
接続の覚え方を例に、まとめて覚えてしまうとどれほど簡単に覚えられるか、見ていきましょう。
- る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほし
- つ・ぬ・たり・けむ・けり・たし・き
- べし・まじ・らむ・めり・なり・たし
- なり・たり・ごとし
- り
この文字の並びを見て何かピンとこないでしょうか?

これは助動詞を接続別にまとめたもので、上から順に未然形、連用形、終止形、連体形、特殊形になっています。
接続を覚えるときは、「『ず』は未然形接続で、『まじ』は終止形接続で……」というように、一つ一つの助動詞ごとに接続を暗記していくのではなく、「る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほしは未然形接続!」というようにまとめて覚えてしまうことがポイントです。一つ一つ覚えるのは非常に労力がかかりますし、どれがどれだかわからなくなってしまいますからね。
まずはこの「接続」ごとに、なんども「未然形接続は る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほし……る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほし……」と唱えて覚えましょう。寝る前や学校の休み時間、歩いている時間やトイレ・お風呂などのスキマ時間もいくらでも活用できます。
接続ごとにまずすべての助動詞の「終止形」を覚えたら、ここからも重要。
すべての助動詞の活用・意味を片っ端から覚えていくのは大変なので、「この3日間は未然形接続の助動詞」というように小分けにしてまとめるのがおすすめです。
「まずは未然形接続を覚えよう」と決めたら、3日間ひたすら「『る』の活用は れ・れ・る・るる・るれ・れよ、れ・れ・る・るる・るれ・れよ…」となんども唱えて覚えます。いきなり意味も活用も両方覚えるのは難しい!という場合は、まずは活用だけ覚えてもOKです。
意味を覚えるときも同じように小分けにして覚えていきましょう。
このとき、同じ意味の助動詞があればセットで覚えてしまうのがおすすめです。
例えば先程挙げた「る」の意味は「受身・自発・可能・尊敬」と4種類ありますが、「る」だけでなく「らる」も同じ意味を持ちます。
そのため、「『る』『らる』は『受身・自発・可能・尊敬』、『受身・自発・可能・尊敬』……」と覚えればいいんですね。
ほかにも、過去の助動詞「き」「けり」などが挙げられます。
この2つの助動詞は、細かく分別すれば「き」が体験過去で「けり」が伝聞過去と、微妙に意味が違うのですが、まずはどちらも「過去」と覚えてしまってOKです。
実際に助動詞を使って文章を読んでいくときは、たしかにこういった細かい区別や、「この文章ではどの意味で使われているか」の見極めが必要になります。ただ、いきなりそういった意味の見極めや違いまで覚えようとするとパンクしてしまうので、まずはシンプルに意味だけを覚えて、あとから理解を紐づけていくほうが、数が少ない助動詞を覚える場合は得策ということです。
活用については、こちらの記事も参考にすると覚えやすいでしょう。
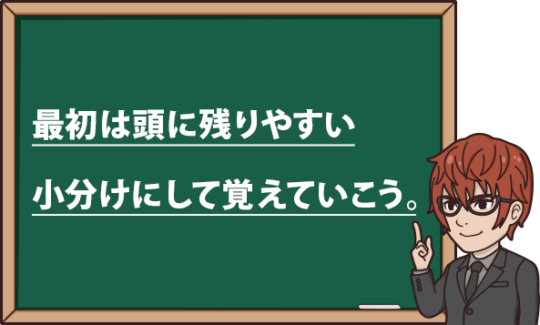
歌に合わせて覚える
次に紹介するのは替え歌に乗せて覚える方法です。こちらも古典ではおなじみの勉強方法ですから、学校などで聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
歌で覚えることは、特に助動詞の「接続」を覚えるのに特に効果的です。


歌に乗せて何度も繰り返しましょう。繰り返す目安は、1日10回以上 です。
暗唱できるまでは何度も繰り返しましょう。人によって差はありますが、こちらも2週間も繰り返せばほとんど覚えられます。好きな歌を覚える感じで楽しく覚えましょう。
有名なのが「もしもしかめよ」の替え歌。
助動詞の終止形をただ並べただけではなく、接続ごとに分けて歌っているので、接続も合わせて覚えられるというわけです。
以上の例でもいいですし、学校で先生から教わったものでも、自分で作ったものでもなんでもいいです。歌に乗せて効率よく覚えましょう。

問:次の空欄に助動詞「ぬ」を適切な形に活用させて入れよ。
人にも、おほやけにも、失せかくれ( )たる由を知らせてあり。(2016年 学習院大学)
まず、着眼すべきは空欄の後ろです。後ろには、助動詞「たり」の連体形「たる」があります。「たり」の接続を歌から思い出してみると…。
そう。「たり」は歌の中で、接続は連用形だ、と覚えましたよね。
連用形接続ということは、この助動詞の前に来る用言は連用形になる、ということなので、「ぬ」を連用形に直せば正しい形になります。よって、答えは「ぬ」の連用形である、「に」です。

古文の助動詞暗記におすすめの参考書と勉強法


ここからは参考書を使った具体的な勉強法を紹介していきます。
やはり歌などで覚えるだけでは、試験で得点できるようになりません。あくまでここまでで覚えたものは「接続・活用・意味」で、実際の問題ではそれを使った意味の見極めなどが出されるので、ここまで覚えてはじめて文法問題が解けるようになり、長文問題でも正確に読めるようになります。
参考書を効果的に使って助動詞をものにしましょう。
おすすめの参考書は次の2つです。
『ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル』
『ステップアップノート』は助動詞だけではなく、文法全体を紹介してくれている参考書です。助動詞は意味ごとに小分けにして紹介しており、意味の見極めについても説明が簡単についているためわかりやすくなっています。
日栄社『発展30日完成古文 高校中級編』
こちらも文法全体を紹介してくれている参考書です。後半は文章問題になっているため、読解の中で文法を復習することもできて一石二鳥です。
見た目が古いですが、この参考書のポイントは品詞分解が解説についていること。

古文の文章を品詞(単語)ごとに区切って、助動詞の意味や敬語の用法などを書き込んでいく作業を「品詞分解」といいます。
英語で言う「英文解釈」に近く、文章の意味を正確に取るために練習することが多いですね。
この参考書を使うときはぜひ「品詞分解」で、出てきた助動詞の意味をすべて確認するようにしてください。
オレンジ色の「中級」が難しい場合は、桃色の「初級」や、文法の演習だけに焦点を当てた「古典文法サブノート」を活用するのもおすすめです。
助動詞の使い方をマスターするための「参考書の使い方」
上で紹介した2つの参考書の使い方も必ず確認しておきましょう。
特に助動詞は、ただ問題を解くだけでは身につかないことがほとんど。問題集の文法問題は「適切な形に直しなさい」という問題や「活用を答えなさい」「訳しなさい」といった問題が多いですが、実際の入試では文法問題や訳以上に、長文の中で正確に助動詞の意味を見分けられるかが重要になるので、ただ問題演習をするだけでは実用的ではありません。
問題集の勉強法は次の通り。
- ステップ1
- 問題集をコピーして、品詞分解をしながら問題を解く
- ステップ2
- 答え合わせをして、間違ったものだけでなく「たまたま正解していたもの」にも印をつける
- ステップ3
- 解説を読んで見極め方を理解し、抜けていた文法事項をその場で何度も唱えて覚える
これらの参考書は、1回やって終わりにするのではなく、頭に残るまで何周も繰り返すことをおすすめします。
このときに品詞分解を書き込んでしまうと2周めに取り組むときに消さないといけないので、コピーを取って書き込むといいですね。
品詞分解のときは、単語ごとに区切る線を入れていきながら、助動詞だけ○で囲って、横に意味を書き込むのがおすすめです。別途敬語の勉強もしていれば、敬意の方向なども書き込んでおくとバッチリですね。
品詞分解と合わせて問題を解き、答え合わせの際に単語や意味の識別、品詞分解が合っているかも確認しましょう。
合っていた問題でも「たまたま正解した」というものは印をつけて、2周めで解き直すようにしてください。
ここで抜けていた助動詞や意味の見極め方を忘れていた助動詞を覚え直せばOKです。
今回紹介した問題集であれば、1章(2ページ)につき30分程度を目安に解き進められるといいですね。


助動詞の覚え方まとめ
今回は古文文法でもっとも重要な「助動詞の覚え方」について見ていきました。大事な点は3つ。
- 「接続・活用・意味」が重要
- 必ずすべての助動詞を覚えよう!「接続・活用・意味」の3つが覚えられればまずはOK
- まとまりごとに何度も唱える・歌で覚える
- 細かい用法よりもまずは「接続・活用・意味」を覚えることが大事。最初に接続を歌やまとまりで覚えて、そこに活用・意味を紐付けよう。声に出すことがポイント!
- 最後は問題集で演習
- 読解でも使えるように問題集で繰り返し演習。品詞分解をすることで助動詞の見極めを何度も演習できる!
助動詞は古文の読解に直接つながる重要な内容。逆に言えばこの助動詞と単語さえ覚えられれば、正確に古文の文章を読むことができるようになります。最初につまずく分野ではありますが、とにかく何度も繰り返し唱えて、丁寧に問題演習をして短期間で覚えてしまいましょう!
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば古文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
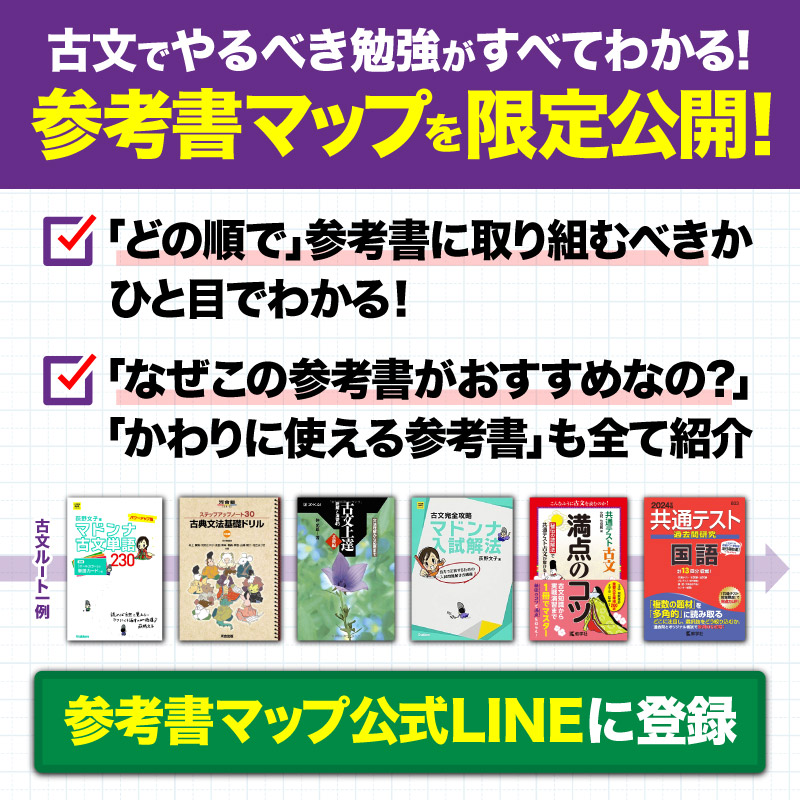
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る古文文法全体の勉強法はこちらもチェック!
他の文法事項もチェック!
文法が固まったら読解に進もう!