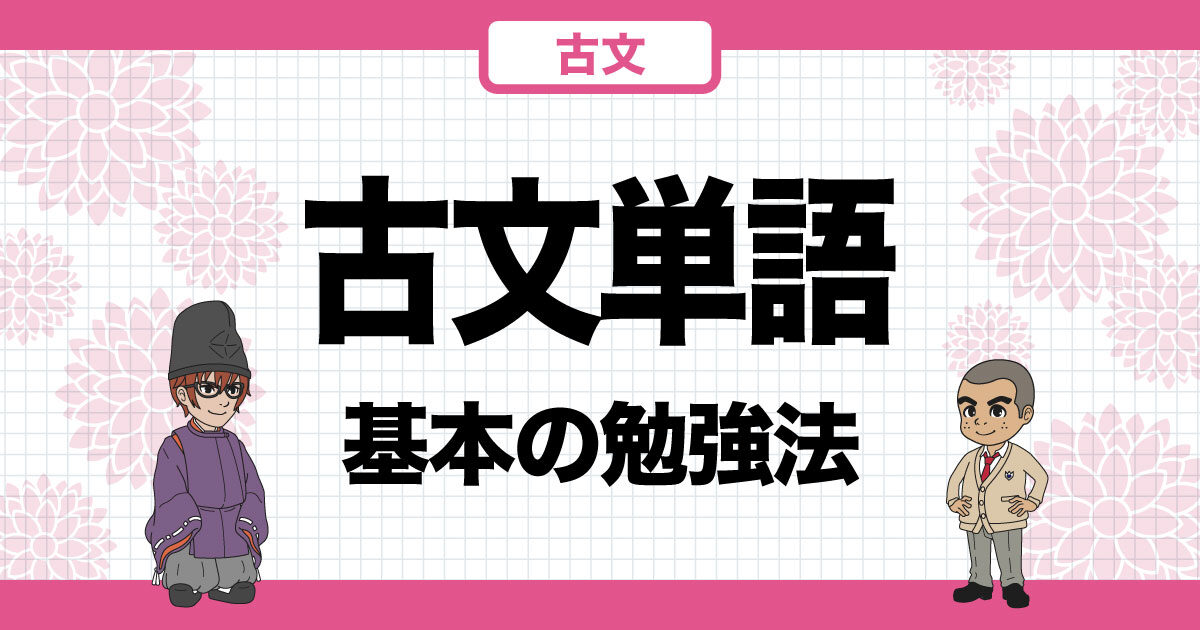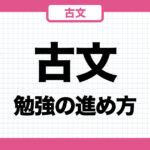古典の勉強において避けられない道である単語の勉強。単語をどれだけしっかり勉強できるかどうかで古文の出来を左右してしまいます。
しかし多くの人が「どうやって覚えたらいいの?」「どれくらい覚えればいいの?」という悩みを抱えがちです。この記事ではそういった悩みを解決すべく、「単語知識ゼロ」でも「早慶レベル」まで持っていくための勉強法をご紹介します。


古文単語の勉強については以下の動画もご覧ください。
古文単語はいくつ覚えればいいの?


単語をどれくらい覚えておけばいいか知ってますか??
実は英単語みたいに2000単語も覚える必要はないんです。
書店に行って単語帳を見たことある人はわかると思いますが、単語数が明らかに英語に比べて少ないですよね。古典単語は多くても600単語も覚えれば十分です。そしてそのうち300単語も覚えていればある程度の文章は読めてしまいます。
現代語と似ている意味の言葉や、今の言葉の語源になっている言葉も多いので、そもそも英語みたいに単語暗記でそんなに頑張らなくてもいいんですね。
なので、古文単語は単語帳1冊を完璧にすれば大丈夫です。
1冊でいいの?と疑う人もいると思いますが、多くの単語帳では入試でよく問われる重要単語を網羅しているので、ご安心を。とにかく、単語帳1冊をきちんと覚えきりましょう。



暗記が楽になる古文単語の勉強法


単語帳を使った古典単語の勉強を詳しく紹介していきます。
今回の記事では『重要古文単語315』を使った勉強法を紹介します。
関連語や例文が豊富に掲載されている上に、品詞ごとに単語がまとめられている参考書です。各単語の下に赤字で現代語訳が書かれているため、赤シートで隠して覚えることができます。初めの3周くらいは、まず「赤字の意味」を見ていきましょう。
このとき心がけておくべきルールは2つです。
- 赤字の意味だけを覚える
- なるべくたくさん繰り返す
古文単語の覚え方①:赤字の意味だけ覚える
古文の単語帳をみてください。関連語をはじめ、1つの単語についてたくさんの意味が一緒に書かれていると思います。特に古文単語は英単語とは違い、現代語と近い意味であったり、ニュアンスによって使い分けている単語もあります。
もちろん、最終的には全部覚えておかないと、現代語訳に直す時に間違った訳を書いてしまったり、文脈を正しくつかめなかったりします。しかし、最初にこうした細かい情報を覚えようとしてもこんがらがってしまい、結局なかなか覚えることができないことが多いです。
なので、まずは単語は赤字の意味だけを覚えましょう。

古文単語の覚え方②:なるべくたくさん繰り返す
古文単語を覚える上で、暗記するのが苦手だという人に特に実践してほしいことが、「なるべくたくさん繰り返す」ことです。繰り返し暗記することで、脳が「これは大事な情報なんだ」と認識して、より効率よく定着させられます。
では、実際にどういう流れでやればいいのかをみていきましょう。
1周目:赤字の意味を定着させる
- Step1
- 1ページずつ見出しの単語を見て、現代語訳を覚える
- Step2
- 1ページが完璧になったと思ったら、赤シートを使い単語を見て現代語訳を思い出せるかテストする
- Step3
- 間違えた単語の現代語訳をもう一度覚える
- Step4
- 完璧になったと思ったらもう一度テストする
- Step5
- step3〜4を完璧になるまで繰り返す
- Step6
- 1ページ完璧になったらStep.1〜5を1セクション(30単語)が終わるまで繰り返す
1周目では、1ページずつ見出しの単語を見て現代語訳を覚えましょう。古文単語は各単語の解説が詳しいものが多いので、必ず一回は解説を読んでください。
1ページが完璧になったと思ったら、赤シートを使ってテストします。間違えたものはもう一度覚えなおしてテストしてください。これを1ページ完璧になるまで繰り返しましょう。

2~3周目:赤字を定着させる
- Step1
- 1周目でやった単語の現代語訳をどこまで覚えているか、赤シートを使い1セクションまるまるテストする(間違えたものには×印をつける)
- Step2
- 間違ったものだけ完璧だと思うまで繰り返し見る。また、各単語の解説を読んで理解を深める
- Step3
- 完璧になったと思ったら、もう一度テストする
- Step4
- step.2〜3を完璧になるまで繰り返す
覚えるときは「見るだけ・読むだけ」でもいいですが、必ず赤シートを使って覚えるようにしましょう。古文の単語帳の多くは各単語についての詳しい解説が書かれています。その単語の語源や使い方が書かれているので、解説を読むことも、現代語訳を覚えるのに役立ちますよ。
また、古文では「単語→現代語訳」がわかれば十分です。ほとんどの問題では現代語に訳す力が求められるので、現代語から古文単語に直す練習は必要ありません。
最初の1〜3周目は何度も繰り返し取り組んで、単語に触れる回数を稼ぎましょう。
このペースで3周すると大体1ヶ月で終わります。

最初の3周では、とにかく赤字であるメインの現代語訳を覚えることにのみ力を注いできましたね。
もちろんそれを完璧にするだけでも力はつきますが、4周目以降はメインではない関連要素に目を向けてみましょう。
ここから先は見るだけで十分です。関連語の多くはメインの現代語訳から派生した言葉なので、メインの現代語訳がわかっていれば意味が推測できるものがほとんどです。
「Aの単語とBの単語は同じ意味だったんだな」「CとDは同じ意味だけどニュアンスが全然違う」などがわかると思います 。
ここでも大事なのは、メインの現代語訳です。記憶の軸を作って覚えられるかどうかで古文が読めるようになれますし、4周目以降の関連語を覚えることもメインの現代語訳を覚えてなければ始まりません。
そうはいっても人間なので、いつかは忘れていってしまうもの。なのでそういう時は「チェックが付いているものの再チェック」を隙間時間など使ってやりましょう。

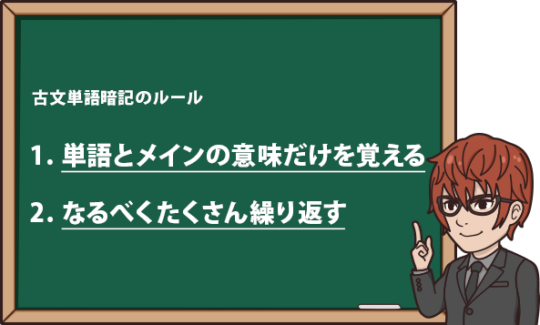
古文単語の覚え方のコツ
続いて、知っていると古文単語を覚えるのが楽になる覚え方のコツを3つ紹介します。
- 単語のイメージを掴む
- 漢字で覚える
- 現代語と違う意味を意識する
古文単語の覚え方のコツ①:単語のイメージを掴む
古文単語を覚えるコツはズバリ、「単語のイメージを掴む」ことです!例えば「おどろく」という古文単語がありますが、この単語には「驚く」「目を覚ます」という2つの意味があります。
普通に覚えようとすると、「驚く」の方はすぐに覚えられても、もうひとつの「目を覚ます」はなかなか覚えられなさそうですよね。
そんな時に有効なのが単語のイメージです。「おどろく」という単語のイメージは「衝撃によってハッとする」というもの。そのため現代語と同じように、ただ「驚く」という意味以外にも「(眠っている状況から)目を覚ます」という意味があるんです。
こうやって単語のイメージを最初に掴んで置くと、バラバラに「驚く」「目を覚ます」という2つの意味を覚えるよりも、簡単に覚えられます!
古文単語の覚え方のコツ②:漢字で覚える
覚え方のもうひとつのコツが、「漢字で覚える」というもの。例えば「めづ」という単語には「愛する」という意味がありますが、これは「めづ=愛づ」という漢字を当てることを知っていれば、一瞬で覚えることができます。
このように、古文単語の中には漢字を当てて簡単に覚えられるものがいくつもあります。そのため単語の意味を覚える前に、その単語が漢字で書けないかを確認しましょう。
古文単語の覚え方のコツ③:現代語と違う意味を意識する
覚え方の3つ目のコツが、「現代語と違う意味を意識する」こと。例えば、コツ①で解説した「おどろく」が「驚く」じゃない思っておくと、出てきたときにイメージしやすいです。
逆に、現代語と同じ意味の単語は覚えなくてもOKです。だいたいの単語は現代語と同じ意味でも使えるので、まずは訳してみてしっくりこなければ現代語の意味で答えましょう。
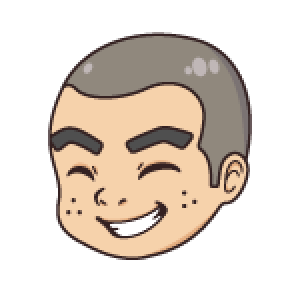

あなたにぴったりの参考書はこれ!!古文単語を覚えるためのレベル別単語帳
古典単語の覚え方がわかったところで、最後にこれから新しく参考書を買うあなたのためにオススメ参考書3選を紹介します。
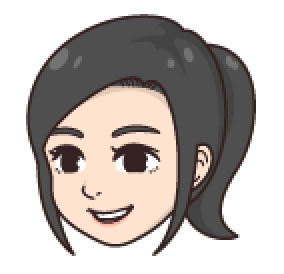

古文単語を覚えるための参考書 ①:『マドンナ古文単語230』
『マドンナ古文単語230』は、これから古典単語の勉強をはじめる人にぴったりの1冊です。収録数は230語と少なめですが、重要単語がきっちり網羅されています。重要な単語順にまとめてあり解説も豊富なので、初心者でも学びやすい1冊です。
敬語が載っていないので、古文が苦手な人の入門としておすすめです。
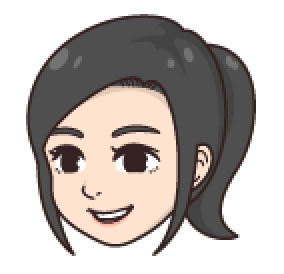
また、『マドンナ古文単語230』は解説がとても丁寧なのでしっかり読みましょう。
1周目に取り組む前に解説を2周読みましょう。わかりやすく書かれているのでサクサク読めると思います。
古文単語を覚えるための参考書 ②:『重要古文単語315』
『重要古文単語315』はシンプルなデザインの単語帳です。品詞ごとにカテゴリーが分かれており、苦手なところをピンポイントで勉強できます。巻末には慣用句や和歌など、付録の章では情報がたくさん載っているので、古典常識も学べて一石二鳥です。
付録の章や解説などは隙間時間に読んでみましょう。古典を得点源にしたい人にはオススメです。
この参考書の詳しい使い方はこちらをチェック!
古文単語を覚えるための参考書③:『新・ゴロゴ古文単語』
『新・ゴロゴ古文単語』は、古典の単語帳の中で一番知られている単語帳ではないでしょうか?
単語帳の名前通り、ゴロで単語の意味を覚えることができます。ゴロもイラストも面白いので、古典嫌いな人でも古典単語を楽しみながら覚えることができます。大事なポイントがコンパクトにまとまっているので、どんどん進めましょう。
ただし、掲載されている意味は充実していないため、国公立志望だと物足りません。そのため、「ゴロで覚えるのが好きな人」「古典がニガテすぎて単語を覚えられない人」「あまり古文対策に時間をかけられない理系の人」にオススメです。
この参考書の詳しい使い方はこちらをチェック!
まとめ

- 単語帳一冊をきちんと覚えきる!
- 単語と赤字の意味だけを覚える!
- なるべくたくさん繰り返す!
- かならずテストをする!
暗記の鉄則は「なんども繰り返す」「かならずテストをする」ことです。1周目で全てを暗記しようとせず、何周もして少しずつ覚えていきましょう。
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば古文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
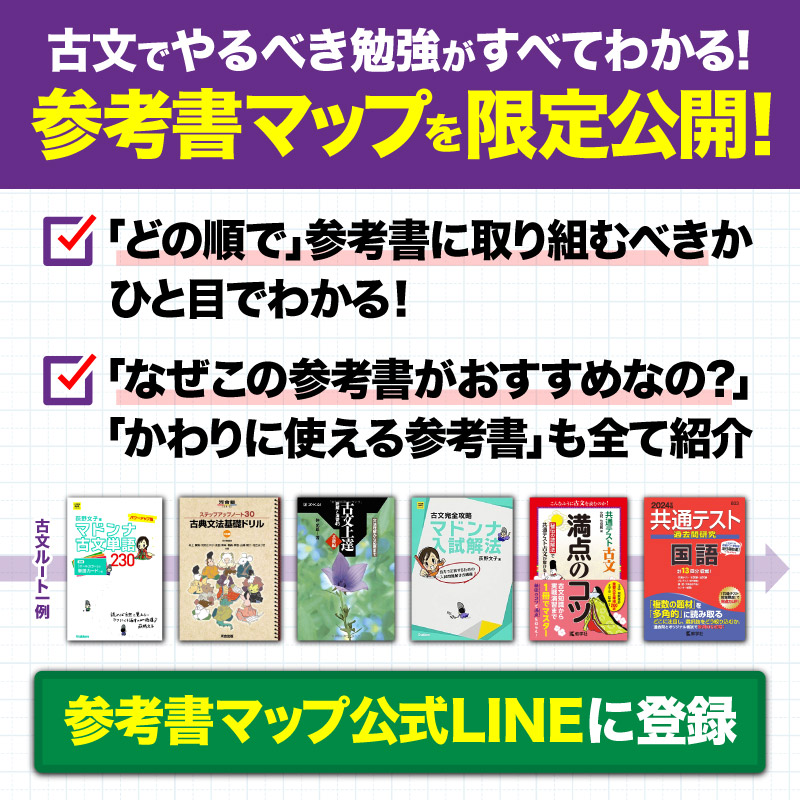
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る