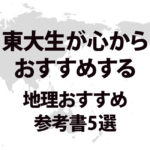『文系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学III』は、難関大学を志望する人にオススメの参考書です。
全国の大学入試の傾向から頻出の良問がまとまっているので、『青チャート』などの網羅系問題集で基礎固めが終わり、応用問題に挑戦したい人には特にオススメです。
今回の記事では『文系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学III』を最大限活用する勉強法や注意点について解説します!
『数学の良問プラチカ』シリーズはどんな参考書?
それでは『数学の良問プラチカ』シリーズがどんな参考書なのかを簡単に確認しましょう。
まず、『文系数学の良問プラチカ数学1A2B』についてご紹介します。
- 料金
- ¥1,257
- 問題数
- 149問
- 習得にかかる時間
- 223.5時間
- レベル
- 大学入試数学の中級~上級レベル
『文系数学の良問プラチカ数学1A2B』は、特に難関私大・国公立大を志望する文系学生にオススメの参考書です。
「共通テストレベルの問題は8割解けるが入試問題は解けない」「二次試験でも数学が出題される」という場合は、ぜひやっておきたい1冊です。
続いて、『理系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学III』についても確認しておきましょう。
- 料金
- ¥1,100
- 問題数
- 153問
- 習得にかかる時間
- 223.5時間
- レベル
- 大学入試数学の中級~上級レベル
- 料金
- ¥1,100
- 問題数
- 76問
- 習得にかかる時間
- 223.5時間
- レベル
- 大学入試数学の中級~上級レベル
『理系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学III』は、難関私大・国公立大を志望する理系学生にオススメの参考書です。
応用レベルの問題への対応力を身につけられるため、「基礎的な問題は解けるが応用問題になると躓きやすい人」は取り組みましょう。
『数学の良問プラチカ数学1A2B』のメリット・デメリット
まず、『文系数学の良問プラチカ数学1A2B』のメリット・デメリットについて解説していきます。
メリット
- 難関大学の過去問の中から厳選された良問で演習できる
- 受験数学で取り扱うテーマが分野別に全て網羅されている
- 適度な難易度であるため過去問演習前の問題集として最適
デメリット
- 基礎力がないと解説を理解できないことがある
- やや難しい内容なので数学の基礎力がついていること前提となる
『文系数学の良問プラチカ数学1A2B』は、難関大学受験生にとっては定番の参考書。頻出の良問を全項目網羅できるのが大きな魅力です。
一方、難易度はやや高めなので、ある程度の数学基礎力がないと使いこなせないでしょう。そのため、まだ共通テストの数学で8割をとれない人は、先に『青チャート』などで基礎力を身につけることが重要です。
続いて、『理系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学III』のメリット・デメリットについて解説していきます。
メリット
- 難関大学の過去問の中から厳選された良問で演習ができる
- 項目別に出題されるのでピンポイントで演習できる
- 難関大受験に最適な難易度のため本番で実戦できる応用力がつく
デメリット
- 基礎力がないと解説を理解できないことがある
『理系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学III』は、難関大入試レベルの応用力を身につけられる参考書です。
解説を理解するには基礎力が必要であるため、「模試は解けるけど過去問演習になるとできない」という数学中級~上級レベルの人にオススメです。
『数学の良問プラチカ数学1A2Bシリーズがオススメな人
まず、『文系数学の良問プラチカ数学1A2B』は以下のような人にオススメです。
- 難関私立・国公立大学志望の文系で数学を使う人
- 中級・上級レベルの問題で実践力をつけたい人
- 応用問題の演習を積んでから、本格的な過去問演習に入りたい人
- 『青チャート』での基礎固めが完了している人
『文系数学の良問プラチカ数学1A2B』は、典型的な問題を解ける実力があり、応用問題対策としてもう一段階レベルアップしたい人にオススメです。
全国の大学入試問題の出題傾向と特徴が分析されているので、過去問演習に十分対応できる実力が身につきます。
続いて、『理系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学III』は以下のような人にオススメです。
- 難関私立・国公立大学志望の理系学生
- 基礎力はあるけど応用問題は苦手という人
- 応用問題の演習を積んでから本格的な過去問演習に入りたい人
『理系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学III』は、難関大を受験する理系学生が過去問演習前に取り組んでおきたい1冊です。
河合塾の定番の参考書なので、この1冊を完璧にしておけば、応用問題が出題されても解法が思いつくようになります。
『数学の良問プラチカ数学1A2B』シリーズの使い方
ここからは具体的な『数学の良問プラチカ数学1A2B』シリーズの使い方をチェックしていきましょう!どんなに良い教材でも正しい手順で使えなければ、効率的に勉強できません。
使い方は『文系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学III』で共通です。
基本的に以下のステップで活用しましょう。
- Step1.
- 時間を計って解く
- Step2.
- 解説を丁寧に読む
- Step3.
- 間違えた問題は解説を閉じてその場で解きなおす
- Step4.
- 間違えた問題にバツ印をつける(正解した問題のバツ印を消す)
Step1.時間を計って解く
問題集を解くときは必ず時間を計りましょう。実際の入試では制限時間があるため、ダラダラと問題は解けません。そのため、日頃から時間を意識して効率よく解く練習を繰り返しましょう。
時間については、入試を意識して「5問で100分」のようなテスト形式で進めるのも良いでしょう。テスト形式で行う場合は、単元をバラバラにして取り組むと実戦に近い形で演習できます。
また、復習する際にわかりやすいよう、必ず「どの問題を解いたのか?」は分かるようにしておきましょう。
Step2.解説を丁寧に読む
制限時間が来たら問題の解説を読みましょう。問題自体の解説はもちろん、補足部分にも重要なことが書かれているため、必ずチェックしましょう。
『数学の良問プラチカ』は、問題冊子に対して解説冊子のボリュームが大変多く、丁寧にまとめられています。解答のポイントが丁寧にまとめられているので、正しい解答ができているのかを確認できます。
Step3.間違えた問題は解説を閉じてその場で解きなおす
解説を読んだだけで終わりにしてはいけません。説明を理解したら解説を閉じて、間違えた問題をその場で解きなおしましょう。
答えだけではなく、途中の計算まで含めて考え方を理解できているか、必ずチェックします。途中の考え方まで理解しておくことで、入試で類似問題が出題されても対応できるでしょう。
Step4.間違えた問題にバツ印をつける(正解した問題のバツ印を消す)
最後にバツ印をつけて、次の周回に備えましょう。2周目以降はバツ印のついている問題だけに取り組めばOKです。
きちんと理解している問題には時間をかけすぎないことで、周回速度を上げられます。2周目で正解できた問題はバツを外しましょう。
全てのバツが外れるまで取り組めるのがベストですが、過去問演習の時期が来たらそちらを優先しましょう。
『数学の良問プラチカ数学1A2B』シリーズを使う際のペース配分
『数学の良問プラチカ数学1A2B』シリーズに取り組むペース配分は、どんな状況で使うかによって異なります。自分に合うものを選んで適切なペースで暗記していきましょう。
まだ受験まで時間がある高校1・2年生の場合、まずは『青チャート』などの基礎・基本の参考書を解くことを優先しましょう。高校1・2年生の段階で『良問プラチカ』まで進められれば非常に優秀です。プラチカに進む前に、基本的な問題に安定して解答できるようにしましょう。
取り組む余裕がある場合は、1週間に2回のペースで勉強すると、文系なら7ヶ月・理系なら10ヶ月で完了します。3ヶ月~半年程かかってもOKです
一方で、受験のもう一つの柱である英語についてきちんと勉強しましょう。英単語や文法に不安がある場合は、数学よりもそちらに時間を使ってください。
部活動で忙しくて時間が取れないという高校1・2年生の場合、まずは『青チャート』レベルを完成させてから『良問プラチカ』に進みましょう。1回の勉強時間を1時間にすると、文系なら4ヶ月・理系なら6ヶ月で完了します。
受験まで時間のない高校3年生の場合は、1回の勉強時間を4時間にして1日に8問解くと、文系なら1ヶ月・理系なら1ヶ月半で完了します。4問を1時間で解いた後、必ず復習まで済ませてから、次の4問を解くようにしましょう。
理系学生の場合は、科目ごとの配点や目標点数を参考にしながら、各科目にどれだけの時間を費やすか決めましょう。
確かに数学は入試における重要科目ですが、完成に時間がかかる科目でもあります。そのため、他の科目とのバランスも見ながら勉強することが大切です。
例えば、志望校で理科の配点が大きい場合、理科の勉強に多めに時間を割いたほうが総合的な点数が大きくなる可能性があります。『良問プラチカ』を進める場合でも、過去問演習の時間をしっかりとって進めるようにしましょう。
『数学の良問プラチカ数学1A2B』シリーズを使う際の注意点
『数学の良問プラチカ数学1A2B』シリーズを使う際は以下の点に注意しましょう。
- わからなかった問題は、2周目で必ず解けるように復習する
- 全くわからない問題は早めに解答を見て方法を学ぶ
- 2周目は2倍のスピードで解答できるよう練習する
- むずかしく感じても、ひとまず1周をやりきる
- 1問あたり15分~20分のペースで、最低2周以上はする
『数学の良問プラチカ』に取り組んでいる受験生は、基礎学力が身についていることが前提です。今までの勉強で固めた基礎力を使って解き切ってみましょう。
また、合格に近づくためには、過程も含めて間違えた問題を確実に理解することが必要です。まずは「きちんと復習をしながら」1周し、2周目で正解できるようにしましょう。終わる頃には数学の力はかなりつくはずです。
まとめ
最後にもう一度『数学の良問プラチカ数学1A2B』シリーズがオススメな人を確認しましょう。
『文系数学の良問プラチカ数学1A2B』は以下のような人にオススメです。
- 難関私立・国公立大学志望の文系で数学を使う人
- 中級・上級レベルの問題で実践力をつけたい人
- 応用問題の演習を積んでから、本格的な過去問演習に入りたい人
- 『青チャート』での基礎固めが完了している人
『理系数学の良問プラチカ数学1A2B』『理系数学の良問プラチカ数学III』は以下のような人にオススメです。
- 難関私立・国公立大学志望の理系学生
- 基礎力はあるものの、応用問題は苦手という人
- 応用問題の演習を積んでから、本格的な過去問演習に入りたい人
『数学の良問プラチカ数学』シリーズは、基礎固めが完了しており難関大を受験する人は、是非やっておきたい1冊です。適度に難しいレベルになっており、解説も丁寧で複数の解法が提示されています。
この1冊を完璧にしておけば、応用問題が出題されても解法が思いつくようになるでしょう。
今回紹介した方法を実戦すれば、本番で応用できる自信が身につきます。ぜひ実戦してみてください。
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば数学の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
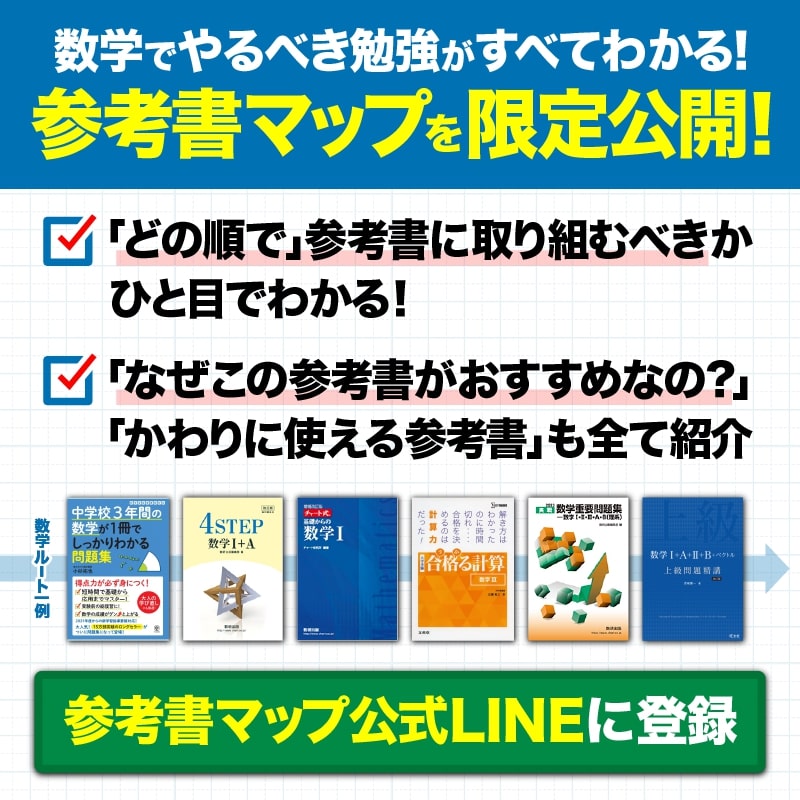
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る