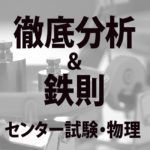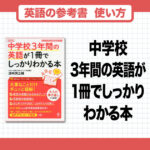「共通テストの物理ってセンターってどれくらい違うんだろう?」
「センターの過去問も共通テストの練習になるのかな?」
こんな疑問をお持ちではないでしょうか?
こちらの記事では、共通テストの物理と、従来のセンターの物理との違いを丁寧に解説していますので、これを見れば違いが全て分かります。
大問構成の違いは?【共通テスト物理】と【センター物理】の問題構成の違い
センター試験では大問5問構成で、最後の1問に関しては2つの大問から選択する形でした。
一方、共通テストでは大問4問構成で選択問題がなくなりました。そのため物理の後半の方で習う「原子」の単元も必ず勉強しなければならない形になっています。
配点の違いは?【共通テスト物理】と【センター物理】の得点配分の違い
配点も問題構成の変化に合わせて変化していて、センター試験では第4問までに85点、選択した大問が15点でしたが、2022共通テスト本試では以下のようになっています。
第1問 25点
第2問 30点
第3問 25点
第4問 20点
ただし、年度によって大問ごとの配点は多少変わります。
マーク形式で、試験時間が60分ということは変わりません。問題数自体もそれほど増えたわけではありません。
身近な現象を題材にした出題が特徴的ですが、これまでのセンター試験の延長線上にあるといって良いでしょう。

試験時間・解答形式の違いは?【共通テスト物理】と【センター物理】の違い
マーク形式で、試験時間が60分ということは変わりませんが、身近な現象からの出題が増え、場合によっては教科書には載っていないようなことも出題される可能性があります。
これに慣れていない場合には、時間内に解き終わるのが難しくなりました。
ただし、パッと見た感じが見たことのない図や実験だからと言って、習っていない範囲が必要になるということではありません。
教科書に載っている範囲内の情報で十分解くことのできる形式です。
解答形式は従来のものと変わりません。
共通テスト物理とセンター物理の【出題傾向】の違い

センター試験の頃と比べて問題の種類や問い方が大きく変わったわけではありませんが、共通テスト物理ならではの特徴が2つあります。
それは以下の通りです。
- 身近な現象に関する問題が出題される
- 表・実験データの読み取りが必要
それぞれ詳しく解説します!
問題集ではあまり見かけない身近な現象に関する問題が出題される!
共通テスト物理ではセンター試験では多くは見られなかった「身近な現象」からの出題があります。
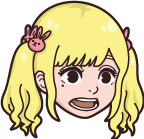
30年度試行調査~2022年共通テスト本試で出題された「身近な現象」をまとめるので具体的に見てみましょう。
- 宇宙船の軌跡
- 石けんの縞模
- アンテナの電波受信
- エレキギターの出力
- ダイヤモンドの光の分散
- 水銀蛍光灯の光る原理
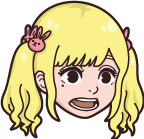
このように問題集では見かけない現象が出題されるのが共通テストの特徴です。
見たことがないからといって、諦める必要はありません。
よく問題を読めば、必ず問題集などでも頻繁に見かける公式や考え方を利用して解くことができるようになっていますから、特別難しいことを勉強する必要はありません。
単純に慣れが必要な出題と言えるでしょう。
表・実験データの読み取りが必要!
センター試験の頃からグラフの読み取りは頻出でしたが、見たことのないようなグラフや、表も共通テストでは出題される可能性が高いです。
特に実験データをまとめた表に関しては、なじみが薄いのではないでしょうか?
予想問題などをしっかり解き、慣れておくことが必要でしょう。
細かい設問の説明はこちらからどうぞ!
センター物理は共通テスト物理の練習になる?
共通テストの過去問は少ないので、演習不足を補うためにセンター物理を使うべきかどうか迷う方も多いと思います。
結論から言えば、十分練習として使えます。
ただし、センターでは大問の選択があるので、その分の違いは意識した上での練習と考えるのがよいでしょう。
また、2014年以前のものは指導要領が違うので少し注意が必要です。
より共通テストの形式に近い形で演習をしたい方は、センター過去問よりも「予想問題集」などを使うのがおすすめです。
こちらで解説していますので、ぜひ参考にしてください!

まとめ
この記事のまとめです。
共通テストとセンターの物理を比較すると、
- 大問構成に変化があり、全問必答の4問構成になった
- 身近な現象からの出題が増えた
- 実験をまとめた表やグラフの出題の可能性が高くなった
となります。
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば物理の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
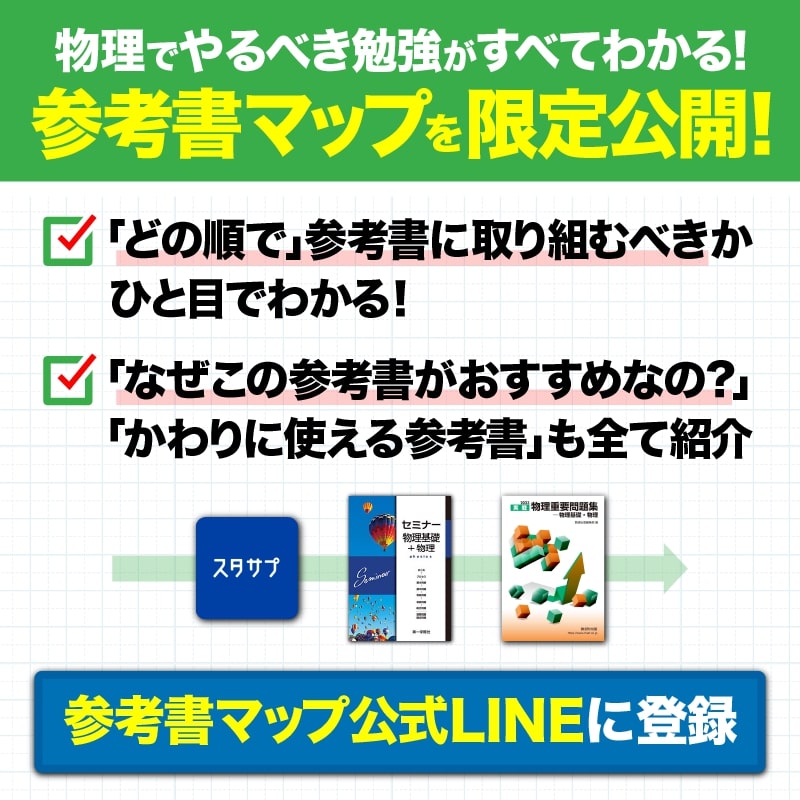
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト物理全体の対策を理解したい場合はこちらからご覧ください!