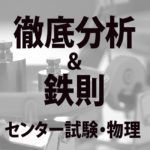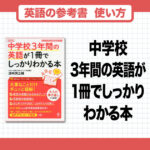「共通テストの物理が時間内に解き終わらない」
「一番得点が高くなる時間配分ってあるのかな?」
「解く順番とかって点数に関係してくる?」
このようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?
実はいくつかのポイントを押さえて解けば、解く順番や試験時間に悩むことなく、共通テストが解けるようになります。こちらの記事で全て解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
得点が高くなるための時間配分は?【共通テスト物理】

大問構成・問題数を把握すべし!知らずに時間配分は考えられない!?
共通テストの大問構成・問題数を理解したうえで時間配分については考えていかなければなりません。
2022共通テスト物理(60分)
第1問 25点
第2問 30点
第3問 25点
第4問 20点
全マーク数 25
これを理解した上で時間配分について考えていきましょう。
各大問最大13分を目安に【1マークあたり2分以内で余裕を持って解ける】
共通テストの物理は大問4問構成、試験時間は60分になっています。
大問1つあたりの配点は年度によって変わりますし、大問ごとのマーク数も変わってくるので、完璧な時間配分というのはありません。
大問4問構成ということはしばらく変わることがないと予想されるので、大問1問あたり最大13分を1つの目安にしておくといいでしょう。
13分×大問4つで52分となるので、このペースで解ければ最後に苦手で飛ばした問題に戻ったり、マークミスのチェックをしたりする余裕があるはずです。
また大問ごとに問題数の偏りがある場合もあるので、より汎用性が高い方法は1マークあたりの時間を決めておくことです。
マーク数は25個程度、多くとも30個以内になるはずなので、1マーク2分以内という風に考えておくと、余裕を持って最後まで解ききることができます。
試験が始まったら、最初に各大問のマーク数をチェックし、マークの数に2分間を掛け算して、大問ごとの目安の時間を出してからスタートすれば、問題数が多少変わる分には対応できます。
これまでマークの数が30を超えたのは29年度試行調査のみで、センター試験でもここ最近は20マーク少しくらいがマーク数の目安になっています。
こういった単純計算の結果を元に、得意不得意に合わせた時間配分の例を見てみましょう。

解く順番は?得意な所から解いていこう!わからない問題は即座に飛ばそう!
次にどの大問から解くべきか、その順番について書いておきましょう。

解く順番はどの順番でも構いません。
基本的にはマークミスを避けるために前から解いていくことがおすすめです。
苦手な単元がある場合は、その部分は飛ばして戻って来るという風に決めておいてもいいでしょう。
上に書いたように1問あたりにかけられる時間は2分程度ですから、悩まず飛ばす癖を付けておくことが重要です。
どの順番で解いても構いませんが、解く順番は本番までに決めておきましょう。
本番も「どの順番で解こうかな」と迷っていたのでは、迷っている時間がもったいないですから、解く順番は本番までに過去問や予想問題で練習して決めておくべきです。
【悩む前にすぐ飛ばす】ことが解く順番よりも重要!?
時間が足りないということに悩んでいる受験生はある程度は共通テストレベルの問題を解けるようになってきているという状態です。
解けるようになってきているからこそ、「どうやって解くんだっけ?」と解けない問題に対して「悩む時間」が多くなってしまいがちです。
共通テストの物理は試験の性質上、テンポ良く解く必要がありますし、そうでないと高得点は取れません。
少しでも悩むようなら飛ばして次の問題に進む癖を付けておきましょう。


まとめ
この記事のまとめです。
大問あたり最大13分を意識するか、1マークあたり2分間以内で試験開始直後に計算をするかがおすすめの方法です。
少しでも悩んだらすぐに次の問題に移る癖をつけるため、過去問や予想問題で演習をしましょう。
また、どの順番で解いても構わないけど、順番は決めてから本番に臨むようにしてください!
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば物理の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
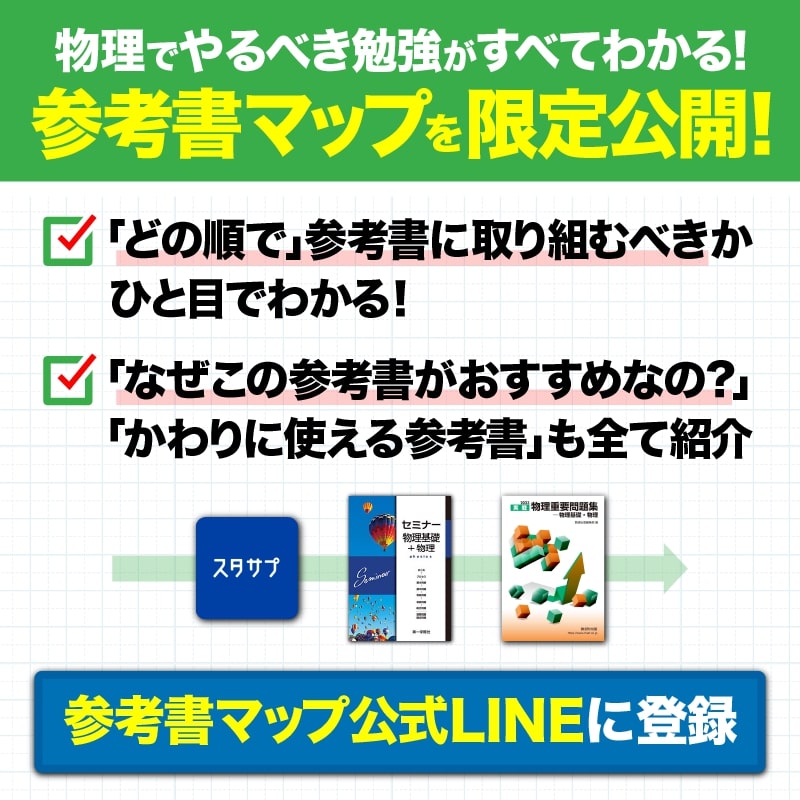
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト物理全体の対策を理解したい場合はこちらからご覧ください!