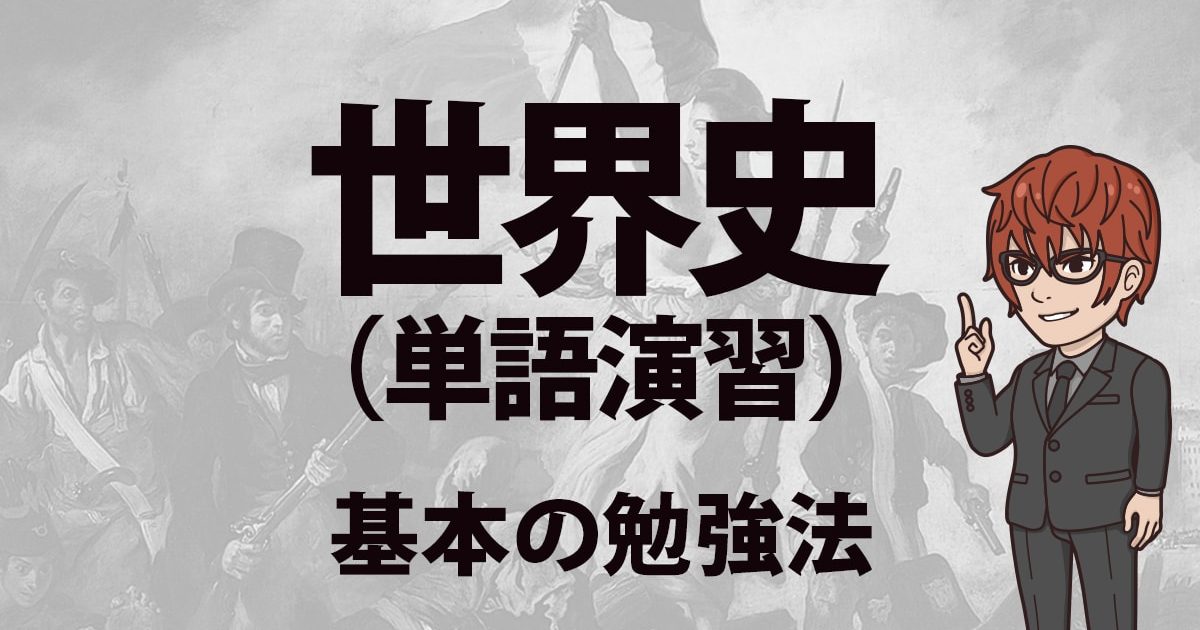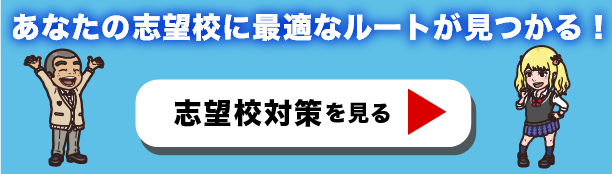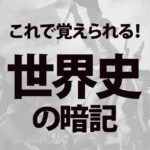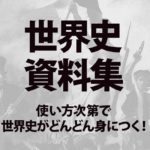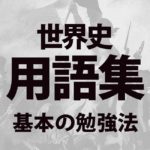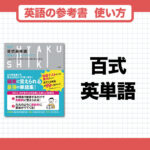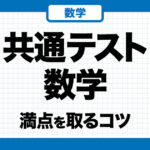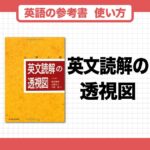突然ですが、「定期テストの世界史はできるのに、模試や過去問では解けない…。」という人、いませんか?もしあてはまるならば、この記事を読むことを強くおすすめします。
世界史の模試や入試では、教科書や一問一答を使った勉強だけでは点数が取れません。なぜなら、それでは「問題を解く」練習をしてないから。この記事では、問題を解く「演習」の必要性と、中でも私立大学頻出の記号問題を中心に、演習のやり方について解説します。これを読めば得点力が上がること間違いなしです。
世界史入試で得点アップする秘訣は「問題演習」をすること!





皆さんは、世界史の勉強でこんな状態になっていませんか?
- 一問一答を何十周もしたのに、過去問の点数が上がらない
- 初めて受けた世界史の模試で思ったより点が取れなかった
- 世界史得意なはずなのに、過去問になるとよく間違う
1つでも当てはまる人は、せっかく覚えた知識を入試で活かせず、点数を取りこぼしてしまっているかもしれません。
そんな状態から脱却するためには、実際の入試と同じような問題の「演習」がポイントになります。
なぜ教科書、一問一答だけじゃダメなの?
一問一答で単語を覚えたり、教科書や映像授業で流れの理解をしたりしている人は、理解した知識をきちんと覚えられている、という点ではまったく間違っていません。
しかし、一問一答ばかり何周もしていたり、いつまでも教科書を眺めていたりするばかりで、これから紹介する「演習」をやっていなければ、試験本番で得点が取れないかもしれません。

なぜかというと、入試本番で出題されるのは「覚えた知識や理解した内容を正確に引き出して解く力」がないと解けない問題がほとんどだからです。
例えば、こんな問題があります。
【選択式問題の例】
“下線部fに該当する人物の一人に蔣介石がいる。蒋介石に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。”(イ~二の中から誤っている記述を選択)(2014年度 早稲田大学 政治経済学部 「世界史」)
【地図問題の例】
“下線部⑤に関して、中世ヨーロッパにおいて東方貿易に従事し、香辛料の取引で栄えた都市の名と、その位置を示す次の地図中のaまたはbとの組み合わせとして正しいものを、次の①~④のなかから一つ選べ”(平成29年度 センター試験「世界史B 」)
【記述式の問題の例】
“下線部Dに関連して、ビザンツ帝国の衰亡とイタリア・ルネサンスとの関係について、90字以内で述べなさい。”(2009年度 慶応義塾大学 経済学部「世界史」)
本番ではこのように、複数の「時代」「地域」について、複数の「形式」(穴埋め、選択式、記述式など)で出題されます。

一問一答はあくまで「単語を覚える」ための問題集ですから、こういった「歴史の流れと組み合わせる問題」や「正誤を問う問題」は出題されません。あくまで「聞かれた人物や出来事を答える」だけで、これは定期テストの問題などでも同じことがいえます。
実際の入試では、複数の地域・時代にまたがって出題されることで、似たような単語や歴史の流れが混ざって混乱してしまったり、同じ時代の別の地域の出来事がすぐに思い出せなかったりということが起こってしまいます。
とくに「正しいものを選びなさい」「誤っているものを選びなさい」のような正誤問題では、当然のように問題文で間違った内容が書かれているため、慣れていないと覚えている単語でも「あれ、そうだったかも……」と思ってしまうことがあります。
- 単語とその説明は覚えてるんだけど、比べられると混乱してしまう
- 時代順を聞かれると正確に答えられない
- 地図上で場所を把握していないので、まったく手が出ない
こういった「単語や知識としては知っているのに、問題に正解できない…」という状態をなくすために必要なのが、実際の入試形式に合わせた「演習」なんです。
演習って何?
ここでいう「演習」は、すでに書いた通り実際の入試で出題されるような問題と同じ形式のものを解くことです。
「問題を解くなら一問一答と変わらないんじゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、そもそも一問一答と演習とでは目的が違います。
一問一答は、「知識を覚える」ことが目的です。そのため基本的に「誰が(何が)、何を、いつ、どこで、どのように(5W1Hですね)、したのか(起こったのか)」のどれかが空白になっていて、それを問う穴埋め形式の問題として聞かれます。
演習の目的は、「入試問題を解けるようになること」です。
例えば、演習問題だと、
(例)~の中から不適切なものを選びなさい。
(例)下線部が意味するものを答えなさい。
(例)~の中から不適切なものを選びなさい。
(例)下線部が意味するものを答えなさい。
など、単純な穴埋めではない問題を多数解くことになります。
穴埋め問題であっても、1文だけ聞かれるのではなく、歴史の流れやテーマについて説明した長文の中に空白がある形式になっています。
純粋に単語だけを覚えればいい「一問一答」と異なり、単語の意味と歴史の流れ、他の地域との比較や地理上の場所などもすべて絡めて答えを導き出していくのが、実際の入試で問われることであり、「演習」を通じて身につけたいことです。
「一問一答」は知識を「インプット」「定着」させるためにすること、「演習」は知識を「アウトプット」する練習で行うもの、と理解しておきましょう。

世界史の「記号問題」「選択肢問題」を解けるようになる演習法

ここからは具体的に、世界史の入試や模試で点数アップするための「問題演習」のやり方と、おすすめの参考書についてお伝えしていきます。
ここでは私立大学でよく出題される「記号問題」「選択肢問題」を中心に解説していくので、論述問題が出題される国公立大学を受験する人はこちらの記事を参考にしてください。
世界史の問題演習ステップ
- 必要なもの
- 現状のレベルに合わせた問題集
- いつからやるべきか
- 遅くとも高3・8月から
- どれくらいかかるか
- 1冊あたり100時間程度
世界史の問題演習は、通史を一通りインプットして、『詳説世界史ノート』などで単語を覚えたあとに取り組むようにしましょう。
高3の夏休み前にはインプットを終わらせて、問題演習を夏休みにスタートできるペースが標準ですが、早慶志望ならもっと前倒し、逆に共通テストでしか使わない場合は多少遅れてもかまいません。
今回使う問題集は『実力をつける世界史100題』。
ここ数年で私大世界史の難易度は上がっており、対応するためには頻出のテーマを網羅した実戦形式の問題集で演習したいところです。
『実力をつける世界史100題』は、どの大学を受験する場合でも活用できますが、状況に応じて別の参考書に差し替えたり、取り組む順番を変えたりしてください。
- 早慶上智・MARCH・関関同立を受験する
- 『実力をつける世界史100題』のあとに『標準問題精講』に取り組む
- 日東駒専レベル以下の入試が中心
- 『全レベル問題集世界史』の1・2を先に取り組む
- 共通テストでのみ世界史を使う
- 『実力をつける世界史100題』は使わずに、共通テスト向けの教材を使う
以下、『実力をつける世界史100題』に沿って使い方を説明していきますが、どの問題集を使う場合でも同じ使い方を意識してください。
- Step1
- 問題を解く
- Step2
- 間違えた問題には印をつける
- Step3
- 正解していた箇所も含めて解説をすべて読む
- Step4
- 解説を読んで知らなかった単語は覚え直し、該当箇所の教科書や資料集も確認する
それぞれのステップについて詳しく解説していきましょう。
Step1 問題を解く
さっそく問題を解いていきましょう。2周目以降にも取り組めるように、問題集には直接答えを書き込まず、必ずノートに解きましょう。
ここで注意したいのは、答えが分からなくてもその場で「調べない」こと。

演習の目的は「問題を解けるようになること」なので、「解けない問題を洗い出して、解けるようにする」という作業が重要になります。教科書や資料集で答えを調べてしまうと、自分が「どこまで覚えていて、どこまで覚えていないのか」があやふやになってしまいます。
正解・不正解に関わらずあとでまとめて調べる時間を取るので、ここでは「自分が持っている知識で問題を解けるか」確認するだけにしましょう。
Step2 間違えた問題には印をつける
問題が解き終わったら、答え合わせをしましょう。間違えた問題に印をつけておくことで、2周め以降に重点的に解くべき問題がわかります。
このとき、「たまたま正解していた」という問題にも印を必ずつけるようにしてください。少し厳し目に印をつける意識でOKです。
Step3 正解していた箇所も含めて解説をすべて読む
答え合わせの際は、解説をしっかり読んで「なぜその問題を間違えたのか」を分析しましょう。
間違えた理由は、大きく次の3つに分けられるはずです。
- そもそもその用語を知らなかった
- 用語は見たことあるけれど忘れていた
- 用語は覚えていたけど、流れや理由、場所など問題に関わることを理解していなかった
多くの場合は3つ目の「用語自体は知っているけど、問題で問われている出来事の順番などを知らなかった」にあてはまるはずです。「用語は分かっていたのに、問題が解けなかった」という場合は、その単語の「理解」が足りない、ということ。
こうした場合は特に解説をしっかり読み込んで、あやふやな部分をなくしましょう。
今回紹介している『実力をつける世界史100題』には、背景が複雑な単語の詳しい解説が掲載されているだけでなく、図表や地図など理解を助ける工夫がたくさんあります。
ここで重要なのが、正解していた問題の解説もきちんと読み込むことです。

正解していた問題の解説も読むことで、「たまたま正解していた問題」を見逃すことが減ります。自己判断だけだと甘くなってしまいがちなので、すべての解説を読むことで「この問題は理解していたと思っていたけど、たまたまあっていただけだったな」ということを判断できます。
また、正解していた問題の解説の中にも「知らなかった背景や理由」が書いてあることがあります。せっかく充実した解説がついているので、解いた問題と紐づけながら周辺の知識や背景情報も押さえておくことで、次に似た問題や同じ時代の問題が出たときに正解しやすくなります。

Step4 解説を読んで知らなかった単語は覚え直し、該当箇所の教科書や資料集も確認する
解説を読み込んでいくうちに、知らなかった単語や忘れていた内容が出てくるはずなので、間違えた問題や解説で出てきた知らない単語について教科書や資料集でも調べて、その場で必ず覚えるようにしてください。
せっかく時間をかけて解説を読み込んでも、単語を覚えていなければ意味がありません。「あとで覚えよう!」と思っていても忘れてしまいがちなので、その場で必ず覚えるようにしましょう。
まとめ
最後にもう一度、演習のポイントを復習しましょう。
- 演習で点数UP
- 教科書、一問一答だけじゃ入試問題は解けるようにならない。演習で「問題をとけるようになろう」
- 解説を読み込むことがポイント
- 演習では「なぜ解けなかったか」を理解すること、「解説を読みこむ」ことが大事

みなさんも、しっかり演習をして周りのライバルに差をつけましょう。
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば世界史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
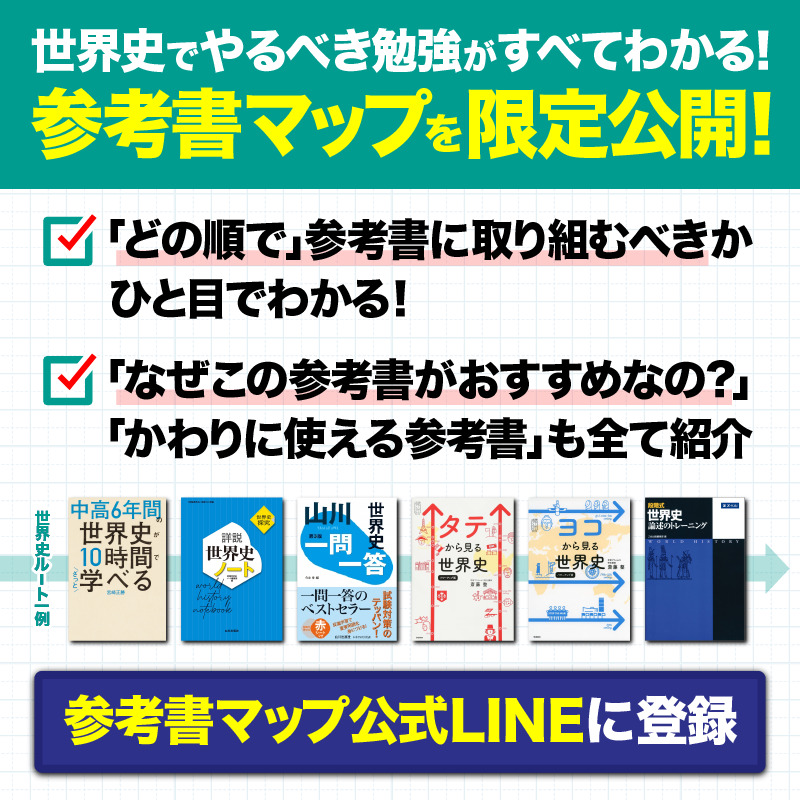
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る