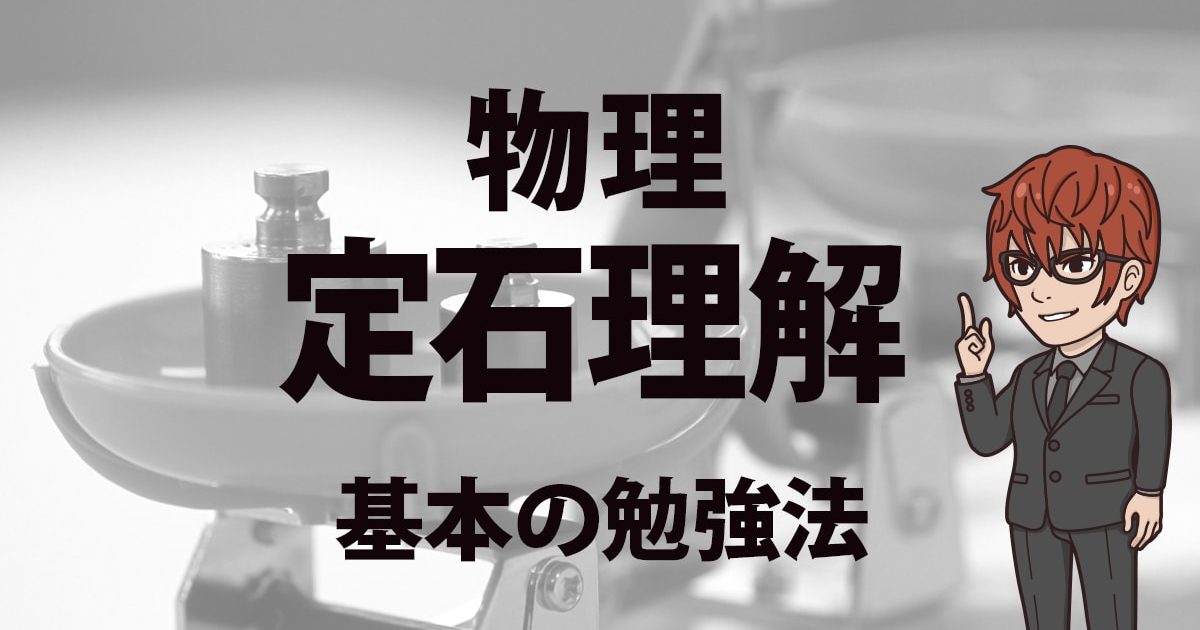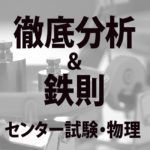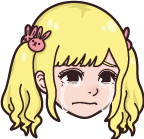

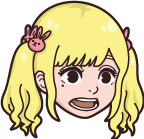

物理は、公式の意味や導出方法を理解しただけでは、問題を解けるようになりません。テストや模試で高得点を取るには、問題演習に取り組んで「具体的な解き方(=定石)」を理解し、暗記することが必要です。
今回は、定石理解・暗記の勉強法について解説します!
高校物理の勉強の流れについて!物理も暗記は必要!
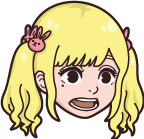

物理では数学と同じように公式などがあるため、まずはそれらを暗記することが必要です。この暗記を踏まえた、物理の勉強の流れは以下の通りです。
教科書レベルの内容理解
↓
定石理解・暗記
↓
入試レベル問題演習
↓
過去問演習
まずは学校の授業や映像授業などを活用して、教科書レベルの内容を理解しましょう。この時点で、公式や基本的な実験内容を理解することが大切です。ここで理解した知識を「問題でどう使うのか?」という点を理解し暗記することが、定石理解・暗記の勉強内容です。
問題演習を通してこの定石理解・暗記を行えば、テストや模試で高得点を取れるようになります!
MARCH・関関同立以上の難関大学を目指す場合は、定石理解・暗記の後に入試レベルの問題集で演習してから、過去問演習で仕上げをしましょう。
物理では典型問題=定石の理解と暗記が重要!

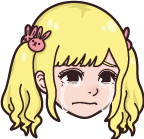

物理では、数学と同じくたくさんの公式が出てきます。しかし、実際のテストや模試で「公式に数字を少し当てはめれば解ける」という問題が出題されることは、ほとんどありません。

テストや模試では、公式を使って解く典型的な問題(=定石)が存在します。その定石を理解し暗記することで、テストや模試で得点できるようになるのです。
また次のような勉強では、定石を理解して暗記することはできません。
- 教科書を読むだけ
- 授業を聞くだけ
- 問題集の答えを読むだけ
実際に自分の手で問題を解いて理解し暗記をしなければ、定石は身に付きません。
それでは、具体的に「どの問題集を使って・どう勉強すれば良いのか?」を紹介します!

高校物理の定石理解・暗記におすすめの問題集と勉強法
ここからは、物理の定石理解・暗記の勉強におすすめの問題集と勉強法を紹介します!
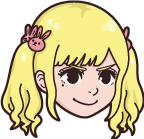
物理の定石理解・暗記におすすめの問題集
物理の定石理解・暗記でおすすめの問題集は、学校で配られる『セミナー』『リードα』『ニューグローバル』などです。分厚いため終わらせるのが大変に感じるかもしれませんが、定石はある程度の問題数を解かないと身に付かないため、取り組んでおきましょう。
もし持っていないのであれば、個人で購入できる『エクセル物理』を使いましょう。
どうしても「分厚い問題集が苦手」という場合は、『物理のエッセンス』『良問の風』を使って演習してもOKです。この2冊は薄いため、比較的楽に進められます。
しかしその分、2冊とも演習量は『セミナー』『リードα』などより若干少ないため注意しましょう。
各問題集の具体的な使い方については、それぞれ以下の記事で解説しています!
セミナー
リードα
ニューグローバル
エクセル物理
物理のエッセンス
良問の風
具体的な物理の定石理解・暗記の勉強法
具体的な物理の定石理解・暗記の勉強法は以下の通りです!
- ステップ1
- 時間を計りながら問題を解く
- ステップ2
- 解説を丁寧に読む
- ステップ3
- 間違えた問題を解き直す
- ステップ4
- 間違えた問題に印をつける
- ステップ5
- ステップ1.に戻り2周目
まずは時間を計りながら解きましょう。1周目は、2〜3分手が止まったらすぐ解説を読んでもOKです。物理は、そもそもの知識を暗記していないと、わからない部分を何分考えても解けません。これも数学と同じです。
解けそうな場合でも、あまり粘りすぎないでください。目安として「基本問題は大問1つあたり5分・発展問題は15分以内」で進めましょう。
解説は、正解した問題もしっかり読みましょう。正解していても「実は根拠があやふやだった」ということもあり得ます。計算も読み流さないようにしましょう。
次に、解説を閉じて間違えた問題を解き直します。解説を読み飛ばさずしっかり理解できていれば、計算まできちんと解けて正解できるはずです。また、解説に出ている図を自力で描けるようにしておきましょう。
そして、間違えた問題には印をつけておき、2周目に取り組みましょう。「2周目は1周目に間違えた問題だけ」「3周目は2周目に間違えた問題だけ」というように、少しずつ問題数を減らすことが大切です。

物理の問題演習の注意点
物理の定石理解・暗記の問題演習に取り組む際は、以下の点に注意しましょう。
- 図をサボらずに描こう
- ちゃんと自力で計算しよう
- 基本問題から徐々にレベルアップしよう
- 周回ごとに問題数を減らそう
図をサボらずに描こう
物理の勉強ではサボらずに図を描くことが大切です。

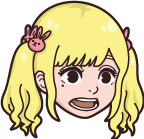
物理が苦手な人のほとんどは、図を描くことをサボっています。解答に掲載されている図は、全て自力で描けるようにしておきましょう。
実際の入試では、大問1つあたり1つ程度しか図がつけられていません。そのため、問題を解く中で何度も図を描き直さないと、本番の入試で必要な式をイメージできないこともよくあります。物理の問題を正確に早く解ける人ほど、何度も図を描き直しているため、普段から慣れておきましょう。
ちゃんと自力で計算しよう
物理で「立式までできれば解けたも同然」なのは間違いありません。しかしそれでも計算は自力で行いましょう。
例えば、「数学で出てくる簡単な2次方程式の「解の公式」が物理で出てきたら使えない」ということは本当によくあります。数学ほどキレイに計算が進まないこともありますが、コツコツ計算しないと計算力は身に付きません。
基本問題から徐々にレベルアップしよう
『セミナー』などの問題集は、問題数が多いため途中で挫折しがちです。そのため、いきなり全部の問題を解く必要はありません。
- 1周目:基本例題&問題のみ
- 2周目:1周目で間違えた問題+発展例題&問題
- 3周目:2周目で間違えた問題+総合問題
というように、周回ごとに少しずつレベルアップしていきましょう。最初から発展問題に取り組むと、解けなくて挫折します。
ちなみに、物理や化学の発展問題1周目は「半分以上解答を読んでいるだけ」という状態になることもよくあります。それでも諦めず、次の周回で必ず解けるようになることを目指して勉強しましょう。
周回ごとに問題数を減らそう
周回ごとに問題数を減らすことも大切です。
前の周回で正解した問題を、もう一度解いてもあまり意味がありません。2周目以降はわからなかった問題だけにフォーカスして、少しでも取り組む時間を短くしながら前に進んでいきましょう!
まとめ
物理の勉強では、公式の意味や導出方法を理解したうえで問題演習に取り組み、典型問題の解き方(=定石)を暗記することが重要です。定石を理解するためには「教科書を読むだけ・授業を聞くだけ・問題集の答えを読むだけ」という勉強を避けて、何度も問題集に取り組みましょう!
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば物理の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
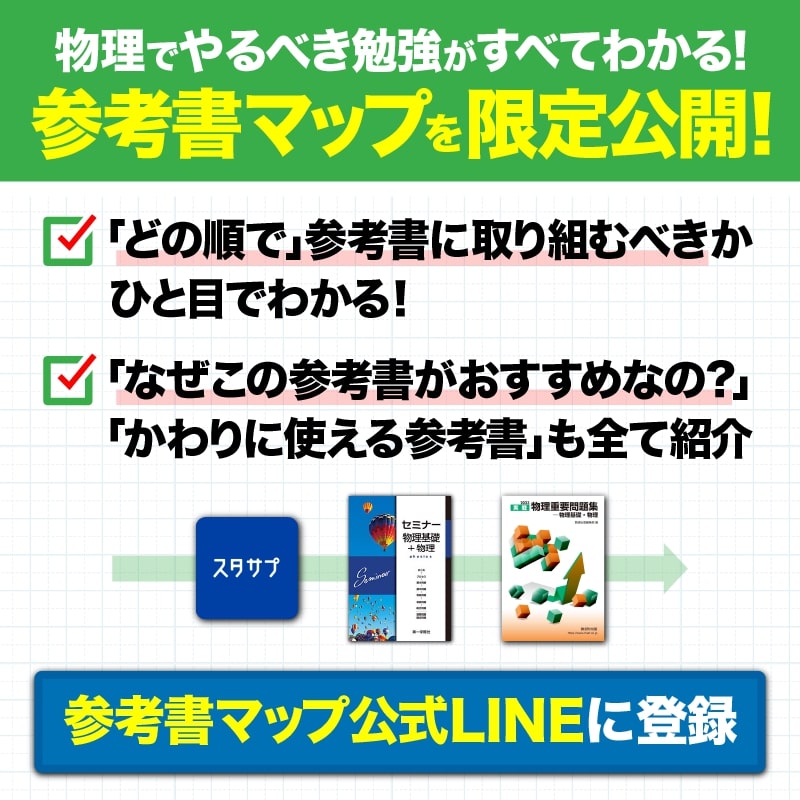
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る