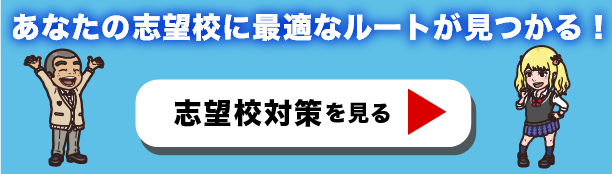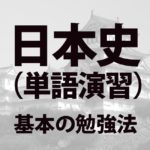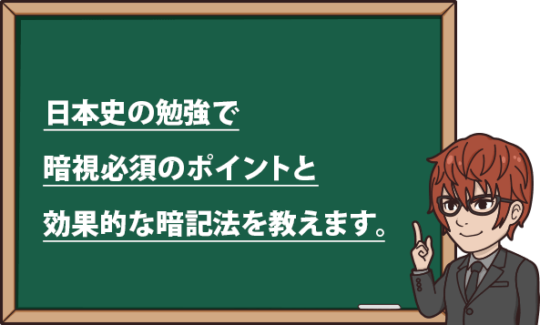
日本史の勉強で欠かせないのが暗記。しかし、「全然覚えられない」「どうやって覚えたら良いのかわからない」なんて悩んでいる人は多いと思います。
この記事ではそんな受験生の悩みを解決するために、日本史暗記のコツについてお伝えします。


日本史の勉強で主に暗記すべきことは3つ!

暗記の勉強法をチェックする前に、まず日本史で「覚えなければいけないこと」を確認しましょう!
暗記すべき項目の内容によって、「覚えられない原因や解決策は異なります。なのでまずは、日本史で覚えなければいけないことを今一度認識しましょう。
- 用語
- 用語の内容
- 年号
①用語
「足利義政」や「神皇正統記」などの用語が覚えられないパターンです。「言葉はわかるんだけど漢字は書けない」「この将軍は何代だっけ?」といったものも含みます。

②用語の内容
例えば、「勘合貿易について説明せよ」といった問題が出題された際に、あなたはすぐ答えられますか?

マルオ君のように「単語は見たことあるんだけど」と言って答えられないパターンです。用語を見たことはあっても、内容の詳細までは覚えきれていない状態です。
③年号
年号の暗記に苦しんでいる人は、意外と多いのではないでしょうか?
共通テスト(あるいはセンター試験)などでは、以下のように「出来事が起こった順に並び替えよ」という問題が出題されます。
問4 下線部©に関して述べた次の文(a)〜(c)について、古いものから年代順に正しく配列したものを、下の①〜⑥のうちから一つ選べ。
(a) 造都を主導していた藤原種継が暗殺され、早良親王が首謀者として処罰された。
(b) 三筆の一人として知られる橘逸勢が謀反を企てたとして流罪になった。
(c) 政権を批判して九州で反乱を起こした藤原広嗣が敗死した。① (a)—(b)—(c)
② (a)—(c)—(b)
③ (b)—(a)—(c)
④ (b)—(c)—(a)
⑤ (c)—(a)—(b)
⑥ (c)—(b)—(a)(平成29年度 センター試験「日本史B」一部改)
このように「年号を暗記できているかどうか?」という点を問われる問題は日本史で頻出のため、年号暗記が必須です。
以上の3つが、日本史を勉強する上で暗記すべき必須事項です。
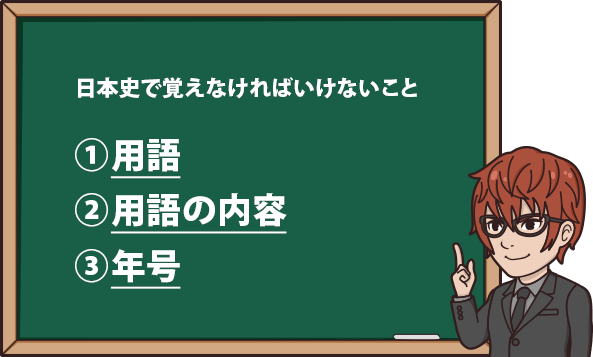
それではここから、各項目に合わせた暗記法を紹介していきます。
これから紹介する暗記法を駆使すれば、日本史で覚えなければいけないことのほとんどすべてに対応できます!

日本史の暗記法:用語&用語の勉強について

はじめに「①用語」「②用語の内容」の暗記法から解説していきましょう。
まず「①用語」そのものが覚えられない場合、考えられる理由は以下の2つです。
- 1.用語を覚える作業を怠っている
- 2.用語「だけ」を覚えようとしている
1.用語を覚える作業を怠っている
用語を勉強する中で、一問一答をやらなかったり、教科書を読んだだけで暗記しようとしたりする人も多いです。しかし基本的に、日本史の内容は軽く目を通したくらいで暗記できるものではありません。
人によって定着度は変わりますが、一問一答に3〜4周くらい取り組むなどしてもっと積極的に暗記することで、日本史の用語は定着します。
2.用語「だけ」を覚えようとしている
用語の意味や内容を全く意識せず、ひたすらその用語だけを丸暗記しようとしても、日本史の内容は頭に入ってきません。
しかも、日本史の用語集に掲載されている用語は、約6,000語と数が多いです。
そのため、暗記が得意な人でも日本史の用語をすべて丸暗記するのはかなり難しいでしょう。暗記が苦手な人ならなおさらです。
この「用語だけを丸暗記しようとする」という理由は、「②用語の内容」が覚えられない理由と同じです。

日本史を丸暗記せず勉強するために効果的なのが、「ストーリーと関連付ける暗記法」です。
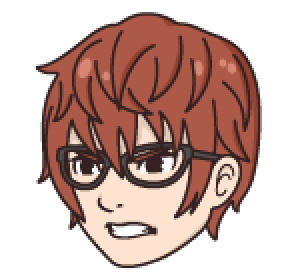

例えば、明治時代の「自由民権運動」の場合、事件や法律の名前はたくさん出てきます。しかし「なぜ起こったのか」「なぜ法律が出されたのか」という理由まで理解した方が覚えやすいです。

そう思うかもしれませんが、実はストーリーで覚えた方がたくさん暗記できます。
ここでXという用語を覚えるとして、「A.丸暗記する方法」と「B.ストーリーと関連付けて覚える方法」で比較してみましょう。
A.丸暗記する方法の場合
Xってなんで起こったんだろ?わかんないけど、とりあえず覚えておこう!
B.ストーリーと関連付けて覚える方法
そもそもXっていうのはYの影響なのか。そしてXのせいでZまで起こったのか。
このように、Bの覚え方は他の出来事と関連させながら覚えようとしているため、「Xってなんなのか?」という用語の内容まで理解しやすいです。
理解が深まれば、暗記もスムーズにできますよね。また、背景を関連付けることで、XだけでなくYやZまで覚えられるので、より効率的です。
「①用語」「②用語の内容」が覚えられない人は、以下のステップで背景と関連づけながら勉強しましょう。
- Step1.
- 知識をインプットして理解する
- Step2.
- 繰り返し問題を解いてインプットした知識を定着させる
- Step3.
- 知識を活用して入試に合わせた問題を解く
Step1.知識をインプットして理解する
まずはインプットをしましょう。ここでは「通史」を理解していきます。「Xはなぜ起こったのか」というように、歴史の流れを頭に入れていきましょう。
インプットする際は、単語ひとつひとつを別個で覚えようとせず、単語同士の関連性を意識して一本の線を作るイメージで勉強しましょう。
インプットの段階から単語を覚えようとせずに、まずは「理解する」ということが大切です。
基礎事項のインプットにはスタディサプリを活用するのもよいでしょう。多くの映像授業の中から自分のレベルにマッチしたものを選んで勉強できます。
具体的な勉強の仕方については、以下の記事を参照してください。
step2.繰り返し問題を解いてインプットした知識を定着させる
次は定着の段階に移りましょう。定着させる際は「穴埋めノート」を使って、step1で関連付けて理解した知識を覚えていきましょう。
インプットを行ったらすぐに穴埋めノートでの勉強に移って復習するのが理想です。インプットした直後に取り組むことで、単語を歴史の流れの中で理解しやすくなります。
穴埋めノートとしては『詳説日本史ノート』がオススメです。
穴埋めノートで暗記できたら、『日本史一問一答』に切り替えて勉強するとよいでしょう。
穴埋めノートの使い方については以下の2つの記事をご覧ください!
step3.知識を活用して入試に合わせた問題を解く
最後のステップはアウトプットです。アウトプットでは、定着させた知識を「引き出す」訓練をしていきます。
この段階では共通テスト(センター試験)過去問などの問題集を解きましょう。
国公立志望なら『段階式日本史論述トレーニング』などで論述対策にも取り組みます。
私立志望なら、選択肢式の問題に対応できるようにするため『日本史B一問一答』と並行して『実力をつける日本史100題』などを進めるとよいでしょう。
演習する際も、単語の背景のストーリーと関連づけて「なぜその出来事が起こったのか?」ということを意識しながら進めていきましょう。

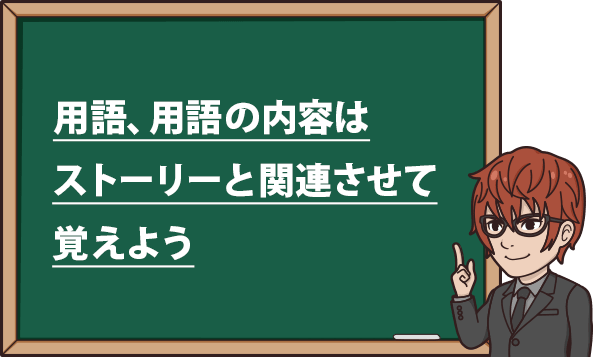

日本史の暗記法:年号の勉強について
「③年号」が覚えられない原因も、先ほどの用語と同じく、年号だけを覚えようとしているからです。例えば「〜年に〜が起こった」だけでは、やはり覚えられません。
「教科書」や「学校の授業」でしっかり勉強していれば、その出来事が起こった順番や流れがわかるはずです。
流れを理解しているだけで解ける問題もありますが、年号そのものを問われる問題や、年号を暗記していないと答えにたどり着けない問題もあります。
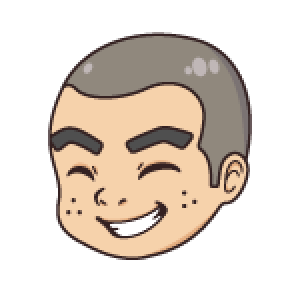
流れとセットで年号まで暗記することが理想ですが、どうしても覚えられないという人は「語呂合わせ」で覚えましょう!
例えば「794(なくよ)ウグイス平安京」などが有名ですよね。
年号など、単調なものの暗記には語呂合わせがぴったりです。リズムに乗せて頭に定着させましょう。
また、語呂合わせは、教科書やノートの年号が書いてあるところに書き込んでおくのがオススメです。こうすることで、通史の復習をするときに年号も合わせて暗記できます。
年号の語呂合わせの参考書としてオススメなのが『マンガとゴロで100%丸暗記 高校日本史年代』です。
この問題集には、イラストや簡単な解説とともに、時代ごとでたくさんの語呂合わせが紹介されています。
解説まで読めば、「その年号に起こった出来事がどんな出来事だったのか」に至るまでを丁寧に確認できます。
ただ、一番重要なのは「流れを理解する」というです。あくまでも語呂合わせは、「流れの中で年号を覚えるときに使うもの」という認識は持っておきましょう。

日本史の勉強で感じがちな「暗記に対する不安」に回答します!
ここからは日本史の勉強をする上で抱えがちな、暗記に関する不安点について回答します!
Q:具体的にどこからどこまでを暗記すればよいですか?
「どこまで暗記すべきか?」については、自分の志望校レベルによって変わります。大体の目安をまとめたのでチェックしておきましょう。
- 早慶レベル
- 一問一答や早慶レベルの問題集に載っている単語
- 難関国公立、MARCHレベル
- 教科書に出てくる単語
- 上記以外の大学
- 教科書の太字
もちろん、これはあくまで目安なので、実際に過去問を見てどの都度必要な暗記量を確認しましょう。
志望校で覚えるべき単語数は変わる!
Q:暗記におすすめの時間帯ってありますか?
正直、時間帯はあまり関係ありません。
確かに「朝」や「寝る直前」のほうが暗記しやすいとよく言われますが、あくまでも目安程度でしかないため、気にしすぎる必要はないでしょう。
暗記の際は、時間帯よりも「どれくらい暗記の時間をとれているか」という基準で考えましょう。しっかり時間をとって勉強していれば、時間帯は関係なく暗記できます。
暗記は「いつやるか」よりも「どれくらいできているか」を意識しよう

Q:漢字が書けない単語はどうやって覚えますか?
漢字が書けない用語については、とにかく書いて覚えましょう。「漢字ドリル」を使って、書いて覚えたことがある人も多いと思いますが、それと同じようなイメージです。
書いて覚えたほうが、ただ単に読んだり一問一答を眺めたりするよりも効果的です。
漢字は何度も書いて覚えよう!!
まとめ
日本史の勉強で必ず押さえるべき点は以下の3つです。
- 用語
- 用語の内容
- 年号
用語や用語の内容については、単体で覚えるのではなく、背景知識などのストーリーと関連づけて覚えましょう。ストーリーとして関連づけることで、複数の観点から効率的に知識を暗記できます。
年号については語呂合わせで定着させましょう。語呂合わせにすることで、リズムに乗って効率よく覚えられます。
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば日本史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
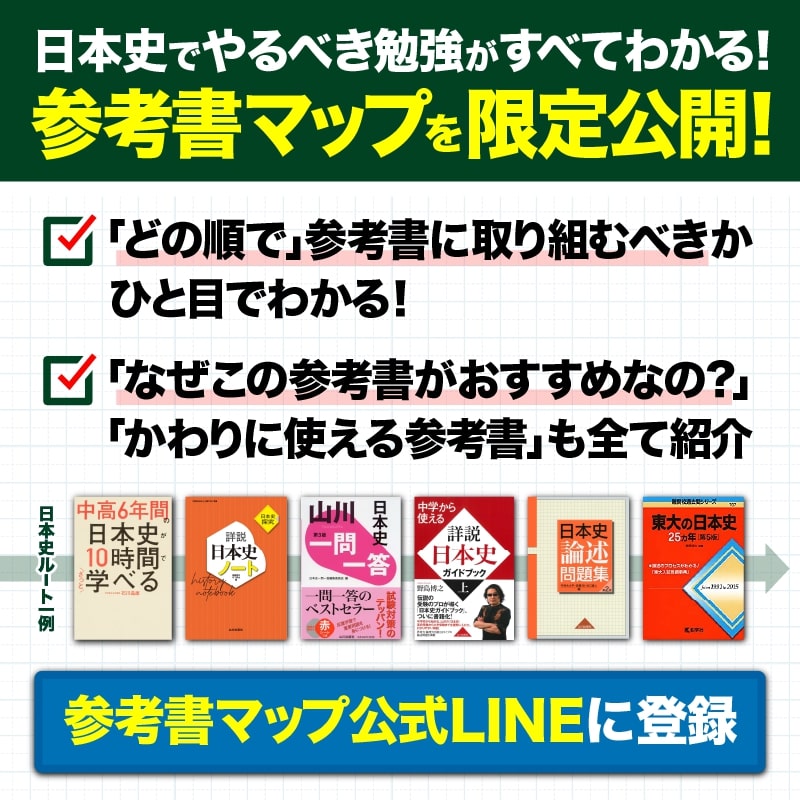
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る日本史の勉強にオススメの問題集やアプリについては、以下の記事でも解説しています!