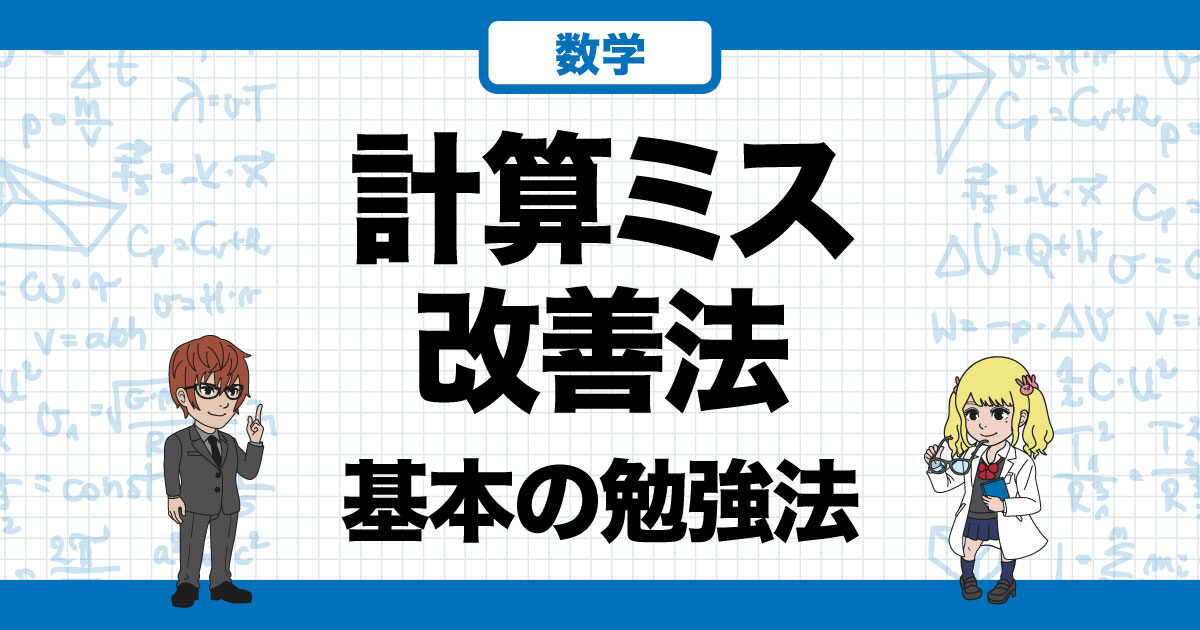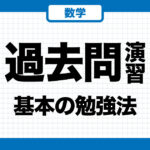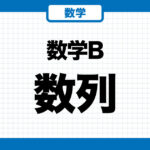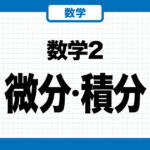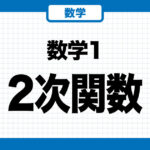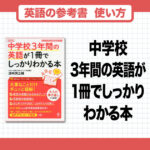受験数学を解くうえで、確実に解消しておきたいのが「計算ミス」です。公式や定理をしっかり理解していても、数字がひとつ違っただけで答えが全く違うこともあります。
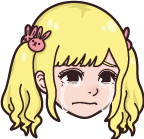
このように、細かい計算ミスで悔しい思いをした受験生もたくさんいるでしょう。
計算ミスをしている人の中には「小学生のときから計算ミスが多いから改善を諦めている・・・」という人も多いはず。
しかし計算ミスは、それ単体で減点されるだけでなく、問題を解くスピードも遅くして結果的に他の部分の得点も下げる原因になるため、絶対に改善しなければなりません。
もちろん、多少は「大雑把な性格だから計算ミスしやすい」というような部分もあります。それでも、正しい手順で勉強すれば計算ミスは確実に減らせます!

今回の記事では、数学の計算ミスを減らすための具体的な勉強方法を解説します!
計算ミスを減らす具体的な手順
計算ミスを減らすには、具体的に以下のステップで勉強しましょう!
- ステップ1
- 演習する際は常に自力で計算をする
- ステップ2
- どんなミスをしているか把握する
- ステップ3
- キレイな字や図で書く
- ステップ4
- 見直しの時間を作る
ステップ1.演習する際は常に自力で計算をする
まずは演習する際には必ず自力で計算をしましょう。普段から自力で計算している人は、いつも通りの感覚で問題を解き進めればOKです。
自力で計算を解いたら答え合わせをしましょう。この答え合わせの際、間違えた問題については注意が必要です。
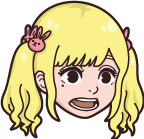
基本的には、解答を見て答えが合っているかをチェックすればOKです。ただし、間違えた問題については「答えを見て終わり」「解き方を理解して終わり」となってはいけません!間違えた問題の答えだけでなく、計算部分もしっかりチェックして、もう一度自力で計算しましょう。
答えを理解したつもりになっていても、意外と細かい計算ができないということはよくあります。

また「答えだけをチェックして終わり」ということを続けると、自力で計算して正解した人と比べ、計算の経験数が少なくなります。自力での計算回数が少ないと、あとから大きな差となって、受験当日に計算ミスをする原因になるかもしれません。
間違えた問題は解説を閉じて、自力で計算しておきましょう。こうした計算練習の積み重ねが、入試本番での計算ミス防止につながります。
ステップ2.どんなミスをしているか把握する
自力で計算をして答え合わせまで終えたら、次に「どんなミスをしていたか?」をチェックしましょう。
普段どんな計算ミスをしているかパッと「すべて」答えられますか?
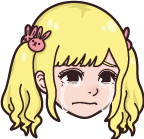
1つ〜2つくらいは挙げられるかもしれませんが、自分の普段の計算ミスをすべて洗い出すのは難しいですよね。
具体的な対策方法を考えるためにも、ミスの内容はその都度ノートに書き出しましょう。
例えば、
- 移項のときに符号をミスった
- 行が変わるときに書き写し間違えた
- 問題文の数字を見間違えた
などをできるだけ具体的にノートにまとめます。同じミスをする度に「正」の字などでカウントしていけば、「自分がどんなミスを何回しているのか?」を正確に把握できますよ!
具体的なミスの内容まで書き出せれば、「計算ミスを直す手順の8割はクリアした」と言っても過言ではありません。
ステップ3.計算過程をキレイな字で書く
具体的なミスの内容を書き出したら、把握した内容を活かしながら問題に取り組んでいきましょう。問題を解く際は、必ず「計算過程をキレイな字で書く」ということが大切です。
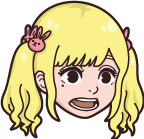
という人もいるでしょう。しかし、計算過程を書く習慣がなければ、「どういうミスをしているのか?」を把握できません。
計算過程を書くときには、丁寧にキレイな文字で書きましょう。
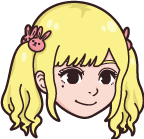

ある程度学力が伸びてくると、「問題自体が分からなくてミスをする」ということは減るでしょう。それでも最後まで残るのが「数字や文字の写し間違いによるミス」です。
写し間違いによるミスは、文字をキレイに書きさえすれば防げるため、ここで得点を失うのはもったいないですよね。
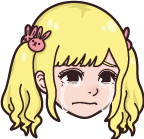
と思う人もいるでしょう。しかし実は、文字を「キレイに書く」「雑に書く」という違いだけで、問題を解くスピードはほとんど変わりません。
むしろ毎回の計算式をキレイに書くほうが、余計なミスが減ってスピードが上がることすらあります。普段からキレイに計算式を書く練習をしておけば自然とスピードが上がり、入試本番でもキレイな字でスラスラ書けるようになるでしょう。
入試本番で計算ミスをなくすためにも、日頃から文字や数字をキレイに書くことが大切です。

キレイな図やグラフが描けていれば、ミスが減ることはもちろん、解き方の手順が思いつきやすくなったり、それっぽい値から解き方を逆算したりすることも可能です。逆に雑な図を描いていると、「直角ではない所を直角と勘違いしてしまう」のようなミスも起こりやすくなってしまいます。
図やグラフも普段からキレイに描く練習をしておかないと、本番で対応できません。
ステップ4.見直しの時間を作る
計算を終えたら、必ず見直しの時間も作りましょう。「1問につき10秒だけ」でもOKです!自分がやりがちな計算ミスや、それに関連しそうな部分を見直す習慣を身に付けておけば、徐々に「やりがちなミス」を減らすことができます。
また、計算ミスの見直しをすることで、実は「計算練習に取り組んだ」のと同じ効果があります!
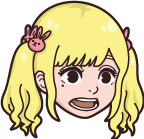

確かに1回1回の見直し自体は大した量ではありません。しかし、その1回1回の小さな見直しが、受験までに何百・何千問分と積み重なれば、本番で計算問題を解く際に大きな差につながります。

「計算ミスかと思ったら違う原因で間違えていた!」ということもある
ここまでで、具体的な計算ミスの勉強方法を解説してきました。せっかく公式を理解しているのに、細かい計算ミスで得点を失うのはもったいないです。上記で紹介した手順を意識して、計算ミスを減らしましょう。
しかし実は、計算ミスと思っているものが「実は計算ミスではない」ということもよくあります。
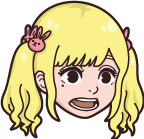
「計算ミス以外で間違えていた」という原因としては、以下の2つがよく挙げられます。
- 公式の理解不足
- 公式の暗記不足
例えば、因数分解や三角関数の加法定理の公式を使う際に、
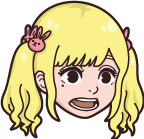
となったり、数列の和の公式で
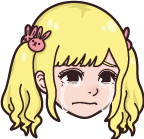
などと分からなくなるのは、計算ミス以前に公式の理解や暗記が不足している証拠です。もし迷ったとしても、公式の導出法まで理解できていれば、その場で導出することもできるでしょう。また、そもそも公式を暗記できていれば、迷うことはありません。
「公式の導出ってどうやるの?」「公式ってどうやって使うの?」などを理解するには、以下の記事を参考にしてみてください!
「公式の暗記が足りていない!」という場合は、問題演習が不足している証拠です。以下の記事を参考にして問題演習に取り組みましょう!

まとめ
今回は、計算ミスを減らす4つのステップを紹介しました!
- ステップ1
- 演習する際は常に自力で計算をする
- ステップ2
- どんなミスをしているか把握する
- ステップ3
- キレイな字や図で書く
- ステップ4
- 見直しの時間を作る
計算ミスを減らせば、得点が伸びるのはもちろん、勉強スピードが上がったりテストや模試で問題を解く時間を短縮できたりします。1問1問は小さいですが、受験までに数千問と解くことで大きな差をつけられるため、日頃からコツコツ積み重ねましょう!
また、計算ミスではなく「そもそも公式の理解や暗記が不十分だった」という場合も、しっかり自分のレベルに合わせて勉強することが大切です。
細かいミスとごまかさずに必要な「理解」や「暗記」にも時間を使うようにしてくださいね!
計算ミスを減らして模試やテストはもちろん、入試本番でも実力を100%発揮できるようになりましょう!
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば数学の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
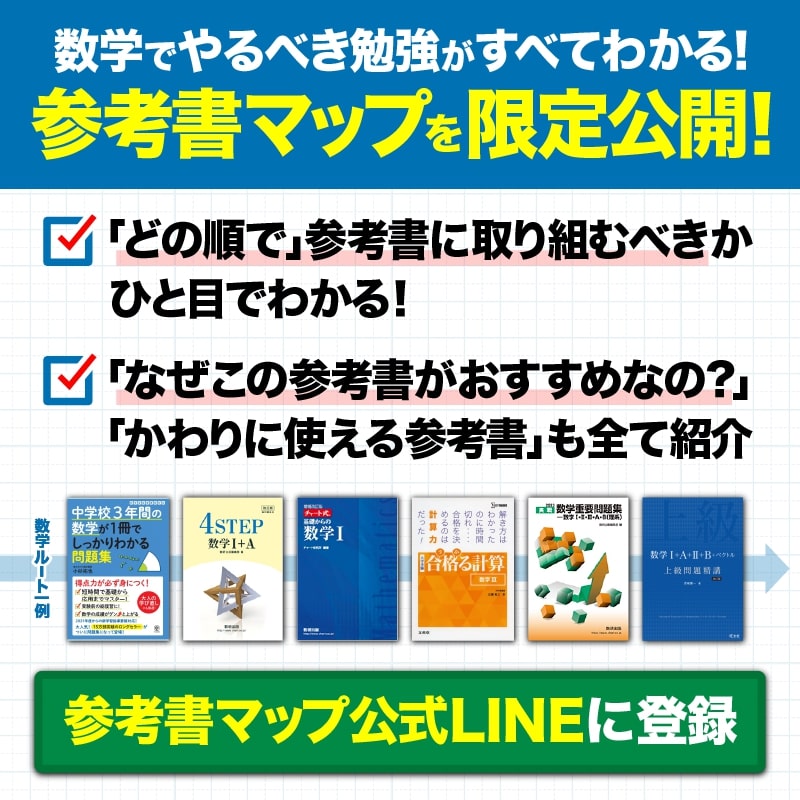
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る