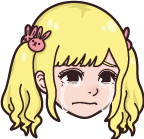

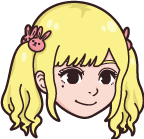

物理は得点が取れるようになるまで、少し時間のかかる科目です。しかし、正しい勉強法を使って得意分野にできれば、誰でも満点を狙える科目でもあります。一方で正しい勉強法で勉強しないとなかなか成績が上がらず、モチベーションもどんどん低下することもあるでしょう。
今回の記事では、学校の定期テストくらいの高校初級レベルから難関大入試レベルまでについて、「どの参考書を使って・どんな順番で・どのように勉強していくか?」を具体的に解説します。
勉強する前にまずは「物理の特徴3つ」を理解することが重要!

物理の勉強の主な特徴は以下の3つです。
- 計算が多くて暗記は少ない
- 入試の大問数は少ないが「関連性のある小問」が連なって出題される
- 頻出分野とそうでない分野の偏りがある
計算が多くて暗記は少ない
物理は数学と比較的似ている科目です。基本的には「公式を理解&暗記する→覚えた内容を組み合わせて解く」という流れで問題に取り組みます。
そのため、暗記だけで解ける知識問題は少なく、「公式を具体的にどう使うのか?」という運用方法を理解し計算しなければなりません。このように数学と似ている部分が多いため、「数学が苦手だと物理も苦手になりやすい」という傾向にあります。
とはいえ、数学と比べれば覚えるべき内容はそこまで多くないため、正しく勉強すれば得点にも繋がりやすいです。

入試の大問数は少ないが「関連性のある小問」が連なって出題される
物理の大学入試では、大問が3~4つくらい出題されます。各大問の中では「易しい小問から難しい小問が連なって出題される」ということがメインです。
各小問同士の繋がりが強いため、例えば「小問1で間違えたら小問2以降の問題すべてが不正解」ということも珍しくありません。つまり、応用問題だけを解けても意味がないのです。基本問題を「正確に解ける」ということも、かなり重要になります。
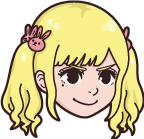
頻出分野とそうでない分野の偏りがある
物理には、大きく5つの分野があります。そして、その中でも圧倒的に出題頻度が多いのは「力学」と「電磁気学」です。
大学入試では例えば
- 大問が3つ出題される大学→「力学」「電磁気学」+「他の分野」
- 大問が4つ出題される大学→「力学」「電磁気学」+「他の分野2つ」
のような出題なることも多く、力学と電磁気だけで50~66%の得点が取れてしまいます。
理系の大学入試では60~70%くらい取れれば受かる大学が多いため、この「力学と電磁気でいかに得点できるか?」ということが重要だとわかりますね。
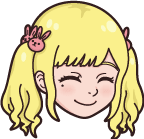
高校物理の5分野の特徴は?
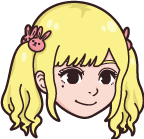

高校の物理には以下の5分野があります
- 力学
- 熱力学
- 波動
- 電磁気学
- 原子物理
それぞれの特徴を簡単に見ていきましょう。
力学の特徴
力学は、大学入試で最も頻出される分野です。しかも、他の分野との融合問題も出題されやすい傾向にあります。具体的には「物体がどのような力を受けて、どのように運動するのか?」を扱うことになります。

しかも、力学は高校物理の中で最初に習う分野です。そのため「なんとなく苦手だけどまあ大丈夫かな」と油断しているうちに力学の範囲が終わってしまい、その後の分野をほとんど理解できないということもあります。
物理の勉強全体に影響を与えるため、とにかく力学だけは最重要視して勉強しましょう!
熱力学の特徴
高校物理の熱力学では、「気体がどのように変化するか?」を扱います。「圧力や温度、体積を変化させるとどのような力を出力するか?」「どのような変化を起こすのか?」などを、限られた公式から考えていく分野です。
覚えなければならない公式数は最も少ないため、集中して勉強すれば、習得にそこまで時間はかかりません。
波動の特徴
波動は、波の性質を考える分野です。
身の周りには「(海や川などの)波」「音」「光」など、さまざまな波があふれています。そういったさまざまな種類の波による現象を「どのように数式的に表現できるか?」を考える分野です。

覚えるべき公式や公式の使い方は、力学や熱力学に比べるとやや多めで、典型的な実験も覚える必要があります。
電磁気学の特徴
先ほども解説したように、電磁気学は最重要分野の2つ目であり、入試でも頻出です。
中学で出てきた回路と電流の関係を扱う分野もあれば、電磁波といった目に見えないものを扱う分野もあります。いずれにしても、力学などと違って電流も電磁波も直接は見れないため、公式やその使い方をなかなかイメージできず、苦労する人も多いです。
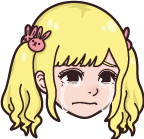
しっかり勉強しないと幅広い出題に対応できず、物理の中でも実力を伸ばすのに一番時間がかかってしまうでしょう。
原子物理の特徴
原子物理は「原子や電子サイズでどんな現象が起こっているのか?」を、数式を使って説明する分野です。
高校物理の中では最後に勉強するため、どうしても手薄になりがちです。個別試験で出題されることは少ないですが、共通テストでは必ず出題されるため対策しないわけにはいきません。
範囲自体は広くないですし、難しい問題もそこまで出題されないため、正しく勉強すればきちんと得点が取れる分野です。
高校初級から大学受験レベルまでの物理の勉強法4ステップ
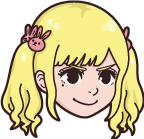

物理の勉強法の全体像は以下の通りです。
教科書レベルの理解
↓
定石理解・暗記
↓
入試レベル問題演習
↓
過去問演習
物理の勉強では、教科書の基礎や定石を固めた後に実際の問題演習に取り組む、という流れが基本です。先ほども解説したように、物理では大問の中に基本的な小問が連なっていることが多いため、まずは基礎からしっかり固めることが重要です。
それでは、それぞれ詳しく勉強法を見ていきましょう
教科書レベルの理解とは?
教科書レベルの理解は、物理の勉強すべての基礎になる部分です。基本的な内容を完璧に理解していない状態で問題演習に取り組んでも、すぐに手が止まったり、解説を読んでも内容を理解できなかったりするため、なかなか成績が伸びません。
教科書レベルの理解を行う際は、映像授業や講義系参考書などで勉強しましょう。この記事の後半でおすすめの教材も紹介します。
具体的な教科書レベルの理解の勉強法などについては以下の記事で解説しています!
定石理解・暗記とは?
定石理解・暗記とは、学校の授業や映像授業などを活用して理解した教科書レベルの内容を、「実際の問題でどう使うのか?」という点を理解し暗記することです。
物理は数学と同じくたくさんの公式が出てきます。しかし、実際のテストで「公式に数字を少し当てはめれば解ける」という問題はほとんど出題されません。数学でも、公式に当てはめるだけで解ける問題は出題されませんよね。
テストや模試では、公式を使って解く典型的な問題(=定石)が存在します。その定石を理解し暗記することで、テストや模試で得点できるようになるのです。定石を理解して暗記するためには、実際に自分の手で問題を解いて理解し、暗記することが必須です。
具体的な定石理解・暗記の勉強法などについては以下の記事で解説しています!
入試レベル問題演習とは?
学校のテストや模試で基本的な問題を確実に正解できる状態になったら、入試レベルの問題演習に取り組みましょう。入試レベルの演習に取り組むことで、過去問で高得点を狙えるようになります。
物理は、大問の出題数が3~4問と少ないケースがほとんどです。その各大問では後半に進むにつれて、難しい内容の小問が出題されるようになります。少ない大問数の中で高得点を取るには、この難しい問題に正解することが必須です。
ただし、物理では典型的な問題を確実に解けるだけでも、多くの大学を突破できます。そのため、後半の難問を解けることも大切ですが、きちんと基礎的な典型問題にも対応できるようにしましょう。
具体的な問題演習の勉強法などについては以下の記事で解説しています!
過去問演習とは?
過去問演習は、入試レベルの問題演習も終えた後に総仕上げとして取り組む勉強です。時間を測りつつ本番同様の環境で問題を解くことで、実際の出題傾向を把握し当日も落ち着いて対応できるようになります。
物理のレベル別おすすめ参考書
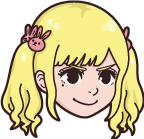

以下3つのステップでおすすめの参考書を紹介します。
- 教科書レベルの理解
- 定石理解・暗記
- 入試レベル問題演習
教科書レベルの理解
教科書レベルの理解では、映像授業なら『スタディサプリ』がおすすめです。
月額料金を支払えば、レベルの高い映像授業を自分の好きなタイミングで視聴して勉強できます。具体的には以下の手順で勉強しましょう。
- ステップ1
- テキストを印刷する
- ステップ2
- 集中して映像授業を視聴する
- ステップ3
- 授業で解説された問題を自力で解く
- ステップ4
- 確認問題を解く
具体的な使い方は以下の記事で解説しています!
『スタディサプリ』などの映像授業が自分に合わない場合、講義系参考書である『宇宙一わかりやすい高校物理』で勉強してもOKです!
講義系参考書とは、講義口調で内容が書かれた参考書です。教科書よりもわかりやすく新単元を学習できます。具体的には以下の手順で勉強しましょう。
- ステップ1
- 飛ばさず全て読む
- ステップ2
- 例題を自力で解く
- ステップ3
- 確認問題を解く
定石理解・暗記
定石理解・暗記の勉強では、学校で配られる『セミナー』『リードα』『ニューグローバル』などがおすすめです。ボリュームが分厚いため終わらせるのは大変ですが、大量の問題を解いて定石を身に付けられるため、取り組んでおきましょう。
学校で配られていないなら、個人で購入できる『エクセル物理』もおすすめです。
「分厚い問題集が苦手」という場合は、比較的薄い『物理のエッセンス』『良問の風』を使って演習してもOKです。
具体的には以下の手順で勉強しましょう。
- ステップ1
- 時間を計りながら問題を解く
- ステップ2
- 解説を丁寧に読む
- ステップ3
- 間違えた問題を解き直す
- ステップ4
- 間違えた問題に印をつける
- ステップ5
- ステップ1.に戻り2周目
各問題集の具体的な使い方については、それぞれ以下の記事で解説しています!
セミナー
リードα
ニューグローバル
エクセル
物理のエッセンス
良問の風
入試レベル問題演習
入試レベル問題演習の勉強では、『重要問題集』『名問の森』『難問題の系統とその解き方』がおすすめです。
『重要問題集』は毎年新版が発売さfれており、最新の入試状況が丁寧に反映されています。収録されている問題は基本的に問題文が長いため、難関大の過去問で頻繁に出題される傾向に慣れることができるでしょう。
『名問の森』は、長年旧帝大や早慶などの難関大受験生から評価されている参考書です。『重要問題集』より問題文がやや短いため取り組みやすいです。
『難問題の系統とその解き方』は、受験最難関レベルの問題集です。収録されている問題のすべてが東大・京大レベルであり、問題数も非常に多いため1周取り組むのも大変でしょう。進めるのに時間がかかるため、最難関大学が志望であり「物理を得点源にしたい!」という人だけが取り組みましょう。
勉強方法は次の通りです。
- ステップ1
- 時間を計りながら問題を解く
- ステップ2
- 解説を丁寧に読む
- ステップ3
- 間違えた問題を解き直す
- ステップ4
- 間違えた問題に印をつける
- ステップ5
- ステップ1.に戻り2周目
各問題集の具体的な使い方については、それぞれ以下の記事で解説しています!
重要問題集
名問の森
難問題の系統とその解き方
物理を勉強するときの注意点

物理の勉強で気を付けるべきことは以下の3つです。
- 必ず自力で図を描いて解く
- 必ず自力で計算する
- 成績が伸びる瞬間まで耐える
必ず自力で図を描いて解く
物理は自分で図を描きながら問題を解くことが大切です。
物理を勉強したての人がつまずく原因のほとんどが「力の矢印を図示できない」ことです。力学では「何の力が・どの方向に・どれくらいの大きさで働くか?」という点をきちんと図に落とし込まなければ、必ず立式で間違えます。
さらに難しい問題になると、図を描かないと「問題文の実験設定が整理できない」という状況に陥ります。正しく実験設定を理解できなければ、もちろん正しく答えは導けません。
どのような問題でもスムーズに解けるよう、「授業で見た図」や「問題集の解説に載っている図」を自力で描けるようになることが重要です。
必ず自力で計算する
物理では、図と公式を使って式を作れれば、あとはそれを解くだけです。実際に式を解く際に必要なものが「計算力」です。
物理では数学ほど難しい計算が出題されるわけではありません。しかし正しく計算できないと、例えば「小問1で凡ミスして小問2以降で全滅する」ということが、物理ではよく起こります。
また、計算のスピードも重要です。特に大学入試の個別試験で物理と化学の2科目が必要な場合は「どれだけ物理を早く解けられるか?」という点が理科で高得点を取る鍵になります。
いずれも計算力が必要なので、演習をするときに計算をサボらず少し面倒でも手を動かしましょう。
成績が伸びる瞬間まで耐える
物理の問題では、知識だけで解ける穴埋め問題などはほとんど出題されません。そのため、少し勉強したくらいではあまり点数は伸びないでしょう。
物理の成績は伸びるときは一気に伸びますし、伸びるタイミングに到達していなければ、いくら勉強しても成績に反映されません。少なくとも問題集を1周したくらいでは成績は大して伸びないため、最低でも2~3周は繰り返し、成績に反映されるまでは耐え続けて勉強しましょう!
まとめ
物理は以下の特徴を持つ科目です。
- 計算が多くて暗記は少ない
- 入試の大問数は少ないが「関連性のある小問」が連なって出題される
- 頻出分野とそうでない分野の偏りがある
以下の流れで勉強することで、身につけた知識を実際の問題で柔軟に活かして解けるようになるでしょう。
教科書レベルの理解
↓
定石理解・暗記
↓
入試レベル問題演習
↓
過去問演習
物理の問題を解く際は、実際に図を描いて自力で計算することが大切です。成績が伸びるまで多少時間がかかりますが、めげずに2〜3周は参考書に取り組みましょう!
もっと具体的に「このとおりに勉強すれば物理の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!
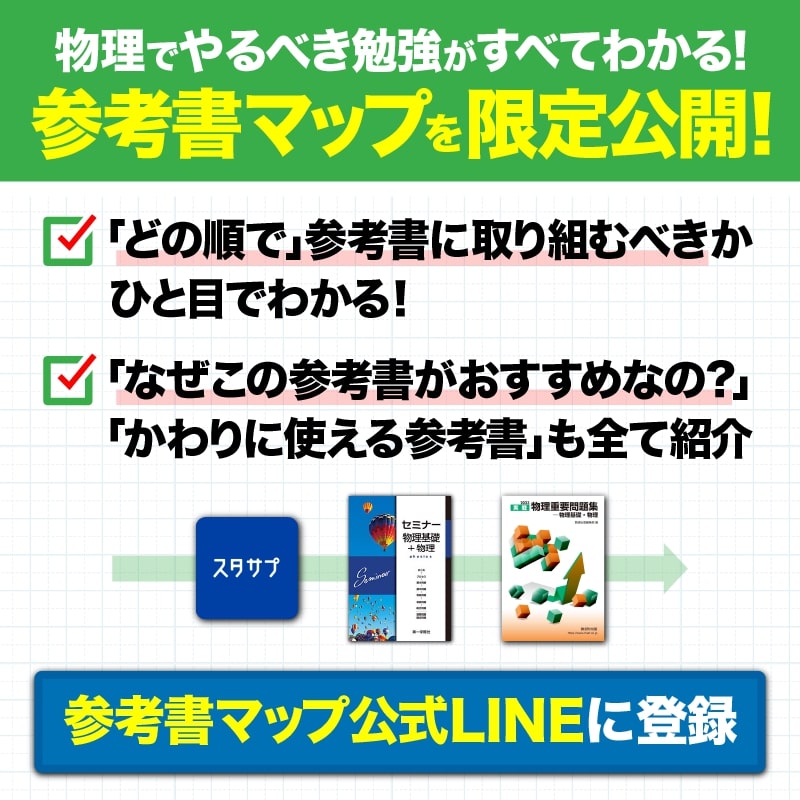
■ 参考書マップとは? ■
STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。
- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!
- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介
STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!
LINEに登録して参考書マップを見る






















